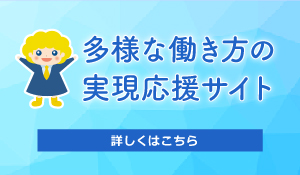
「多様な正社員」制度導入支援セミナーの資料・動画を掲載(多様な働き方の実現応援サイト)(2024/2/21更新)
厚生労働省の「多様な働き方の実現応援サイト」では、令和5年11月20日に開催された「多様な正社員」制度導入支援セミナーの資料・動画を掲載しております。
本セミナーでは、多様な人材活用のヒントとなるよう、「多様な働き方」に関するトレンドや、勤務地や職務内容、勤務時間などを限定した「多様な正社員」制度のポイント、実際に「多様な働き方」を実践されている先進事例などを紹介しています。
令和5年度の第1回目の内容は、以下の通りです。
・基調講演「多様な正社員」制度の導入に向けて
・事例紹介 企業事例のご紹介(2社)
・パネルディスカッション
以下よりご確認ください。
「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」の全業種版のご紹介(2024/2/5更新)
いわゆる正社員と非正規雇用の労働者との働き方の二極化を緩和し、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保や定着を同時に可能とするような、労使双方にとって望ましい多元的な働き方の実現が求められています。
そうした働き方や雇用の在り方の一つとして、職務、勤務地、労働時間を限定した「多様な正社員」の普及を図ることが重要となってきています。
今回、「多様な正社員」及び労働契約法に定める「無期転換ルール」について、企業での制度導入支援を支援するツールとして、「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」の全業種版について改訂が行われました。
本冊子では、「多様な正社員」制度の導入・運用、「無期転換ルール」への対応を円滑に行うために、就業規則見直しのガイドとなる規定例が掲載されております。
規定例は、「多様な正社員」制度の導入や「無期転換ルール」への対応に際して、必ず明示していただきたい「必要事項」と、有期契約労働者を活用する観点から考えていただきたい 「検討事項」に分けて整理されております。
また、本冊子は、導入を検討している「多様な正社員」制度、「無期転換ルール」に応じて、該当する箇所をお読みいただくことにより、必要な知識を得ることができるように構成されております。
以下の内容が掲載されております。
第1章 多様な正社員制度・無期転換ルールとは
第2章 多様な正社員制度・無期転換ルールの導入手順
第3章 多様な正社員・無期転換ルール導入のためのモデル就業規則と解説
第4章 多様な正社員制度・無期転換ルールの運用・改善に向けた事例紹介と解説
詳細は、以下よりご確認ください。
有期契約労働者の無期転換サイトがリニューアルされました(2023/7/10更新)
有期契約労働者の無期転換サイトがリニューアルされました。
無期転換ルールとは労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。
WEBサイトは、以下のような内容で構成されております。
〇契約社員・アルバイトの方向け
・無期転換ルールとは
・無期転換社員の声
・各種お問合せ
〇事業主・人事労務の方向け
・無期転換ルールとは
・導入のポイント
・導入企業事例
・無期転換社員の声
・導入支援策
・無期転換ルールの特例
・各種お問い合わせ
〇Q&A
・契約社員・アルバイトの方向けQ&A
・事業主・人事労務の方向けQ&A
2024年4月からは、労働条件明示のルールが変わり、「無期転換申込機会の明示」が無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに必要となるため、有期契約労働者からの無期転換に関する問い合わせが増えることが予想されます。
上記のWEBサイトを参考にされてみてはいかがでしょうか。
Google マップは現在の Cookie 設定では表示されません。「コンテンツを見る」を選択し、Google マップの Cookie 設定に同意すると閲覧できます。詳細は Google マップの[プライバシーポリシー]をご確認ください。Cookie の利用は、[Cookie 設定]からいつでも変更できます。



