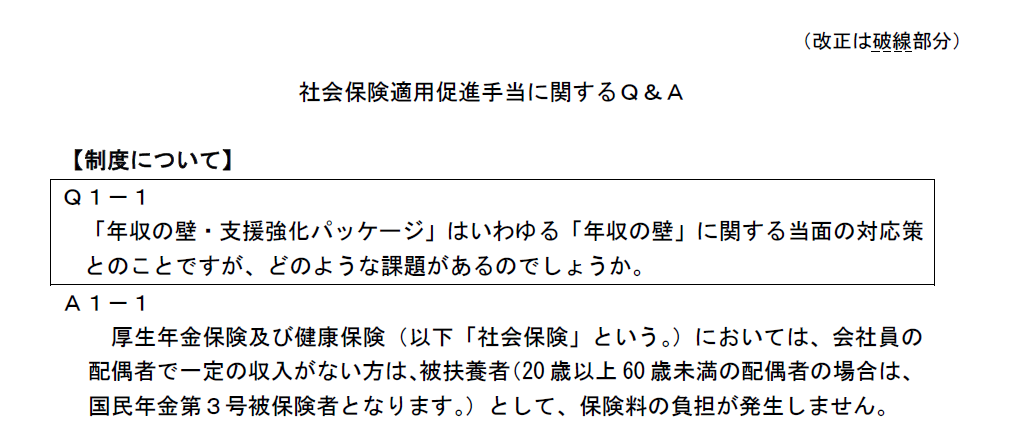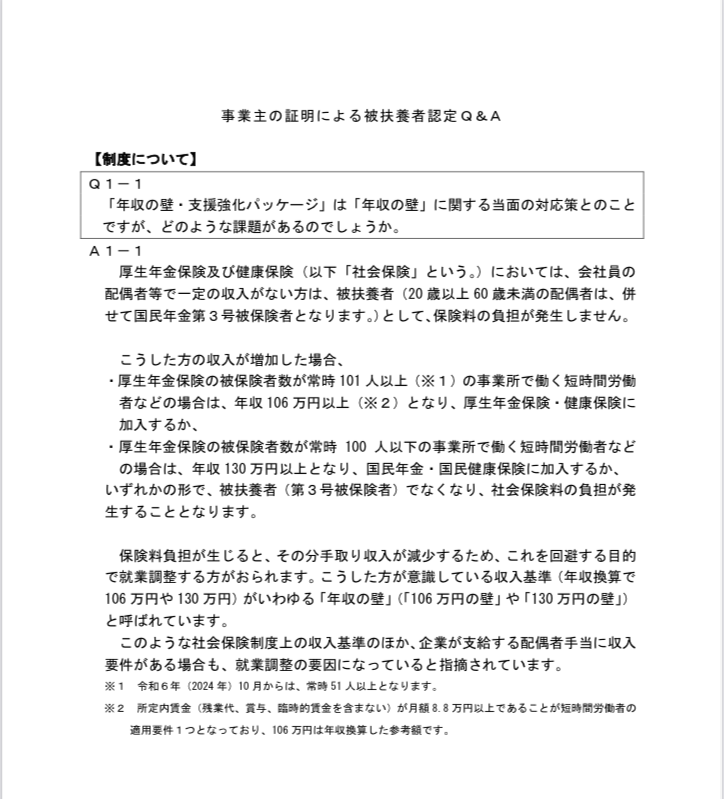19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更について(2025/8/23更新)
日本年金機構は、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更に関するお知らせを掲載しております。
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
◎変更内容
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
※年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
◆ご参考
現行の収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
上記の変更に関し、Q&Aも掲載されております。
記載時点で以下の6つが掲載されております。
・今回(令和7年10月)の変更の対象に配偶者は含まれないのですか。
・今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。
・年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。
・年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取り扱いと同様に、過去1年間の収入で判定するのですか。
・12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのですか。
・令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのですか。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
高年齢雇用継続給付、介護休業給付のリーフレット(令和7年8月1日版)に更新(2025/8/20更新)
厚生労働省は、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、介護休業給付)のリーフレットを令和7年8月1日版に更新しております。
・高年齢雇用継続給付についてのリーフレット
高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付金です。
・介護休業給付についてのリーフレット
被保険者の方が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと支給される給付金です。
詳細は、以下よりご確認ください。
外国人労働者の雇用保険手続きに関するリーフレットのご紹介(2025/8/13更新)
厚生労働省は、事業主の皆様あてに、「外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」というリーフレットを作成し公表しております。
労働関係法令および社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。
以下の要件に該当する労働者は、外国人であっても、原則として、雇用保険の被保険者となります。
※ただし、出向等で日本に駐在している外国人であって、母国の失業補償制度に加入している方は日本の雇用保険の加入対象とはなりません。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込みがあること
リーフレットでは、「雇用保険の適用要件」、「雇用保険加入手続き時の注意点」、「外国人の雇用保険被保険者資格取得届の記入方法」などが記載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001530992.pdf
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(2025/7/28更新)
厚生労働省は、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の通達(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)を令和7年7月24日に掲載しております。
本通達は、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19 歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」と いう。)が19歳以上23歳未満である場合における取扱いを定めたものです。
1.認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするも のについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52 年通知と同じと すること。
2.船員保険法第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。
3.上記の取扱いは、令和7年10月1日から適用すること。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付の支給限度額変更に関するリーフレットのご紹介(2025/7/25更新)
厚生労働省は、「高年齢雇用継続給付金」、「介護休業給付金」、「育児休業等給付」の受給者の皆さまに向けた、令和7年8月1日からの支給限度額変更に関するリーフレットを作成し公開しております。
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付については、支給限度額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、その額が変更されます。
〇高年齢雇用継続給付(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額:376,750円 → 386,922円
最低限度額:2,295円 → 2,411円
60歳到達時の賃金月額 上限額:494,700円 → 508,200円
下限額: 86,070円 → 90,420円
〇介護休業給付金
支給限度額 上限額:347,127円 → 356,574円
〇育児休業等給付
・出生時育児休業給付金
支給上限額(支給率67%):294,344円 → 302,223円
・育児休業給付金
支給上限額(支給率67%):315,369円 → 323,811円
(支給率50%):235,350円 → 241,650円
・出生後休業支援給付
支給上限額(支給率13%):57,111円 → 58,640円
・育児時短就業給付(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額:459,000円 → 471,393円
最低限度額: 2,295円 → 2,411円
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001520023.pdf
雇用保険の基本手当日額の変更について(2025/7/24更新)
厚生労働省は、8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。
1. 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60 歳以上65 歳未満 7,420円 → 7,623 円 (+203円)
45 歳以上60 歳未満 8,635円 → 8,870 円 (+235円)
30 歳以上45 歳未満 7,845円 → 8,055 円 (+190円)
30 歳未満 7,065円 → 7,255 円 (+190円)
2. 基本手当日額の最低額の引上げ
2,295 円 → 2,411円(+116円)
詳細は、以下よりご確認ください。
届書作成プログラム(Ver30.10)を公開(日本年金機構)(2025/7/17更新)
日本年金機構は、届書作成プログラムを更新し、Ver30.10を公開しております。
留意事項として、以下の2点が記載されております。
・旧バージョン(Ver28.00以前)での申請は、令和7年2月28日をもって受付を終了しましたので、更新してください。
・届書作成プログラム(Ver29.00)で作成される電子申請および電子媒体申請用データ(CSV、CD/DVD)では、「資格取得届・70歳以上被用者該当届(健康保険組合提出用)」に「資格確認書発行要否」項目が追加されていません。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20250714.html
「社会保険の加入対象の拡大について」特集ページのご紹介(2025/7/4更新)
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
厚生労働省では、本改正に関する特集ページを作成し公開しております。
以下の4つの特集ページが公開されております。
・社会保険の加入対象の拡大について
・在職老齢年金制度の見直しについて
・将来の基礎年金の給付水準の底上げについて
・厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて
本日は、「社会保険の加入対象の拡大について」ご紹介します。
社会保険の加入対象の拡大についての法改正の概要は以下の通りです。
① 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃する。
② 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。
※ 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。
③ 適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。
本特集ページは、以下の内容で構成されております。
1.そもそも現行の社会保険の加入対象は
2ー①.今回の加入拡大の対象となる方ー短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃
2-②.今回の加入拡大の対象となる方ー短時間労働者の賃金要件を撤廃
2-③.今回の加入拡大の対象となる方ー個人事業所の適用対象を拡大
3.社会保険加入のメリット
4.社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者の、就業調整を減らすための支援策について
5.よくあるご質問ー配偶者の扶養(第3号被保険者)のままで働けなくなるのですか?
法律に関する参考資料
図が用いられてわかりやすく解説されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年度の算定基礎届のご提出についての案内を掲載(日本年金機構)(2025/5/30更新)
日本年金機構は、令和7年度の算定基礎届のご提出についての案内を掲載しております。
令和7年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(木曜)です。
6月中旬より順次様式等が送付される予定です。
これに合わせて、算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等を公開しております。
主に以下のような資料が掲載されております。
・令和7年度算定基礎届事務説明【動画】
・算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和7年度)(PDF)
![]() ・算定基礎届等の提出のお願い(ターンアラウンド届出用紙を送付した事業主様向け)(PDF)
・算定基礎届等の提出のお願い(ターンアラウンド届出用紙を送付した事業主様向け)(PDF)
![]() ・算定基礎届等の提出のお願い(電子申請を使用して届出を行う事業主様向け)(PDF)
・算定基礎届等の提出のお願い(電子申請を使用して届出を行う事業主様向け)(PDF)
・標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いに関する事例集(PDF)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)について(パブコメ)(2025/5/20更新)
厚生労働省は、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)について、パブリックコメントによる意見募集を行っております。
健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定について、令和7年度税制改正において、19 歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者が19歳以上23歳未満である場合における取扱いを以下の通り定めるものです。
1.認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするも のについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150 万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じとすること。
2.船員保険法第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。
3.上記の取扱いは、令和7年10月1日から適用すること。
詳細は、以下よりご確認ください。
労働保険の電子申請に関する特設サイトのご紹介(2025/5/6更新)
厚生労働省は、労働保険の電子申請に関する特設サイトを開設しております。
労働保険に関する申請や届出について、書面での手続ではなく「電子申請」を使うことで、インターネットを経由して「カンタン・便利に」手続できます。
自宅やオフィスなどから、「e-Gov」サイトにアクセスし、24時間いつでも申請や届出ができます。
〇労働保険の電子申請 3つのメリット
・スピード申請
大量の申請書類への記入も簡単&スピーディー。前年度の情報を取り込め、入力チェック機能や自動計算機能で、記入漏れや記入ミスを防げます。
・いつでもどこでも手続き可能!
労働局や労働基準監督署などの窓口に出向く必要はありません。窓口での待ち時間がなく、自宅やオフィスにいながら申請や届出ができます。しかも24時間365日、いつでも手続が可能です。
・無駄な時間・コストの削減
申請・届出用紙の入手は不要。窓口で並ぶ時間や窓口までの移動費などを大幅に削減でき、総務担当者の業務改善につながります。
労働保険の電子申請に関する動画や労働保険の電子申請申請の進め方などが掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年度社会保険制度説明会の開催に関する情報を掲載(日本年金機構)(2025/4/18更新)
日本年金機構は、令和7年度社会保険制度説明会の開催に関する情報を掲載しております。
令和7年6月に「社会保険制度説明会」が開催されます。本説明会では事業主、社会保険事務担当者の皆さまに向けた、さまざまなプログラムを用意されております。
本説明会で予定さえているプログラムの一例です。(開催場所によって説明会のプログラムは異なります。)
・オンラインサービス・・・算定基礎届などの手続きの電子申請など機構が提供しているオンラインサービスをご紹介します。
・届出誤りの多い事例・・・正しく届出いただけるよう、届出の誤りが多い事例を紹介します。
・子育て支援のための制度・・・産前産後休業や育児休業時の保険料免除について説明します。
・算定基礎届の作成方法・・・毎年7月に届出いただく算定基礎届の作成方法について説明します。
日程や会場等詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/jimukoshukai.html
「雇用保険に関する業務取扱要領」(令和7年4月1日以降)版に更新(2025/4/11更新)
定期的に内容が更新されている「雇用保険に関する業務取扱要領」が(令和7年4月1日以降))版に更新されております。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いについて解説されたものです。
2025年4月には、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設などの改正が行われました。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いに手続について不明な点があれば、こちらを確認することをお勧め致します。
以下よりご確認ください。
労働保険年度更新に係るお知らせを掲載(2025/4/10更新)
厚生労働省は、労働保険年度更新に係るお知らせを掲載しております。
●令和7年度労働保険の年度更新期間について
令和7年度労働保険の年度更新期間は
6月2日(月)~7月10日(木)です。
※電子申請は6月1日(日)から可能ですが、受付は6月2日(月)となります。
●<申告書の書き方について>
年度更新の書き方は、以下の4種類の申告書の書き方が掲載されております。
・令和7年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
・令和7年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
・令和7年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
・令和7年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方
また、厚生労働省動画チャンネルでは、年度更新申告書の書き方について動画配信しております。
以下の動画が掲載されております。
・令和7年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用編)
・令和7年度労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期事業(建設の事業)用編)
・令和7年度労働保険年度更新申告書の書き方(第3種特別加入(海外派遣)用編)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年4月の電子申請様式の変更等について(日本年金機構)(2025/3/30更新)
日本年金機構は、電子申請時の利便性向上のため、令和7年4月1日に一部の電子申請様式を変更します。
〇ターンアラウンドCDの提供終了にともなう様式変更
被保険者データを収録したCD(ターンアラウンドCD)廃止にともない、電子申請様式においても「新規適用届」「任意適用申請書」「事業所関係変更(訂正)届」にある「媒体作成」欄の選択肢「2.必要(電子媒体)」を「2.必要(社労士電子送付)」に変更します
〇委任状の添付省略にともなう様式変更
被保険者の委任状の添付を省略するため、(健康保険・船員保険・厚生年金保険)「産前産後休業終了時報酬月額変更届」「育児休業等終了時報酬月額変更届」に「届出意思の確認」欄(チェックボックス)を追加します。申請者(事業主等)が被保険者本人からの申出であることを確認した場合は、当該項目にチェックを入れてください。
※e-Govアプリケーションから申請する場合は、手続き名の後ろに「2025年4月以降手続き」と表示されている手続きを選択してください。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20250325.html
令和7年4月1日から現物給与価額(食事)が改正されます(日本年金機構)(2025/3/17更新)
令和7年4月1日(火曜)から現物給与価額(食事)が改正されます。
日本年金機構は、改正後の現物給与価額(食事)について、全国現物給与価額一覧表(令和7年度)を公開しております。
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
現物給与に関するよくある質問をまとめましたQ&Aも合わせて掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html
雇用保険に関する業務取扱要領」(令和7年2月25日以降))版に更新(2025/3/8更新)
定期的に内容が更新されている「雇用保険に関する業務取扱要領」が(令和7年2月25日以降))版に更新されております。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いについて解説されたものです。
2025年4月から施行される以下の法改正事項についての記載が変更されております。
※変更内容
・自己都合離職者が、失業給付(基本手当)の受給に当たって、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除。
※このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付 制限期間を3ヶ月とする。
・就業手当を廃止するとともに、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げる。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いに手続について不明な点があれば、こちらを確認することをお勧め致します。
以下よりご確認ください。
雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和7年3月送付分)に関するFAQについて(2025/3/7更新)
厚生労働省は、雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和7年3月送付分)に関するFAQを公開しております。
記載時点で、23のQ&Aが掲載されております。
Q&Aより一部抜粋してご紹介します。
Q1:「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とはどのようなものですか。
A1:厚生労働省から、全ての雇用保険適用事業所の方に送付しているものです。
令和7年3月送付分については、送付先事業所の令和6年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されており、事業主の方に、万が一手続漏れなどがないか、御確認いただく趣旨で送付しているものです。
Q7:はがきに記載されている令和6年11月末時点の被保険者数(または被保険者数とマイナンバー登録者数)が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
A7:事業所における被保険者情報の照会については、企業固有の情報であるため電話ではお答えできません。お手数ですが事業所を管轄するハローワークに来所または郵送で送付したはがきを提出していただき、適正な届出が行われているかどうか確認してください。はがきを提出いただくと、提示日時点の事業所において雇用保険被保険者資格を取得中の方に係る被保険者のリスト(氏名・性別・生年月日・資格取得日・マイナンバーの登録有無等)をお渡しします。はがきを提出いただく際は、必ず事業主(当該事業所の従業員を含む)であることが確認できる書類を添えてください。
また、代理人(社会保険労務士など)が確認を行う場合には、事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類を添えてください。
なお、郵送の場合、返信用封筒(あて名記載のもの)及び切手(特定記録もしくは書留料金分)を同封してください。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
被保険者データを収録したCDの提供は令和7年3月31日で終了します(日本年金機構)(2025/2/15更新)
日本年金機構は、各種手続きのオンライン化を進めており、令和5年1月から社会保険に関する情報を電子データで受け取ることができる「オンライン事業所年金情報サービス」を開始しています。
本サービスでは、届書作成プログラムで届書を作成する際に使用する被保険者データをオンラインで受け取ることができます。
希望する事業主の方に郵送している被保険者データを収録したCDの提供は、令和7年3月31日(月曜)で終了します。
算定基礎届の提出時や賞与支払予定月に、日本年金機構から被保険者データを収録したCDを受け取っている事業主等の方は手続きが必要となります。
1.「オンライン事業所年金情報サービス」によりオンラインで被保険者データを受け取ることを希望する場合
利用申し込みが必要となります。詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」の算定基礎届および賞与支払届媒体作成欄の「1.不要(自社作成)」を選択し、届出を行ってください。
3.今後は紙媒体で被保険者データの受け取りを希望する場合
「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」の算定基礎届および賞与支払届媒体作成欄の「0.必要(紙媒体)」を選択し、届出を行ってください。
本件に関するリーフレットも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202502/0210.html
令和7(2025)年度 雇用保険料率について(2025/2/11更新)
厚生労働省は、令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内を掲載しております。
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率は以 のとおりです。
・失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更になります (農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000に変更に なります 。)。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
「育児時短就業給付金」に関する新たなリーフレットや様式等を公開(2025/2/7更新)
2025年4月より、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たす場合に、「育児時短就業給付金」が創設されます。
「育児時短就業給付金」に関する新たなリーフレットや様式等が公開されました。
以下の資料が掲載されております。
・2025年4月から 「育児時短就業給付金」を創設します
・転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を 再開する場合の留意点をお示しします。
・育児時短就業給付の内容と支給申請手続(令和7年2月1日時点版)
・育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)
・育児時短就業期間等に係る証明書 (別紙)週所定労働時間算定補助シート
詳細は、以下よりご確認ください。
「マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ」を公開(2025/1/13更新)
厚生労働省は、「マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ」を公開しております。
記載時点で【被保険者の方向けFAQ】Q1~Q8と【事業所の方向けFAQ】Q9~Q13が掲載されております。
【事業所の方向けFAQ】の中から一部ご紹介します。
Q11 マイナンバーの登録を行っていない被保険者について資格喪失届にマイナンバーを記載して提出した場合は、対象となりますか。
A11 マイナンバーの登録にはハローワークにおける確認作業が必要となるため、資格喪失届にマイナンバーを記載いただいても離職票発行までの間にマイナンバーを登録することができず、対象とはなりません。大変お手数ですが資格喪失届提出の2週間程度前までにマイナンバーの登録手続きを行ってください。
Q13 離職者がマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行っており、 事業所が電子申請により離職手続きを行ったにもかかわらず、離職者本人のマイナポータ ルに離職票が送信されていないようです。どのようにすれば良いでしょうか。
A13 離職者の方のマイナポータルのお知らせ容量が上限値を超えている等により送信エ ラーとなっている可能性があります。送信エラーとなっていることをハローワークで確認した場合には、ハローワークから事業所を通じて離職者の方にご連絡いたします。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001367147.pdf
養育期間標準報酬月額 特例申出書の取扱いについて(2025/1/12更新)
厚生労働省は、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額 特例申出書の取扱いについて」の通達を令和6年12月23日付けで出しました。
養育期間標準報酬月額特例申出書について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付を不要とすることとする厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第10条の2の2の改正が令和7年1月1日に施行されました。
本改正に係る事務の取扱いについて、通知されたものになります。(下線は筆者加筆)
1 身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付省略について
養育期間標準報酬月額特例申出書については、(中略)、申出者及びその子の個人番号が記載され、当該情報照会で身分関係が確認できるときは、戸籍抄本等の添付を不要としたところである。 令和7年1月1日からは、当該取扱いに加え、申出者が使用される事業所の事業主が続柄を確認したときは、戸籍抄本等の添付を不要とし、当該情報照会で身分関係が確認できない外国籍の被保険者等の場合においても事業主・被保険者の手続きの負担軽減を図ること。
2 事業主が続柄を確認した申出書の日本年金機構での審査について
日本年金機構での養育期間標準報酬月額特例申出書の審査において、事業主が申出者と子の続柄を確認し、「事業主続柄確認」欄に確認済の記載がある場合は、日本年金機構で続柄を改めて確認することは要しないこと。ただし、個々の審査において必要があると認めるときは、戸籍関係情報の情報照会等により申出者と子の続柄を改めて確認することを妨げるものではないこと。
3 申出様式について
養育期間標準報酬月額特例申出書の様式について、事業主による続柄の確認欄を設けることとする改正を行うこと。 従前の様式は、当分の間これを使用して差支えないこと。また、従前の様式で申出がされた場合において、事業主が続柄を確認済である旨を様式の備考欄に記載したときは、改正後様式で続柄の確認欄に確認済の記載がある場合と同様に取り扱って差し支えない こと。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241225T0040.pdf
賞与支払届等に係る事業主及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて(通達)(2025/1/9更新)
厚生労働省は、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて」の通達を令和6年12月25日付で出しました。
これは、オンライン事業所年金情報サービスによる基本情報(当該事業所の被保険者氏名及び生年月日等の情報)の送付の対象が、 従来の事業主に加えて社会保険労務士に対しても拡大されることに伴い、その対応について記載されたものです。(下線は筆者加筆)
1 令和5年1月から事業主に対してオンライン事業所年金情報サービスによる基本情報の送付が開始されたが、令和7年1月6日より、届書の作成を事業主から受託した社会保険労務士に対しても同サービスによる基本情報の送付を可能とすること。
社会保険労務士に算定基礎届等の届出に必要となる基本情報を送付するにあたっては、届出に係る提出代行に関する証明書により社会保険労務士が事業主から届書の作成を受 託したことを適切に確認の上実施すること。
2 1の取扱いの開始により、事業主及び社会保険労務士のいずれに対してもオンライン事業所年金情報サービスによる基本情報の送付が可能となることから、令和7年3月31日 をもって事業主及び社会保険労務士に対する基本情報を収録した記録媒体の送付は廃止すること。
3 省略
4 事業主又は社会保険労務士に対する基本情報を予め印字した届出用紙の送付に係る取扱いは従来どおり可能とするが、郵便事故による個人情報の漏えいの防止や環境負荷の軽減の観点から、電子送付を利用するよう促すこと。届出用紙を社会保険労務士に対して送付する場合に提出を求める手続については従前と同じ取扱いとし、事業主の同意書は別紙のとおりとする。
5 省略
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241227T0090.pdf
厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(案)について(パブコメ)(2025/1/8更新)
厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(案)に関して、パブリックコメントによる意見募集が行われております。
〇改正の概要
食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額については、1人当たりの食料費(総務省統計局「家計調査」より算出)に、食料に係る都道府県ごとの消費者物価地域差指数(総務省統計局「小売物価統計調査」より算出)を乗じて、都道府県ごとの価額を定められております。
今般、令和5年分の総務省統計局「家計調査」及び総務省統計局「小売物価統計調査」が公表され、上記方法により算出した価額に変更が生じることとなったため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額を別紙のとおり改められる予定です。
〇適用期日
告 示 日:令和7年2月上旬(予定)
適用期日:令和7年4月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年度の保険料率について(案)について(雇用保険部会)(2024/12/25更新)
厚生労働省は、第201回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会の資料を公開しております。
今回、雇用保険制度の財政運営に関する資料が掲載されております。
資料の中で、令和7年度の保険料率について(案)の記載がございますのでご紹介させていただきます。(下線は筆者加筆)
<失業等給付の保険料率について>
・令和6年法改正に伴う影響も考慮した上で、令和7年度以降の雇用保険財政状況の試算を行い、検討を行ったが、
ー 給付制限の見直しに伴う被保険者の行動変容が十分に予測することが困難であること
ー 令和5年度以降受給者実人員が増加傾向であること
等の状況も踏まえ、安定的な財政運営と保険料負担軽減の両立を図る観点から、令和7年度の 保険料率は0.1%引き下げ、0.7%としてはどうか。
<育児休業給付の保険料率について>
・令和7年度以降の財政運営試算の結果を踏まえ、令和7年度の料率は現行の0.4%に据え置くこととしてはどうか。
(出典:第201回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 資料1)
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(協会けんぽ)(2024/12/16更新)
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限についての案内を掲載しております。
令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円となります。
※令和6年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は312,550円となります。(この額は、標準報酬月額の第23級:32万円に該当します。)
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
詳細は、以下よりご確認ください。
被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について(2024/12/12更新)
厚生労働省は、第23回社会保障審議会年金部会の資料を公開しております。
今回は、以下の議題が取り上げられております。
(1)被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について②
(2)基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了 (マクロ経済スライドの調整期間の一致)について②
(3)遺族年金制度について②
この中から、本日は、(1)被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について、資料より一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
1 被用者保険の適用拡大
◆賃金要件の見直しの方向性案
就業調整の基準として意識されていること、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす地域や事業所が増加していることを踏まえ、本要件を撤廃することとしてはどうか。その際、最低賃金の動向次第では週20時間の所定労働時間であっても賃金要件を満たさない場合がありえることから、撤廃の時期に配慮する必要がある等の意見があったことも踏まえ、賃金要件の撤廃によって保険料負担が相対的に過大とならないよう、最低賃金の動向を踏まえつつ、本要件撤廃の時期に配慮してはどうか。また、最低賃金の減額の特例の対象となる賃金が月額8.8万円未満の短時間労働者については、希望する場合に、事業主に申し出ることで任意に被用者保険に加入できる仕組みとしてはどうか。
(出典:第23回社会保障審議会年金部会 資料1)
◆被用者保険の適用拡大の進め方のイメージ
・賃金要件の撤廃
最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす地域や事業所が増加していることを踏まえ、本要件を撤廃してはどうか。その際、最低賃金の動向を踏まえつつ、本要件撤廃の時期に配慮してはどうか。
・企業規模要件の撤廃
本要件の撤廃の際に、短時間労働者が適用の対象となる事業所は50人以下の中小事業所であり、配慮が必要なことから、十分な周知・準備期間を確保してはどうか。
・非適用業種の解消
新たに被用者保険の適用事業所となり、短時間労働者のみならず、いわゆるフルタイム相当の通常の労働者も適用対象となることから、さらに十分な周知・準備期間を確保してはどうか。
2 第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応
◆就業調整に対応した保険料負担割合を任意で変更できる特例(案)
【見直しの方向性】
・現行制度では、被用者保険の保険料は原則として労使折半であるが、厚生年金保険法においては健康保険法のような保険料の負担割合の特例に関する規定はない。被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生・手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、健康保険組合の特例を参考に、被用者保険(厚生年金・健康保険)において、任意で従業員と事業主との合意に基づき、 事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を設けてはどうか。
・労使折半の原則との関係で例外的な位置づけであること等を踏まえて、時限措置とすることとしてはどうか。
①給付について
・本特例を利用しても保険料負担の総額は変わらないため、本特例の適用を受ける者の給付(基礎年金・報酬比例部分)は現行通り 。
②保険料負担について
・本特例を利用した場合、労使の判断で、被保険者本人の保険料負担を軽減し、被用者保険の適用に伴う手取り収入の減少を軽減できる。
ただし、健康保険と同様、事業主が保険料全額を負担し、被保険者負担をなくすことは認めない。
〇特例の適用範囲について
・本特例の適用範囲は、最低賃金の近傍で就労し、被用者保険の適用に伴う「年収の壁」を意識する可能性のある短時間労働者に限定することを念頭に検討。(最大12.6万円の標準報酬月額を想定)
・本特例の適用を受ける被保険者の負担割合について、
▶同一の等級に属する者同士で揃えることとしつつ、
▶等級毎の具体的な割合は、事業所単位で労使合意に基づき任意に設定可能
とする。
・本特例を利用する事業所において、厚生年金保険料と健康保険料のうちどちらか一方にだけ本特例を適用することや、両方ともに本特例を適用しつつ、負担割合を別々に設定することを可能とする。
・健康保険と同じく賞与についても本特例の対象とすることを可能とする。
詳細は、以下よりご確認ください。
明日は、遺族年金制度について触れたいと思います。
希望する離職者のマイナポータルに 「離職票」を直接送付するサービス開始について(2024/12/10更新)
厚生労働省は、2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに 「離職票」を直接送付するサービスを開始します。
本件に関するリーフレットを作成し、公開しております。
現在は事業所から離職者に送付されている離職票が、2025年1月20日から、希望する離職者には、マイナポータルを通じて直接送付されるサービスが開始されます。
離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票も、マイナ ポータルを通じて送付されます。
◆本サービスの対象となる条件
・届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
・離職者ご自身にマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていただくこと
・事業主より電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていただくこと
※マイナンバー登録には時間がかかる場合がありますので、資格喪失届提出の2週間程度前までに行ってください。
※被保険者が希望しない場合や要件を満たさない場合は、従来どおり事業所へ離職票等の書類をお送りしますので、離職者に送付ください。
リーフレットには、事業主に行っていただく、STEP1、STEP2の作業が記載されております。
STEP1 マイナンバーを被保険者番号に登録する
STEP2 電子申請で雇用保険の離職手続きを行う
また、被保険者向けリーフレットのQRコードも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344616.pdf
高額療養費の在り方について(案)(2024/12/6更新)
厚生労働省は、第188回社会保障審議会医療保険部会の資料を公開しております。
資料の中から、高額療養費の在り方について(案)をご紹介します。(下線は筆者加筆)
高額療養費については、以下の視点を勘案しつつ、必要な見直しを検討していくべきではないか。
【社会経済情勢の変化】
・高齢化の進展、医療の高度化等により高額療養費の総額が年々増加(総医療費の6~7%相当)する中で、近年、高額療養費の自己負担限度額の上限は実質的に維持されてきた。このような要因もあり、医療保険制度における実効給付率は上昇。
・前回実質的な見直しを行った約10年前(平成27年)と比較すると、賃上げの実現等を通じた世帯主収入や世帯収入の増加など、経済環境も大きく変化している。また、足下では、生活必需品をはじめとした継続的な物価上昇が続く中で、 現役世代を中心に保険料負担の軽減を求める 声も多くある。
【検討の方向性(案)】
・セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持しつつ、 健康な方を含めた全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る観点から、
①高額療養費の自己負担限度額の見直し(一定程度の引き上げ)
②所得区分に応じたきめ細かい制度設計とする観点からの所得区分の細分化
などが考えられないか。
・能力に応じて全世代が支え合う全世代型社会保障を構築する観点から負担能力に応じた負担 を求める仕組みとすべきではなか
・施行時期については、国民への周知、保険者・自治体の準備期間(システム改修等)などを考慮しつつ、被保険者の保険料負担の軽減というメリットをできる限り早期に享受できるようにする観点から検討すべきではないか。
また、資料には、機械的なモデル試算の結果も掲載されております。
※住民税非課税区分を除く各所得区分の細分化を行った上で、自己負担限度額を機械的に一律の率で引き上げた場合の保険料等への影響について分析を行っています。(一律の率は+5%、+7.5%、+10%、+12.5%、+15%の5パターンで試算)
(出典:第188回社会保障審議会医療保険部会 資料1)
詳細は、以下よりご確認ください。
標準報酬月額の上限見直し(案)について(2024/11/27更新)
厚生労働省は、第21回社会保障審議会年金部会の資料を公開しております。
資料の中から、「標準報酬月額の上限について」から、一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
まず、厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額の等級については以下の通りとなっています。
(厚生年金保険法)
標準報酬月額は全部で32等級あり、下限は8.8万円、上限は65万円(第32級は、令和2年9月1日に追加)
(健康保険法・船員保険法)
標準報酬月額は全部で50等級あり、下限は5.8万円、上限は139万円(第48~50級は、平成28年4月1日に追加)
〇標準報酬月額の上限設定の基準の経緯
・制度発足当初、上限改定に関する明確な基準は設けていなかったが、昭和44年改正以降、被保険者の約95%が上下限を除いた標準報酬月額に該当するよう改定することとした。
・昭和60年改正において、給付額の差があまり大きくならないようにする観点から、男子被保険者の平均標準報酬月額の概ね2倍となるように設定することとし、平成元年改正以後は、女子も含めた被保険者全体の平均標準報酬月額の概ね2倍となるように設定。
・平成16年改正においては、保険料率の引上げスケジュールがすべて法定化されたことに伴い、標準報酬月額の上限の考え方を法律に規定し、政令で上限を追加することを可能とした。
具体的には、各年度末時点において、全被保険者の平均標準報酬月額の2倍に相当する額が標準報酬月額の上限を上回り、その状態が継続すると認められる場合には、政令で、上限の上に等級を追加することができることとした。
〇標準報酬月額別の被保険者数分布割合(男女計)
・厚生年金(第1号厚生年金被保険者のみ)において、標準報酬月額の上限の等級(65万円)に該当する者の割合は 6.5%となっており、健康保険と比較すると、多くの者が上限の等級に該当している(健康保険では1%未満)
・上限等級に該当する者の割合は女性よりも男性の方が高く、かつ、男性については上限等級に最頻値が見られる
〇見直しの意義及び方向性
・現行の等級の追加ルール(いわゆる「2倍ルール」)の法定化以降、令和2年9月の1等級の上限引上げを経ても上限等級に多くの者が該当している状態が継続している。上限該当者は、負担能力に対して相対的に軽い保険料負担となっている中、今後、賃上げが継続すると見込んだ場合に、負担能力に応じた負担を求めるとともに、将来の給付も増やすことが出来るようにする観点から、現行ルールの見直しを検討することとしてはどうか。
・具体的には、男女ともに上限等級に該当する者が最頻値とならないように上限等級を見直すとともに、健康保険法の改定ルールを参考に、上限等級に該当する者が占める割合に着目して等級を追加することができるルールへの見直しを検討することとしてはどうか。
・上限等級を追加した場合には、新たな上限等級に該当する者の報酬比例部分が増加するとともに、保険料収入が増加し、これが給付に反映されるまでの間の積立金の運用益が増加することにより、厚生年金受給者全体の将来の給付水準も上昇する(所得再分配機能の強化につながる。)など、高齢期の経済基盤の安定、所得保障・再分配機能の強化につながる。
〇標準報酬月額の上限見直し(案)
以下の案が提示されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
高額療養費の在り方について(案)について(2024/11/22更新)
厚生労働省は、第186回社会保障審議会医療保険部会の資料を公開しております。
【資料2】医療保険制度改革についての資料の中から、高額療養費の在り方について(案)をご紹介します。(下線は筆者加筆)
高額療養費制度は、医療機関の窓口において医療費の自己負担を支払った後、月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後的に保険者から償還払いされる制度です。
入院の場合、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる現物給付化の仕組みが導入されており、外来でも、同一医療機関で自己負担限度額を超える場合に現物給付化が導入されています。
現行の自己負担限度額については、以下をご確認ください。
(出典:第186回社会保障審議会医療保険部会 資料2)
高額療養費の在り方について(案)
【検討の方向性(案)】
・物価・賃金の上昇など経済環境が変化する中でも、高額療養費の自己負担限度額の上限が実質的に維持されてきたこと等を踏まえ、セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持しつつ、健康な方を含めた全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る観点から、
①高額療養費の自己負担限度額の見直し(一定程度の引き上げ)
②所得区分に応じたきめ細かい制度設計とする観点からの所得区分の細分化
などが考えられないか。
・その際、能力に応じて全世代が支え合う全世代型社会保障を構築する観点から負担能力に応じた負担を求める仕組みとすべきではないか
・施行時期については、国民への周知、保険者・自治体の準備期間(システム改修等)などを考慮しつつ、被保険者の保険料負担の軽減というメリットをできる限り早期に享受できるようにする観点から検討すべきではないか。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について②(20024/11/20更新))
厚生労働省は、第20回社会保障審議会年金部会の資料を公開しております。
昨日に続き、『被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について』より一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応
① 制度的対応の検討
いわゆる「106万円の壁」への対応策の考え方
・「106万円の壁」では保険料負担が増えるが厚生年金給付も増える。これは全ての厚生年金被保険者に共通であり、適用拡大に伴う短時間労働者のみ異なる取扱いとなるわけではない。
・他方で、給付のことは考えず、「壁」を境にした保険料負担による手取り収入の減少のみに着目すれば「壁」を感じる者が存在することから、これへの対応は「保険料負担による手取り収入の減少をどうするか」を出発点として考えることが基本となる。(※)なお、現在の適用要件の下においては、最低賃金の引上げ等により、適用時点で「106万円」を意識しない水準まで 収入が増加していればいわゆる「年収の壁」は解消される。
※「保険料負担による手取り収入が減少しない」 仕組みを検討する際には、稼得能力に応じた負担、社会保険料の労使折半負担、他の被保険者との公平性といった社会保険の原理原則に抵触しないかについて留意する必要がある。
また、社会保険の原理原則に関わる視点以外にも、将来の年金給付への影響や実務面への影響などを考慮し、簡素で分かりやすく中立的な制度設計となるよう留意する必要がある。
いわゆる「130万円」の壁への対応策の考え方
・「130万円の壁」では保険料負担が増えても基礎年金給付は同じであり、これは第1号被保険者と第3号被保険者とで負担と給付の構造が異なることによるもの。
・これへの対応は、第3号被保険者のあり方そのものに着目した何らかの見直しを行うか、「壁」を感じながら働く第3号被保険者が少なくなるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を一層加速化することが基本となる。
これまでの年金部会における主なご意見(いわゆる「年収の壁」)
【見直しに向けた具体的なご提案】
・週労働時間が20~30時間の短時間労働者(元3号)について、保険料は厚生年金の事業主負担のみで、給付は厚生年金の半分になる制度「厚生年金ハーフ」と、本人負担もある「厚生年金フル」とで短時間労働者が選択する形にすれば、就業調整の問題はほぼ解決すると考えられるが、今の手取りを高めるために厚生年金ハーフを選ぶことは老後の貧困リスクを高める選択であることを学んでもらうことも必要になる。
・抜本的な解決策としては、週20時間未満も含めた適用拡大が最適。具体的な手段としては、第1号被保険者を1.5号 (1号と2号の間)とし、報酬の18.3%の厚生年金保険料が国民年金保険料に満たない場合、被用者に差額の国民年金保険料の納付を求める。また、第3号被保険者は、20時間未満で働く場合は2.5号(2号と3号の間)とし、厚生年金保険料が国民年金保険料に満たなくても差額の納付を求めず、基礎年金拠出金は全て厚生年金財政が負担することとして はどうか。1.5号/2.5号の給付については、いずれも基礎・報酬比例ともに満額で、ハーフにはしない設計。
就業調整に対応した保険料負担割合を変更できる特例の検討の視点
◆検討の視点
被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生・手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、健康保険組合の特例を参考に、被用者保険(厚生年金・健康保険)において、従業員と事業主との合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を設けることをどのように考えるか。
◆特例を導入する場合の論点
・被用者保険では保険料は労使折半が原則であることや健康保険法では保険者単位で労使合意に基づき保険料負担割合を変更できることを踏まえ、今回検討する恒久的でない特例的な案の位置づけをどのように考えるか。
・一部の標準報酬月額の者に限って特例を認めることをどのように考えるのか。
・健康保険法同様、標準報酬月額及び標準賞与額を対象とするか。
・厚生年金保険法及び健康保険法に限った特例とすることを他の社会保険制度との関係においてどのように整理するか
③ 第3号被保険者制度に係る論点
年金部会の議論における第3号被保険者制度に係る指摘の整理
概ね意見が一致している事項
・まずは被用者保険の適用拡大を進めることにより、第3号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを踏んでいくこと
① 女性を取り巻く環境の変化を踏まえた第3号被保険者制度の在り方に対する指摘
・共働き世帯が多くなり、被扶養者への特別な措置である制度は社会の実態に合っておらず、社会保険制度内の不公平感の解消、社会の担い手の拡大という観点から見直すべき
・適用拡大を進めた上で残る第3号被保険者はどういった人なのか、第3号被保険者やその世帯の生活実態、単身女性に多いとされる高齢期の貧困状況など分析する必要
② 第3号被保険者制度が持つ機能に対する指摘
・見直しによって新たな負担を求める場合には、保険料の免除や未納により低年金を招く可能性があり、高齢期の貧困防止の観点から議論すべき
・公的年金制度が持つ所得保障としての機能を後退させてはならない
・第3号被保険者の配偶者が負担した保険料は共同で負担したものとの基本的認識で制度設計されており、制度の見直しは、年金分割の理念や、事業主や被保険者の負担の意味に影響する
③ 第3号被保険者制度の見直しを検討する上で配慮が必要な者についての指摘
・育児や介護、病気など、働くことが難しい者への対応をどう考えるか
・育児や介護などで労働時間の制約を受け、低収入となっている者に限定するか、あるいは女性の就業環境が整ってきた若い世代から見直してはどうか
・育児や介護といった配慮が必要な人を判定して見極めることは難しく、何らかの配慮が必要な者への対応は、基本的には年金制度外で支援していくべき。
・仮に育児等に着目した何らかの配慮をする場合、同様のニーズを抱える第1号被保険者とのバランスをどのように考えるか
・純粋な無業者に保険料納付を求めても無年金になる可能性があるため、第1号被保 険者と同様に免除してはどうか
④ 第3号被保険者を見直すとした場合の実務的な課題に対する指摘
・第3号被保険者に国民年金保険料を課す場合の政策的な実現可能性を考慮するべき
・配慮が必要な人に限定する場合、本当に支援が必要な人を実務的に捕捉することは困難
⑤ 第3号被保険者制度について検討する上での留意点
・被扶養配偶者の仕組みは健康保険と同様であり、制度を見直す場合は両者の整合性に配慮が必要
・制度の見直しが国民年金の財政に与える影響を見極めることが必要
第3号被保険者制度に係る現状と検討にあたっての論点
◆第3号被保険者制度に係る現状
・短時間労働者への適用拡大が実現して以降、第3号被保険者はすう勢的に減少傾向にはあるが、約675万人の第3号被保険者が存在している。年金部会においては、まずは適用拡大を進めて、第3号被保険者制度を縮小していくことついては、概ね一致した意見となっている。
・こうしたことも踏まえて、更なる被用者保険の適用拡大を進めることを検討するとともに、第3号被保険者制度の縮小につながる取組として、いわゆる「年収の壁」への対応についても検討をしている。
・一方で、現時点においては、「社会保障審議会年金部会における議論の整理」で指摘されている第3号被保険者の実態として、「短時間労働に従事している者、出産や育児のために離職した者、配偶者が高 所得で自ら働く必要性が高くない者などが混在している状況にある」ことは続いていると考えられる。
◆第3号被保険者制度の検討にあたっての論点
今回の更なる被用者保険の適用拡大や「年収の壁」への対応により、第3号被保険者制度が更に縮小の方向に向かっていくこととなるが、それでもなお残る第3号被保険者についての制度の在り方や今後のステップをどのように考えるか
詳細は、以下よりご確認ください。
被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について①(2024/11/19更新)
厚生労働省は、第20回社会保障審議会年金部会の資料を公開しております。
今回は、『被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について』より一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
1 被用者保険の適用拡大
② 短時間労働者及び個人事業所の適用拡大
短時間労働者及び個人事業所の被用者保険の適用範囲の見直しの方向性案
・労働時間要件
雇用保険の適用拡大に伴い本要件を引き下げるべきとの意見があった一方で、保険料や事務負担の増加という課題は対象者が広がることでより大きな影響を与え、また、雇用保険とは異なり、国民健康保険・国民年金というセーフティネットが存在する国民皆保険・皆年金の下では、事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用者保険の「被用者」の範囲をどのように線引きするべきか議論を深めることが肝要であり、こうした点に留意しつつ、雇用保険の適用拡大の施行状況等も慎重に見極めながら検討を行う必要がある等の意見があったことから、今回は本要件を見直さないこととしてはどうか。
・賃金要件
就業調整の基準として意識されていること、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす地域や事業所が増加していることを踏まえ、本要件についてどう考えるか。
・学生除外要件
就業年数の限られる学生を被用者保険の適用対象とする意義は大きくない、適用対象とする場合には実務が煩雑になる等の意見があったことから、今回は本要件を見直さないこととしてはどうか。
・企業規模要件
労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、撤廃 することとしてはどうか。併せて、事業所における事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必要な配慮措置や支援策を講じることとしてはどうか。
・個人事業所
常時5人以上の従業員を使用する個人事業所における非適用業種については、労働者の勤め先等に中立的な制度を構築する観点等から、解消することとしてはどうか。併せて、事業所における事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必要な配慮措置や支援策を講じることとしてはどうか。他方で、常時5人未満の従業員を使用する個人事業所については、本来的には適用すべきとの意見があった一方で、対象事業所が非常に多く、その把握が難しいと想定されること、国民健康保険制度への影響が特に大きいこと等から、慎重な検討が必要との意見もあったことから、今回は適用しないこととしてはどうか
③ 複数事業所勤務者に対する被用者保険の適用等
現行事務における課題と見直しの考え方
◆課題
(事業者)
①複数事業所勤務者については個別管理の必要
自社の他の被保険者と共通の人事給与システムでは複数事業所勤務者を管理できず、個別管理が必要。(選択届の提出により遡及して保険料の修正が発生することや、報酬月額を合算し選択保険者の保険料率で保険料額を算定する必要があること等が要因)
②他の事業所における変更等の影響
自社で報酬月額に変更がなくとも、もう一方の事業所において報酬月額に変更があった場合には自社の保険料にも影響が生じる。
③手続先保険者が増加
非選択事業所にとっては、通常はやりとりのない選択年金事務所・選択医療保険者とのやりとりが発生。
(日本年金機構・医療保険)
④事務負担の増加
・2以上該当者に係る各事業所の情報を管理・処理する必要があり、事務負担が大きい。
・選択年金事務所・選択医療保険者は、通常はやりとりのない事業所とのやりとりが発生。
◆見直しの考え方
事業所における事務負担を軽減する観点からの見直しの考え方は以下のとおり
・それぞれの事業所において保険料算定を可能とし、可能な限り事業者における複数事業所勤務者の個別管理をなくす。
・各事業所は管轄する年金事務所・医療保険者とのやりとりのみで処理を完結できるようにする。
(出典:第20回社会保障審議会年金部会資料1)
複数事業所での労働時間等の合算について
◆現行制度
事業所単位で適用要件を満たすか判断するため、複数の事業所で勤務する者については、労働時間等を合算することなく、それぞれの事業所における勤務状況に応じて適用を判断している。
◆見直しの方向性
複数の事業所で勤務する者の労働時間等を合算することについては、実務における実行可能性等を見極めつつ、慎重に検討する必要があるとの意見を踏まえ、引き続き検討していくこととしてはどうか。
フリーランス等について
◆現行制度
業務委託契約でありながら、実態としては被用者と同様の働き方をしている者については、被用者保険の適用を確実なものとしていくため、労働基準監督署において労働者であると判断した事案について、日本年金機構が情報提供を受け、その情報を基に適用要件に該当するか調査を行っている。
◆見直しの方向性
労働基準法上の労働者に該当しない働き方をしているフリーランス等への適用の在り方については、まずは労働法制における議論を注視する必要があること、被用者保険が事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みであること等の意見を踏まえ、諸外国の動向等を注視しつつ、中長期的な課題として引き続き検討していくこととしてはどうか。
次回は、『第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応』をご紹介します。
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年4月1日からの「高年齢雇用継続給付」支給率変更に関するリーフレットのご紹介(2024/11/10更新)
高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。
【変更内容】
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
本件に関するリーフレットが公開されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」(日本年金機構)(2024/10/19更新)
日本年金機構は、「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」との案内をホームページに掲載しております。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄を新たに設けますので、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、届書の「□発行が必要」にチェックを入れてください。届出内容に基づき、協会けんぽから資格確認書が発行されます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大Q&A集(その3)を公表(2024/9/16更新)
厚生労働省は、令和6年9月5日付で健康保険組合宛に、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)」を事務連絡として出しました。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、令和4年9月28日付け事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」で示されておりますが、これを別添のとおり改正したものです。
2024年10月から、パートアルバイトの加入条件が、従業員数が51人以上の企業に拡大されます。
該当の事業所のご担当者様は、一度、Q&Aを確認されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240914S0010.pdf
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(パブコメ)(2024/9/7更新)
厚生労働省は、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集を行っております。
◆改正の概要(資料より一部抜粋、下線は筆者加筆)
(規則関係)
○改正法第13条の規定の施行に伴い、出生後休業支援給付金の創設等の改正が行われることに対応するため、以下に掲げる規定の整備等を行う。
・出生後休業支援給付金は、被保険者が育児休業給付金又は出生時育児休業給付金が 支給される休業(以下「給付対象出生後休業」という。)を対象期間内に通算して14 日以上取得した場合であって、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子につ いて給付対象出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8 週間を経過する日の翌日までの期間内に通算して14 日以上の給付対象出生後休業を したときに限る。)又は被保険者の配偶者が給付対象出生後休業をすることを要件と しない場合に該当するときに支給するものとすること。
・出生後休業支援給付金の支給に当たり、被保険者がその配偶者の給付対象出生後休 業の取得を要件としない場合のうち、配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者 である場合は、当該給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該 当しない者である場合等とし、その配偶者が期間内に休業をすることができない場合 として厚生労働省令で定める場合は、配偶者が日々雇用される者である場合等とする こと。
・同一の子について出生後休業を分割して取得し、出生後休業支援給付金の支給を受 けることができる場合は、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給の対象と なる休業を分割して取得した場合とする。
・出生後休業給付金の支給申請手続は、原則、育児休業給付金又は出生時育児休業給 付金の支給申請手続と併せて行わなければならない等とすること。
○改正法第13条の規定の施行に伴い、育児時短就業給付金の創設等の改正が行われることに対応するため、以下に掲げる規定の整備等を行う。
・事業主は、その雇用する被保険者が育児時短就業を開始した場合に、当該被保険者 が育児時短就業給付金の支給申請書を提出する日までに、育児時短就業開始時の賃金 に係る証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないこと。
・育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は育児時短就業をすることとする 一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにしてする育児時短就業の申 出に基づき、事業主が講じた1週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした 場合に支給するものとすること。ただし、当該末日とされた日(⑴及び⑵に該当する 場合にあっては、その前日)までに、⑴から⑷までに掲げる事由に該当することとな った場合には、当該事由に該当することとなった日(⑶及び⑷に該当する場合にあっ ては、その前日)後は、支給しない。
⑴ 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
⑵ 育児時短就業の申出に係る子が2歳に達したこと。
⑶ 育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は 雇用保険法第61条の7第1項の休業をする期間が始まったこと。
⑷ 育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まったこと。
・育児時短就業給付金の支給限度額の算定方法について、賃金構造基本統計の常用労 働者のうち65歳未満の者が受けている一月当たりのきまって支給する現金給与額をその高低に従い4の階層に区分したものを基礎とすること。
・育児時短就業給付金の額の算定に当たって、支給対象月に支払われた賃金の額が、 育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の90に相当する額以上100 分の100に相当する額未満である場合に、100分の10から一定の割合で逓減するように定める率は、⑴に掲げる額から⑵及び⑶に掲げる額の合計額を減じた額を⑵に掲げる額で除して得た率とすること。
⑴ 育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額
⑵ 支給対象月に支払われた賃金額
⑶ ⑴に掲げる額に100分の1を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ ⑴に掲げる額から⑵に掲げる額を減じた額
ロ ⑴に掲げる額に100分の10を乗じて得た額
・育児時短就業給付金の支給申請手続は、初めて支給を受けようとするときは、支給 対象月の初日から起算して4箇月以内に行わなければならない等とすること。
○育児休業給付金の対象となる育児休業の分割取得回数の制限の例外に、出向日の前日に育児休業をしている場合であって、出向日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。)を追加すること。
○出生時育児休業の支給申請手続について、「子の出生日から8週間を経過する日の翌日から」に加え、「同一の子について2回の出生時育児休業を取得した場合は当該休業を終了した日の翌日から」及び「出生時育児休業を取得した日数が通算して28日に達した場合はその翌日から」も行うことができるものとすること。
◆施行期日等
公 布 日:令和6年10月下旬(予定)
施行期日:令和7年4月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請義務化に関するリーフレットについて(2024/7/23更新)
2025年1月1日より、労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます。
厚生労働省は、本件に関するリーフレットを作成し公表しております。
電子申請が義務化される手続きは、以下の通りです。
・労働者死傷病報告
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
リーフレットは、以下よりご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001887029.pdf
人事・労務管理者担当者向け、従業員向けサイトのご紹介(社会保険適用拡大特設サイト)(2024/7/19更新)
厚生労働省の適用拡大 特設サイトでは、社会保険適用拡大の対象となる企業等の「人事・労務管理者のみなさま」や社会保険加入のメリットや手取りや年金額の変化を知りたい「従業員のみなさま」向けのサイトを公開しております。
◆人事・労務管理者のみなさま向けページ
このページでは、人事・労務管理を担当する方が、社会保険適用拡大に向けた準備を社内で円滑に進めるために、社内(経営層、現場責任者、従業員)への説明手順や各種チラシの説明方法などのコツを好事例とともに説明しています。
〇従業員説明に向けた準備
・対象となる事業所・従業員について
・社内周知までの流れについて
・経営陣や幹部への説明のポイント
・現場責任者への説明のポイント
〇従業員説明の実施
・従業員への説明のポイント
〇社会保険適用拡大 解説動画・手引き・パンフレット一覧
◆従業員の皆様向けページ
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入した場合、保険料の支払いが生じるものの、医療や年金の保障が充実することから、対象者の範囲が拡大されています。このページでは社会保険の加入条件や、加入することで充実する医療・年金の保障、手取り額の変化について記載されております。
・社会保険加入の対象者
・社会保険加入のメリット
・社会保険加入後の手取り額シミュレーション
・社会保険加入による年金額シミュレーション
・よくある質問
・従業員様向けチラシ
詳細は、以下よりご確認ください。
令和6年10月 被用者保険の適用拡大に関する説明資料を更新(厚労省)(2024/7/16更新)
厚生労働省は、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の円滑な施行に向けて、「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業」を実施しています。
今般、事業主等に向けた被用者保険の適用拡大に関する説明資料について、更新版を取りまとめ公表しております。
内容については、
1.制度編
2.実践編
と大きく2つの項目で構成されております。
1.制度編では、
・被用者保険適用拡大の意義
・適用拡大のメリット
などが記載されています。
2.実践編では、
・適用拡大のスケジュール
・適用拡大の要件(企業規模、労働時間、賃金、学生)
・専門家支援事業の活用
・広報コンテンツ(人事・労務管理者向け手引き、従業員向けチラシ、公的年金シミュレーター)の紹介
などが記載されております。
今回の適用拡大の対象企業の方で、今後、従業員向けの説明会などを予定されている場合、社員向け説明資料作成の参考となると思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240703T0010.pdf
令和7年4月からの育児休業給付金の支給対象期間延長手続きに関するリーフレットのご紹介(2024/7/8更新)
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更となります。厚生労働省は、本件に関するリーフレットを公開しております。
〇改正のポイント
これまで:保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。
2025年4月から:これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
その他、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の入力用と手書用の様式も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください、
「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル(2024/4/25更新)
厚生労働省は、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツを公開しました。
今回追加された新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容です。
〇主な新コンテンツ
① 人事・労務管理者向け「社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?手引き」
② 従業員向けチラシ「社会保険加入のメリット」
「社会保険加入を考える3ステップ」
「社会保険加入に関するQA集」
③ 社会保険適用拡大に関する解説動画(ショート動画、5分動画)
詳細は、以下よりご確認ください。
雇用保険法等の一部を改正する法律案について(2024/2/15更新)
雇用保険法等の一部を改正する法律案が令和6年2月9日に国会に提出されました。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要に関する資料が掲載されておりますので、一部抜粋してご紹介します。
◆改正の概要
1 .雇用保険の適用拡大(令和10年10月1日施行)
・雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。
2 .教育訓練やリ・スキリング支援の充実(①は、令和7年4月1日、②は令和6年10月1日、③は令和7年10月1日施行)
① 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする
※自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
② 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる。
※教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。
③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当 に相当する新たな給付金を創設する。
3 .育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
① 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止する。 ※本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。(公布日施行)
② 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする。
※①・②により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。(令和7年4月1日施行)
4 .その他雇用保険制度の見直し(令和7年4月1日施行、一部は公布日施行)
・教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
詳細は、以下よりご確認ください。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)(2024/1/30更新)
厚生労働省から、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集」が令和6年1月17日付の事務連絡で出されております。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いにあたっては、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」(令和4年9月28日付け事務連絡)等が出されておりますが、今回、令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて別添のとおり取りまとめられました。
Q&Aには、以下のような内容が掲載されております。
1. 被保険者資格の取得要件(総論)
問1~問6
2. 特定適用事業所
問7~問20
3. 任意特定適用事業所
問21~問29
4. 1週間の所定労働時間が20時間以上
問30~問34
5. 学生でないこと
問35~問36
6. 所定内賃金が月額 8.8 万円以上
問37~問46
7. 給付・その他
問47~問51
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf
「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」(2024/01/13更新)
厚生労働省は、「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正についてという通達を令和5年12月22日付で発出しております。(基監発 1222 第1号)
本件については、平成22年4月12日付け基監発 0412 第1号「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」という通達がございました。
今回、賃金台帳等使用者による支払賃金額の記録が確認できない事案において、当該労働者の厚生年金保険の標準報酬月額が明らかであったため、これを用いて平均賃金を算定したところ、当該労働者の健康保険の標準報酬月額もまた明らかであり、これが離職時の賃金額に近似していると考えられる場合には、健康保険の標準報酬月額を用いて平均賃金の算定を行うべきであるから、当該処分は取り消すべきとして行政不服審査会からの答申を受け、取り消しの裁決を行った事案が発生したことを踏まえ、改正されることとなりました。
改正後の通達の内容を一部抜粋してご紹介します。(正直に申し上げますが、私はこの通達の存在を今回、始めて知りました。)
1 標準報酬月額について
平均賃金の算定の対象となる労働者等(以下「算定対象労働者等」という。)が、 賃金額を証明する資料として、任意に、厚生年金保険又は健康保険の標準報酬月額が明らかになる資料を提出しており、当該資料から、労働者が業務上疾病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職した日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間(以下「離職した日以前3か月間」と いう。)の標準報酬月額が明らかである場合は、当該標準報酬月額を基礎として、 平均賃金を算定して差し支えないこと。
なお、関係資料から労働者の標準報酬月額等が明らかな場合であっても、当該資料から、労働者の支払賃金額もまた明らかとなる場合には、支払賃金額を基礎として平均賃金を算定すべきであることに留意すること。
2 賃金日額等について
省略
3 賞与等について
1 の場合において確認された標準報酬月額に、通貨以外のもので支払われた賃金であって平均賃金の算定の基礎とされないものが含まれている場合又は、2の場合において確認された賃金日額若しくは賃金額(以下「賃金日額等」という。)に、臨時に支払われた賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金若しくは通貨以外のもので支払われた賃金であって平均賃金の算定の基礎とされないものが含まれている場合には、1及び2にかかわらず、当該標準報酬月額又は賃金日額等を平均賃金の算定の基礎とすべきでないこと。
ただし、臨時に支払われた賃金若しくは3か月を超える期間ごとに支払われる賃金の額又は通貨以外のもので支払われた賃金であって平均賃金の算定の基礎とされないものの評価額が明らかである場合には、これらの額を当該標準報酬月額又は 賃金日額等から差し引いた額を基礎として、平均賃金を算定して差し支えないこと。 なお、標準報酬月額及び賃金日額に反映される賃金の範囲については、別紙を参照のこと。
(出典:厚生労働省「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正について)
4 賃金台帳等の一部が存在している場合について
離職した日以前3か月間の一部についてのみ賃金台帳等使用者による支払賃金額の記録が存在している場合で、同時に、算定対象労働者等が賃金額を証明する資料として、上記に該当する資料を任意に提出したことにより、当該労働者の標準報酬月額又は賃金日額が明らかである場合には、賃金額が賃金台帳等によっては確認できない期間について、当該標準報酬月額又は賃金日額を基礎として賃金額を算定した上で、平均賃金を算定して差し支えないこと。
詳細は、以下よりご確認ください。
・「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正について(令和5年12月22日基監発1222第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0010.pdf
・新旧対照表
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0011.pdf
・別添
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0012.pdf
・改正後全文
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0013.pdf
「社会保険適用促進手当」のQ&Aを更新(2024/1/5更新)
日本年金機構は、事業主の皆さま宛に「年収の壁・支援強化パッケージ」における「社会保険適用促進手当」および「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&A改正に関するご案内を掲載しております。
本日は、「社会保険適用促進手当」のQ&Aについて、主な改正点をご紹介します。(下線は筆者加筆)
Q2-6
以前からの勤め先ですでに社会保険に加入していますが、別の事業所でも加入要件を満たしたため社会保険に加入します。新たに社会保険に加入する事業所で社会保険促進手当の支払いを受けますが、今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)の対象となるのでしょうか。
A2-6
複数の事業所に勤務し、各事業所において社会保険の加入要件を満たしている被保険者については、事業所ごとで今回の措置の対象となるのか確認します。
そのため、新たに社会保険に加入する事業所で、当該事業所の報酬のみで標準報酬月額を算出したならば、その額が 10.4 万円以下である場合には、今回の措置の対象となります。
Q2-7
社会保険適用促進手当は、各労働者について最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定において考慮しないとのことですが、同手当の対象となっていた労働者が退職し、一定期間経過後に同一事業所で再度雇用された場合、標準報酬等の算定に考慮しない期間はどのように取扱われますか。
A2-7
同一事業所で一定期間経過後に再度雇用された場合は、それぞれの被保険者期間で2年が経過するまで算定に考慮しない措置の対象となります。
なお、同日得喪で被保険者資格が継続している場合は、通算して2年が経過するまで算定に考慮しない措置の対象となります。
Q2-8
厚生年金又は健康保険のいずれか片方のみに加入している場合であっても、今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)の対象となるのでしょうか。
A2-8
70歳以上で健康保険のみに加入している場合等、厚生年金又は健康保険のいずれか一方の制度のみに加入している場合も今回の措置の対象となります。
なお、この場合は標準報酬月額等の算定の対象から除くことができるのは、加入している制度に係る被保険者本人負担分が上限となります。
Q3- 6
社会保険適用促進手当について、労働者が標準報酬月額・標準賞与額の算定から除くことを希望しない場合は、手当を含めて標準報酬月額・標準賞与額を算定してよいでしょうか。
A3- 6
今回の社会保険適用促進手当の特例(社会保険料の算定に当たって標準報酬月額等に含めない取扱い)は、労使双方の合意を前提に活用いただくものとなりますが、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給する手当であっても、労働者の希望を確認した上で標準報酬月額等の算定の対象から除かない場合は、「社会保険適用促進手当」以外の名称を使し、支給いただくようお願いします。
Q3- 12
社会保険適用促進手当は、傷病手当金や出産手当金との調整の対象となる報酬に含まれますか。
A3- 12
社会保険適用促進手当については、傷病手当金等の支給額算出の基礎となる標準報酬月額の算定に考慮しないことから、傷病手当金等との調整対象となる報酬には含まれません。
Q3-13
在職老齢年金制度によって 、厚生年金保険の適用事業所で就労し、一定以上の賃金(標準報酬月額・賞与)を得ている60歳以上の老齢厚生年金受給者は、賃金(標準報酬月額・標準賞与額)に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されますが、 支給停止額の算定に当たって 社会保険適用促進手当は考慮されるのでしょうか。
A3- 13
社会保険適用促進手当は、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことから、在職老齢年金制度による支給停止額の算定においても考慮されません。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202312/1227.files/teate.pdf
「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&Aについて、主な改正点のご紹介(2024/1/4更新)
日本年金機構は、事業主の皆さま宛に「年収の壁・支援強化パッケージ」における「社会保険適用促進手当」および「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&A改正に関するご案内を掲載しております。
本日は、「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&Aについて、主な改正点をご紹介します。(下線は筆者加筆)
Q1-9 健康保険組合等の保険者における被扶養者の収入確認期間が令和5年10月20日を またいでいる場合、既に確認した被扶養者について、事業主の証明を求めて、再度収入確認をやり直す必要があるのでしょうか。
A1-9 健康保険組合等の保険者において被扶養者の収入確認期間が、措置の詳細をお示しした令和5年10月20日をまたいでいる場合、当該期間に係る一連の収入確認について、従前どおりの取扱いとして差し支えありません(今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)を適用する必要はありません)。
Q2-6 今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)については、あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とすることとされていますが、被保険者の転職等に伴い保険者が変更となった場合はどのように考えれば良いでしょうか。
A2-6 被保険者の転職等に伴い保険者が変更となった場合、事業主の証明を用いて一時的な収入変動である旨を保険者が確認した回数の引継ぎはせず、新たに加入した保険者で行った収入確認を1回目としてカウントすることとなります。
Q3-8 今回の措置における事業主証明は、令和5年10月20日以降の収入についてだけ使 えるということでしょうか。
A3-8 被扶養者の収入については、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととしており、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を用いて、確認時点からの今後1年間の収入見込みが130万円以上となるかどうかを判断することとなります。
今回の措置は、措置の詳細をお示しした令和5年10月20日以降の、新たな被扶養者の認定及び既存の被扶養者の収入確認において適用されますが、証明の対象は令和5年10月20日以降の収入に限られるものではなく、過去の収入についても、今回の事業主の証明の対象となります。
Q3-9 事業主の証明は、人事担当者など事業主以外であっても記載可能でしょうか。
A3-9 事業主の証明については、事業主の氏名等を記載いただくこととなっていますが、複数の店舗がある企業で店舗ごとに人事管理を行っている場合等、企業の組織形態によっては事業主に記載いただくことが困難であることも考えられます。
そのような場合には、人事労務管理を担当している部署の責任者など、被扶養者の方の就労状況、労働条件等についてよく把握している方の氏名等を記載ください。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202312/1227.files/fuyo.pdf
「年収(130万円)の壁」への対応について(協会けんぽ)(2023/11/14更新)
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、「年収(130万円)の壁」への対応について、以下の案内を掲載しております。
(1)令和5年度被扶養者資格再確認でご提出いただくもの等について
被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せてご提出ください。
なお、収入を確認する書類(所得証明書等)は、ご提出いただく必要はございません。
(2)協会けんぽからの照会について
被扶養者状況リスト等をご提出いただいた際に、「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付があり、扶養解除の理由が「3.就職・収入増加」(配偶者である被扶養者の場合)もしくは、「3.収入増加」(配偶者以外の被扶養者の場合)を選択されている場合は、協会けんぽより、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないか文書照会をさせていただくことがあります。
文書が到着した際は内容をご確認いただき、扶養解除を予定している被扶養者の収入増加の理由が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明をご加入の都道府県支部までご提出いただきますようお願いいたします。
なお、収入増加の理由が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でない場合は、事業主の証明をご提出いただく必要はございません。
詳細は、以下よりご確認ください。
雇用保険手続における押印廃止に関するリーフレットのご紹介(2023/11/5更新)
令和2年12月25日付けの法令改正等に伴い、事業主及び申請者の押印は、主な雇用保険関係の申請・届出において廃止となりましたが、一部の申請・届出では押印欄が存続していました。
今般、令和5年10月1日付けの法令改正等に伴い、押印不要となる手続きの範囲をさらに広げ、「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除き廃止となりました。
東京労働局では、本件に関するリーフレットを掲載しております。
◆令和5年10月1日付けで新たに押印が不要となった届出
※括弧内は必要としていた押印種別
〇事業所・被保険者関係
・雇用保険適用事業所設置届 [事業主印]
・雇用保険事業主事業所各種変更届 [事業主印]
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届[選任代理人が使用する印] ・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書 [申請者印]
・雇用保険適用事業所情報提供請求書 [事業主印]
〇雇用継続給付関係
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書[事業主印]
・雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書 [事業主印]
〇就職促進給付関係
・再就職手当支給申請書 [事業主印]
・就業促進定着手当支給申請書 [事業主印]
・常用就職支度手当支給申請書 [事業主印]
〇その他
・各種届出における訂正印
・各届出時の委任状 [委任者印]
・採用証明書 [事業主印]
◆引き続き押印が必要となる手続き
〇日雇労働関係
・「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続き [事業主印、被保険者印]
ただし、個人情報保護の観点等からの注意点も記載されておりますので、詳細は、以下のリーフレットをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001616075.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001617498.pdf
「配偶者手当見直し検討のフローチャート」のご紹介(2023/10/25更新)
厚生労働省は、「年収の壁」対策として、「配偶者手当見直し検討のフローチャート」を公表しております。
https://www.mhlw.go.jp/content/001158767.pdf
夫の会社の配偶者手当をもらうため、他社で働いている妻が、手当受取りの収入基準を超えないように働き控えをする場合もあることから、社会保障制度だけではなく、企業の配偶者手当が「年収の壁」として、就業調整の一因となる場合があると考えられています。
配偶者手当を見直すことは、自社の人材確保にも役立つことから、配偶者手当の見直しを行う場合の以下の4ステップのフローチャートを作成し公開しています。
Step1 賃金制度・人事制度の見直し検討に着手
Step2 従業員のニーズを踏まえた案の策定
Step3 見直し案の決定
Step4 決定後の新制度の丁寧な説明
また、手当見直し内容について、以下のような具体例も記載されております。
・配偶者手当の廃止(縮小)+ 基本給の増額
・配偶者手当の廃止(縮小)+ 子ども手当の増額
・配偶者手当の廃止(縮小)+ 資格手当の創設
・配偶者手当の収入制限の撤廃
家族手当は、労働の量や質とは関係のない部分で支給の有無が決まるため、不公平感を抱かせる一面もあり、また、女性の社会進出によって夫婦共働き世帯が増えていることから、家族手当そのものの意義も薄れており、見直しや廃止を進める企業も増えています。
ただし、見直しをする際は、労働条件の不利益変更となる場合もございますので、労使での丁寧な話合いが重要となります。見直しを検討されている企業の方は、本リーフレットや厚生労働省のウエブサイト「企業の配偶者手当の在り方の検討」も参考になると思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
社会保険適用促進手当に関するQ&Aのご紹介(2023/10/24更新)
「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り扱いが示されました。
健康保険、厚生年金関係では、![]()
・社会保険適用促進手当に関するQ&A
・![]() 事業主の証明による被扶養者認定のQ&A
事業主の証明による被扶養者認定のQ&A
が公表されております。
今回は、社会保険適用促進手当に関するQ&Aから一部抜粋してご紹介します。
(下線は、筆者加筆)
Q2-1
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)は、どのような方が対象 となるのでしょうか。
A2-1
今回の措置は、新たに社会保険の適用となった労働者であって、標準報酬月額が 10.4万円以下の者が対象となります。支給対象者は特定適用事業所に勤務する短時間労働者に限られません。
また、事業所内での労働者間の公平性を考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く、既に社会保険が適用されている他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、同様に、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない措置の対象となります。
Q2-3
同一事業所内の同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を事業主が特例的に支給する場合に、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないとのことですが、「同じ条件」「同水準」とは具体的にどのような場合を指すのでしょうか。
A2-3
事業所内で既に社会保険が適用されている労働者については、当該労働者の標準報酬月額が10.4万円以下であれば、事業主が保険料負担を軽減するために支給した手当について、本人負担分の保険料相当額を上限として標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない措置の対象となります。
Q2-5
従業員100人以下の事業所ですが、今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬 算定除外)の対象となりますか。
A2-5
事業所が特定適用事業所かどうかにかかわらず、社会保険(被用者保険)に新たに適用される労働者について、今回の措置の対象となる可能性があります。
また、事業所内で既に社会保険が適用されている労働者がいる場合には、当該労働者の標準報酬月額が10.4万円以下であれば、保険料負担を軽減するために支給した手当について、本人負担分の保険料相当額を上限として標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととすることが可能です。
Q3-2
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)について、標準報酬等の 算定から除外できる上限額はありますか。
A3-2
社会保険の適用に伴い発生する本人負担分の社会保険料負担、すなわち健康保険・厚生年金保険・ 介護保険に係る本人負担分の保険料相当額が、標準報酬等の算定から除外できる上限額となります。
Q3-3
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)について、標準報酬等の 算定から除外できる期間の上限はありますか。
A3-3
社会保険適用促進手当については、今回の措置を継続的な賃金の増額につなげていただくという観点から、それぞれの労働者について、最大2年間、標準報酬月額・ 標準賞与額の算定において考慮しないこととします。
各労働者について、2年が経過した後は、通常の手当と同様に標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めて保険料が計算されます。
なお、2年間の判断に当たっては、社会保険適用促進手当においてどの月の保険料負担を軽減したか(対象としたか)が基準となり、社会保険適用促進手当による保険料負担軽減の最初の対象月から2年間が期間の上限となります。
Q3-4
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)について、標準報酬月額 が10.4万円以下の者が対象とのことですが、具体的には、いつ発生した保険料相当額について、いつの標準報酬月額等の算定から除外することができるのでしょうか。
A3-4
社会保険適用促進手当を支給する労働者の標準報酬月額が10.4万円以下であった月に発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、令和5年10月以降の手当を実際に支給する月の標準報酬月額等の算定から除外することができます。
Q3-5
本人負担分の保険料相当額を超えて手当を支払った場合でも、全額を「社会保険適 用促進手当」として支払って良いでしょうか。
A3-5
基本的には、標準報酬等の算定から除外する部分については「社会保険適用促進手当」という名称としていただき、これを超える部分については別の名称の手当として支給いただく取扱いを想定しています。
なお、本人負担分の保険料相当額を超える分については、今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)の対象外となるため、標準報酬月額等の算定に含まれることとなり、随時改定の契機にもなり得ます。
Q3-7
社会保険適用促進手当を支給する場合、この手当について、就業規則(又は賃金規 程)を変更した上で、労働基準監督署への届出が必要になりますか。
A3-7
常時10人以上の労働者を使用する事業場において社会保険適用促進手当の支給を行う場合は、就業規則(又は賃金規程)への規定が必要になりますので、就業規則(又は賃金規程)を変更し、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数を代表する者)の意見書を添付して、所轄の労働基準監督署へ届け出てください。
Q3-8
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)は、各労働者について2 年限りの措置とのことですが、期間の終了に伴い手当の支給自体を取りやめる場合、終了時に不利益変更の問題は生じないでしょうか。
A3-8
就業規則(又は賃金規程)において、予め、一定期間に限り支給する旨を規定いただくことで、その旨含めて労働契約の内容としておくことが対応として考えられます。
Q3-11
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)を受けていましたが、月 額変更により標準報酬月額が10.4万円超となりました。社会保険適用促進手当はいつから標準報酬月額に算入する必要があるのでしょうか。
A3-11
標準報酬月額が10.4万円超である場合、社会保険適用促進手当は標準報酬月額に算入する必要があるため、標準報酬月額10.4万円超となった月から社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めることとなります。社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めることは固定的賃金の変動にあたるため、月額変更の要件を満たす場合には、社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めた月から4か月目に標準報酬月額を改定します。
Q4-1
適用事業所における短時間労働者の社会保険の適用要件である「所定内賃金が月額 8.8 万円」の判定において、社会保険適用促進手当は含まれるのでしょうか。
A4-1
適用事業所における短時間労働者の社会保険の適用要件である月額賃金 8.8万円の判定に当たっては、今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)の目的があくまでも、労働者の社会保険料負担を軽減することで社会保険の適用を促進することであることに鑑み、社会保険適用促進手当を含めて判断することとなります。
Q4-2
社会保険適用促進手当は、標準報酬月額・標準賞与額の算定において考慮しないと いうことですが、将来の厚生年金保険の給付額に影響はないのでしょうか。
A4-2
今回の社会保険適用促進手当については、社会保険の適用に伴い新たに発生した本人負担分の社会保険料相当額を上限として、標準報酬月額・標準賞与額の算定において考慮しないこととしていますが、この社会保険適用促進手当が保険料の賦課対象となる標準報酬月額等に含まれない以上、厚生年金保険の給付額の算出基礎にも含まれないこととなります。
Q4-4
今回の特例(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)は、所得税や住民税、労 働保険料についても対象となりますか。
A4-4
今回の社会保険適用促進手当の特例(社会保険料の算定に当たって標準報酬月額等に含めない取扱い)は、社会保険料負担の発生等による手取り収入の減少を理由として就業調整を行う者が一定程度存在するという、いわゆる「106万円の壁」の問題に対応するものであるため、厚生年金保険、健康保険の標準報酬月額等の算定のみに係る取扱いとなり、税等の他制度に関しては通常の取扱いとなります。
Q4-5
社会保険適用促進手当は、割増賃金や平均賃金、最低賃金の算定基礎に算入されますか。
A4-5
【割増賃金】(労働基準法第 37 条)
社会保険適用促進手当は①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当に該当しないと考えられるため、同手当が毎月支払われる場合には、割増賃金の算定基礎に算入されます。
他方、社会保険適用促進手当が毎月支払われず、
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
のいずれかに該当する場合には、割増賃金の算定基礎に算入されません。
【平均賃金】(労働基準法第 12 条)
平均賃金の基礎となる賃金には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しないこととされています。
このため、社会保険適用促進手当が毎月支払われる場合や3か月以内ごとに支払われる場合には、平均賃金の算定基礎に算入されます。
他方、3か月を超える期間ごとに支払われる場合には、平均賃金の算定基礎に算入されません。
【年次有給休暇に係る賃金】(労働基準法第 39 条)
1 年次有給休暇の期間については、
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③標準報酬月額の 30 分の1に相当する金額(労使協定で定めた場合に限る。) のいずれかを支払う必要があり、
・①の場合は、上記【平均賃金】に記載のとおりとなります。
・②の場合は、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」には、臨時に支払われた賃金等は算入されないことから、割増賃金の取扱いと同様に、社会保険適用促進手当が毎月支払われる場合には、年次有給休暇に係る「通常の賃金」に算入され、臨時に支払われた賃金等に該当する場合には、「通常の 賃金」に算入されません。 なお、「通常の賃金」を支払う場合には、通常の出勤をしたものとして取り扱えば足り、金額の計算をその都度行う必要はありません。
・③の場合は、社会保険適用促進手当は標準報酬月額の算定において考慮しないこととされているため、年次有給休暇に係る賃金の算定基礎に算入されません。
【最低賃金】(最低賃金法第4条)
社会保険適用促進手当は①家族手当、②通勤手当、③精皆勤手当に該当しないと考えられるため、同手当が毎月支払われる場合には、最低賃金の算定基礎に算入されます。
他方、社会保険適用促進手当が毎月支払われず、
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
のいずれかに該当する場合には、最低賃金の算定基礎に算入されません。
長くなりましたが以上になります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001159342.pdf
事業主の証明による被扶養者認定のQ&Aのご紹介(2023/10/23更新)
「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り扱いが示されました。
健康保険、厚生年金関係では、![]()
・社会保険適用促進手当に関するQ&A
・![]() 事業主の証明による被扶養者認定のQ&A
事業主の証明による被扶養者認定のQ&A
が公表されております。
また、「130万円の壁」でお困りの皆様へというリーフレットも公開されております。
https://www.mhlw.go.jp/content/001159346.pdf
今回は、事業主の証明による被扶養者認定のQ&Aから一部抜粋してご紹介します。
(下線は、筆者加筆)
Q1-4
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)はいつから開始されるのでしょうか。また、今回の措置の開始前の扶養認定に遡及されるのでしょうか。
A1-4
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)については、本Q&Aの発出日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用します。 なお、発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る確認については遡及しない取扱いとします。
Q1-6
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)については、あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とすることとされていますが、具体的には何を以て「1回」「連続2回」と数えることとなるのでしょうか。
A1-6
新たに被扶養者を認定する場合を含む被扶養者の収入確認に当たって事業主の証明を用いて一時的な収入変動である旨を保険者が確認した場合には、「1回」と数えられることとなります。
その上で、社会保険の被扶養者の収入確認については、被扶養者として認定した者については、認定後、少なくとも年1回は保険者において被扶養者に係る確認を行い、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認することが望ましいとしています。
したがって、被扶養者の収入確認を年1回実施する場合は、「連続2回」とは連続する2年間の各年における収入確認において事業主の証明を用いることが「連続2回」になります。
Q1-8
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、健康保険組合等の保険者による円滑な被扶養者認定を可能にするとのことですが、どのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められるのでしょうか。
A1-8
一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、
一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、
・当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケースなどが想定されます。
一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
Q2-1
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、どのような方が対象 となるのでしょうか。配偶者(国民年金の第3号被保険者)に限られますか。
A2-1
今回の措置の対象は、配偶者(国民年金第3号被保険者)だけではありません。
社会保険の被扶養者の方、新たに被扶養者としての認定を受けようとしている方が 対象となります。
なお、雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方は、今回の措置の対象外となります。
Q2-3
フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合、今回の措置(事 業主の証明による被扶養者認定の円滑化)の対象となるのでしょうか。
A2-3
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。そのため、特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません。
Q2-5
被扶養者の収入要件の確認について、被扶養者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては年間収入の要件が180万円未満とされていますが、今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、その判定の際にも適用されるのでしょうか。
A2-5
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、被扶養者が 60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合の、年間収入が180万円未満であるか否かの判定についても適用されます。
Q3-1
事業主の証明はいつ、どこに提出するのですか。
A3-1
被扶養者の方について、新たに被扶養者の認定を受ける際、又は健康保険組合等の保険者が被扶養者の資格確認を行う際に、年間収入が確認されることになります。
この際に被扶養者を雇う事業主から一時的な収入変動である旨の事業主の証明を取得し、被保険者の方が勤務している会社を通じて各保険者に対して、通常提出が求められる書類と併せて、事業主の証明を提出することになります。
このため、各保険者の被扶養者の収入確認のタイミングに合わせて、被扶養者の勤務先の事業者から一時的な収入変動である旨の証明を取得してください。
Q3-5
被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、どの事業所から事業主の証明を取得 すれば良いでしょうか。
A3-5
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)について、被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、一時的に年間収入が130万円以上となった主たる要因である勤務先(事業者)から事業主の証明を取得してください。ただし、複数の事業所においてそれぞれ一時的な収入増加がある場合は、それぞれの事業者から事業主の証明を取得してください。 なお、雇用契約書等を踏まえ、複数事業所で勤務することで年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方については、被扶養者に該当しなくなることになります。
Q4-3
税の扶養控除の適用要件や会社の扶養手当(配偶者手当、家族手当等)の受給要件 の認定に当たっても、今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は適用されるのでしょうか。
A4-3
この特例は健康保険等の被扶養者認定及び国民年金第3号被保険者の認定のみに係る取扱いとなり、税等の他制度に関しては通常の取扱いとなります。
なお、配偶者手当を含む会社の扶養手当については、会社において、労使間の話し合いを経て自主的に設定されているものです。このため、会社の扶養手当の収入要件については、個別の会社の判断になりますが、健康保険の被扶養者認定に連動する形で設定している場合、この特例と同様の取扱いとなるものと考えられます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202310/1020.files/hifuyosha_nintei.pdf
また、事業主の証明書も掲載されております。
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(2023/7/3更新)
厚生労働省は、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正についての事務連絡を令和5年6月27日に出しました。
今般、当該取扱いに関する事例を追加し、同事務連絡の別紙1(標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)が別添のとおり改正されました。
以下のQ&Aが追加されました。
問3 事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。
(答) 永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。
ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。
≪永年勤続表彰金における判断要件≫
① 表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230629T0010.pdf
「被扶養者の国内居住要件等について」の一部改正について(2023/6/23更新)
厚生労働省から、「「被扶養者の国内居住要件等について」の一部改正について(令和5年6月19日保保発0619第2号・年管管発0619第1号)」が公表されました。
令和2年4月1日施行の改正法および改正省令により、健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)の要件に、国内居住要件が追加されました。
これを受けて、「被扶養者の国内居住要件等について」(令和元年11月13日付け保保発1113第2号、年管管発1113第4号)により基本的な考え方を整理するとともに、同通知の別紙「国内居住要件に関するQ&A」により、その具体的な取扱いが整理されています。
この度、その取扱いの一層の明確化を図るため、同通知が改正されました。
以下のようなQ&Aが掲載されております。
Q2-2 外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者であって、本来の在留活動を妨げない範囲の付随的な就労を行う場合又は就労しない場合の収入確認について、渡航先での滞在期間が短い等の理由で収入を確認する公的証明等が発行できない場合の取扱如何。
A 渡航先での滞在期間が短い等の理由で公的証明等が発行できない場合は、ビザにおいて、就労の可否、可能な就労の程度を確認し、今後1年間の収入を見込むこと。ビザだけでは判断できない場合は、被保険者の勤務先において扶養手当の支給状況及び支給基準等を提出させ確認を行うこと。なお、出国前の日本国内での収入で判断する場合は、海外に渡航していることによる状況の変化について考慮すること。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230620T0030.pdf
大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の有期雇用労働者の離職理由の取扱いの変更について(2023/6/17更新)
厚生労働省は、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の有期雇用労働者の離職理由の取扱い変更に関する事業主向けのリーフレットを公開しております。
以下の内容が記載されております。
大学等及び研究開発法人の研究者、教員等で契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の上限が到来したことにより離職された場合で、次の要件に該当する場合、離職証明書の「⑦離職理由欄」は以下のとおりご記入をお願いします。
・基準日(改正労働契約法の公布日:平成24年8月10日)以後に締結された9年6か月以上10年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。)ことにより離職された方。
ただし、基準日前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に9年6か月以上10年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。
※令和5年5月29日から令和7年3月31日までに離職した方、又は令和4年2月10日以降に離職して令和5年5月29日以降に受給資格者である方が対象
これに該当する場合は、離職証明書の「⑦離職理由欄」は「3 労働契約期間満了等によるも の」、「(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」を選択していただいた上で、「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載するとともに、最下部の「具体的事情記載欄(事業主用)」に「9年6ヶ月以上1 0年以下の上限」と記載してください。その際、採用当初の雇用契約書と最終更新時の雇用契約書など、それぞれの事情がわかる書類を添付してください。
記載例も以下の通り記載されております。
(出典:厚生労働省リーフレット)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001101714.pdf
報酬・賞与の区分が明確化されます(日本年金機構)(2023/6/15更新)
日本年金機構は、「報酬・賞与の区分の明確化」に関する案内を掲載しております。
厚生労働省の事務連絡が改正され、賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いが明確に示されました。
なお、こちらの改正は、平成30年に示された事務連絡の内容を明確化するためのものであり、従来の取り扱いを変更するものではありません。
〇概要
毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となる取り扱いが明確に記載されました。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.html
「被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い」について(協会けんぽ)(2022/9/20更新)
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、「被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い」についての案内を掲載しております。
被保険者証の氏名等記載変更に係る申出を行うことにより、被保険者証の氏名等の記載を変更した被保険者証が交付されます。
1.性同一性障害を有する方が、被保険者証に通称名を記載する申出を行う場合
※協会がやむを得ないと判断した場合に、被保険者証に通称名等を記載します。
(1)被保険者証の券面記載について
被保険者証表面 氏名欄:「通称名」を記載、性別欄:「裏面参照」と記載
被保険者証裏面 備考欄:「戸籍上の氏名」と「性別」を記載
2.被保険者証に旧姓を併記する申出を行う場合
(1)被保険者証の券面記載について
被保険者証表面 氏名欄:戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」を記載
被保険者証裏面 備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載
3.お申出先、お申出方法(1の通称名記載、2の旧姓併記共通)
事業主を経由して、被保険者証に記載されている協会けんぽ都道府県支部に、申出に必要な書類を郵便でご送付ください。(任意継続健康保険の加入者を除く)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
【社会保障協定】適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先変更について(2022/8/25更新)
日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が、相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、日本の制度に加入していることを証明する適用証明書の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。
最寄りの年金事務所や事務センターに提出していた適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が、令和4年10月1日(土曜)から、次のとおり変更されます。
申請書送付先
〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階
日本年金機構 社会保障協定担当 宛
送付先が変更となる申請書は以下のとおりです。
社会保障協定を発効しているすべての国が対象となります。
1. 厚生年金保険 適用証明書交付申請書
2. 厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書
3. 厚生年金保険 適用証明書再交付申請書
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0823.html
海外で出産した場合の健康保険出産育児一時金支給申請書の添付書類の変更について(2022/8/8更新)
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、海外で出産した場合の添付書類の変更についての案内を掲載しております。
添付書類は、以下の通りとなります。
〇出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書
〇出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し)
〇海外出産の事実、内容について、協会けんぽが当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
【出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書が添付できない場合】
●出産したことを確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書等)(死産の場合は、死産証書(死胎検案書)等)
●海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類、および、「医師・助産師の証明の添付が困難である理由」と「出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面
【本申請にかかる振込先指定口座が受取代理人の口座である場合】
〇受取代理人の本人確認書類(在留資格認定証明書、パスポート、運転免許証等のコピー)
〇受取代理の理由書
【証明書等が外国語で記載されている場合】
〇翻訳文(翻訳文には、翻訳者が署名し住所及び電話番号を明記してください)
※申請する給付の種類に関係なく条件に該当する場合に必要な添付書類
○(除籍)戸籍謄本又は戸籍抄本:被保険者死亡の場合
○本人確認書類:被保険者のマイナンバーを記載した場合(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。)
詳細は、以下よりご確認ください。