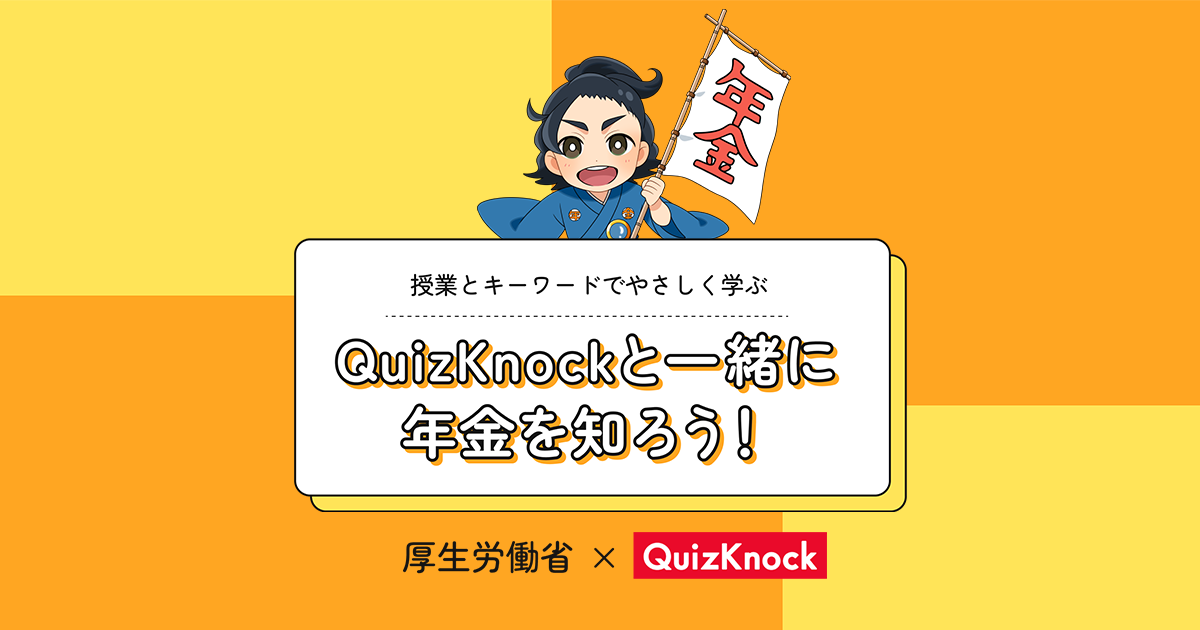日本年金機構からのお知らせ 令和7年6月号のご紹介(2025/6/22更新)
日本年金機構は、日本年金機構からのお知らせ 令和7年6月号を公開しております。
今月号では、以下の内容について記載されております。
〇お願い
・算定基礎届は7月10日までにご提出ください
〇ご案内
・算定基礎届の手続きには、「電子申請」をご利用ください!
昨年度は、算定基礎届の71%が電子申請で提出されたそうです。
〇周知依頼
・~従業員の方へお知らせください~
国民年金保険料の学生納付特例制度、免除等を受けた期間を納めて年金額を増やせます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
ねんきんチャットボットで「オンライン事業所年金情報サービス」の案内を開始(日本年金機構)(2025/6/19更新)
日本年金機構は、令和7年6月13日からねんきんチャットボットで「オンライン事業所年金情報サービス」の案内を開始しました。
「オンライン事業所年金情報サービス」を利用すれば、毎月の社会保険料額情報等の各種情報・通知書を電子データで受け取ることができます。ねんきんチャットボットではサービスの概要や利用方法を案内します。
試しに事業主用の画面を確認してみました。
お問い合わせに対し、いつでも利用可能ですので、ぜひご利用くださいとのことです。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0613.html
年金制度改正法が成立(2025/6/16更新)
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が6月13日に成立しました。
一部修正された改正の概要が掲載されておりますので、ご紹介します。
〇改正の概要(※赤字は、衆議院による修正部分)
Ⅰ 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
1.被用者保険の適用拡大等
① 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃
企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃。
② 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。
※ 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。
③ 適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。
2.在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げ。
3.遺族年金の見直し
① 遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。これに伴う配慮措置等として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う。
② 子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す。
4.厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
標準報酬月額の上限について、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げる(※)ととも に、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。
※ 68万円→71万円→75万円に段階的に引き上げる。
5.将来の基礎年金の給付水準の底上げ
① 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、次期財政検証において基礎年金と厚生年金の調整期間の見通しに著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金又は厚生年金の受給権者の将来における基礎年金の給付水準の向上を図るため、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。
② ①の措置を講ずる場合において、基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかった場合に支給されることとなる基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
Ⅱ .私的年金制度の見直し
① 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げる。
② 企業年金の運用の見える化(情報開示)として厚生労働省が情報を集約し公表することとする
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」を公表(2025/6/14更新)
厚生労働省は、「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」を公表しております。
〇集計結果(令和6年度)
1.新規裁定
・新規裁定1,000件のうち、非該当は130件(13.0%)。令和5年度の非該当割合(8.4%)より上昇し、令和元年度の障害年金業務統計公表開始後、過去最高だった令和元年度(12.4%)とおおむね同水準。
・非該当割合を種類別にみると、精神障害で12.1%、外部障害で10.8%、内部障害で20.6%。令和5年度(精神障害6.4%、外部障害10.2%、内部障害19.4%)と比較すると、精神障害の非該当割合の上昇が大きい。
・内部及び外部障害は、医学的な検査数値等の客観的な指標が障害認定基準に定められており、不支給事案の個別確認の結果、判断の理由が審査資料に明確に記載されているなど、特段の問題点等は確認できなかった。
・一方、精神障害は、そうした指標による評価が必ずしもできない部分があり、ガイドラインや障害等級の目安が定められている。この障害等級の目安との関係をみると、不支給事案に占める「目安より下位等級に認定され不支給となっているケース」又は「目安が2つの等級にまたがるものについて、下位等級に認定され不支給となってい るケース」の割合は75.3%となっていた。
2.再認定
・再認定10,000件のうち、支給停止は105件(1.0%)。令和5年度の支給停止割合(1.1%)と同水準。
また、ヒアリング調査として、 個別確認を行ったケース(新規130件)のうち、精神障害で「障害等級の目安より下位に認定され不支給となっ ているケース」等の計64件について、審査担当職員、センター長等の職員や認定医への ヒアリングを実施した結果をとりまとめたものも掲載されております。
(1)組織的な指示や対応があったか
(事実関係)
・障害年金センター長から、認定の根拠を明確にすべき等といった指摘はあったが、理事長やセンター長等が審査を厳しくすべきといった指示を行っていた等の事実は、確認できなかった。
・認定医に関する文書は、担当者間で引継等に使用。職員が担当する認定医は1~3名程度等であり、選択する余地はほとんどない旨の話があり、組織的に認定をコントロールする意図のものとは認められないが、認定の傾向に関することなど、 一部に適切ではない記載内容も含まれていた。
(今後の対応策)
・認定医に関する文書廃止
・担当認定医の無作為での決定
(3)個別の認定が適正に行われているか
(事実関係)
・審査書類に、判断の理由が明確に記載されているとはいえず、 丁寧さに欠けるものが見受けられる。 ・理由付記文書も申請者にとって分かりにくい記載がある。
・認定医の審査の参考となるよう、等級案も含め、事前確認票が作成されているが、障害等級の目安と、診断書等の内容(病状の経過、具体的な日常生活状況等)をもとに総合的に認定する仕組みの中では、職員による等級案の必要性は高くない。
・令和6年度の不支給割合の上昇は、「障害等級の目安より下位等級に認定され不支給となっているケース」等が増えていることが寄与していると考えられる(44.7%(R5) → 75.3%(R6))。
・令和7年3月の報道を踏まえ、精神障害の新規裁定のうち、その時点で認定医の審査過程で不支給と見込まれた審査中の事案に ついて、より丁寧な審査を行う観点から、障害年金センターに配置される常勤医師による確認を実施し、約1割が支給となった。
(今後の対応策)
・審査書類に丁寧に記載することの徹底
・認定事例の作成・考慮要素の徹底
・理由付記文書の改善
・職員による等級案廃止
・今後の全ての不支給事案について複数の認定医による審査
・過去の精神障害等の不支給等事案の点検
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(日本年金機構)(2025/6/13更新)
日本年金機構は、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等についての案内を掲載しております。
1.令和7年度税制改正の主な内容
(1)所得税の基礎控除の見直し
所得税の基礎控除の見直しにともない、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が、現行の158万円未満から205万円未満に引き上げられました。(65歳未満は現行の108万円未満から155万円未満に引き上げ)
(2)特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳から23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人)を有する場合、その居住者の総所得金額等から、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
令和7年分の所得税において、特定親族特別控除の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
(3)扶養親族等の所得要件の引き上げ
所得税の基礎控除の見直しにともない、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられました。
令和7年分の所得税において、扶養親族等の要件を満たし、扶養控除等の適用を受ける場合には、原則として、確定申告をする必要があります。
2.令和7年分の源泉徴収における取り扱い
令和7年分の所得税については、令和7年12月の年金支払い時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算が行われます。
この精算により還付すべき金額が生じる場合には、原則として、その金額が還付されます。
なお、令和7年分の所得税において特定親族特別控除の適用を受けようとする場合や、扶養親族等の要件を満たすこととなった親族にかかる扶養控除等の適用を受けようとする場合は、原則として、確定申告をする必要があります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0604.html
「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)」を掲載(日本年金機構)(2025/5/27更新)
日本年金機構は、「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)」を掲載しております。
戸籍法および住民基本台帳法の改正により、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、次のとおり年金関係の手続きが必要になる可能性があるため、注意してください。
〇年金受給者の方
年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りします。
「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
※「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)を変更すると、口座名義(フリガナ)と年金記録の氏名のフリガナが相違し、年金の支払いが一時的に止まる場合がありますので注意してください。
〇国民年金第1号被保険者の方
1.国民年金保険料を口座振替によりお支払いいただいている方
「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要となります。
2.国民年金保険料を納付書により納付していただいている方
未納期間がある場合、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合がありますので、重複納付とならないよう注意してください。なお、「氏名の振り仮名」変更前、変更後のいずれの納付書でも納付可能です。
〇健康保険被保険者(協会けんぽ)の方
協会けんぽより資格確認書が発行されている場合は、変更後の「氏名の振り仮名」で資格確認書が発行されます。
また、本件に関するQ&Aも掲載されております。(記載日時点でQ1~Q7)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html
「日本年金機構からのお知らせ 令和7年5月号」のご紹介(2025/5/26更新)
日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ 令和7年5月号」を公開しております。
今月号では、以下の内容が掲載されております。
〇ご案内
・令和7年度社会保険制度説明会のご案内
社会保険事務担当者向けに、オンラインサービスの紹介、届出誤りが多い事例の紹介、算定基礎届の作成方法等が行われる予定です。
・「事業所向けオンラインサービス」のよくある質問にお答えします
「年に数回しか届出の機会がない事業所でもメリットがありますか?」他2つのQ&Aが掲載されております。
〇お願い
・賞与支払届の届け出もれ防止のために、賞与支払予定月の登録をお願いします。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
年金制度改正法案を国会に提出(法案概要について)(2025/5/19更新)
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出されました。
この法律は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再配分の強化や私的年金制度の拡充等により、高齢期における生活の安定を図るためのものです。
以下に法案の概要を記載致します。
Ⅰ .働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
1.被用者保険の適用拡大等
① 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃する。
② 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。
※ 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。
③ 適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支 援する。
2.在職老齢年金制度の見直し
一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げる。
3.遺族年金の見直し
① 遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。
これに伴う配慮措置等として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う。
② 子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す。
4.厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げる
(※)とともに、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。
※ 68万円→71万円→75万円に段階的に引き上げる。
Ⅱ .私的年金制度の見直し
① 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げる。
② 企業年金の運用の見える化(情報開示)として厚生労働省が情報を集約し公表することとする。
Ⅲ .その他
① 子のある年金受給者の保障を強化する観点から子に係る加算額の引上げ等を行いつつ、老齢厚生年金の配偶者加給年金の額を見直す。
② 再入国の許可を受けて出国した外国人について、当該許可の有効期間内は脱退一時金を請求できないこととする。
③ 令和2年改正法附則による検討を引き続き行うに際して社会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置を講じた上で次期財政検証の翌年度まで継続する。
(出典:厚生労働省「法案説明資料(概要版)」)
詳細は、以下よりご確認ください。
公的年金財政状況報告-令和5(2023)年度について(2025/4/22更新)
厚生労働省は、公的年金財政状況報告-令和5(2023)年度を公表しております。(令和7年3月27日)
「公的年金財政状況報告」は、社会保障審議会年金数理部会が、公的年金の毎年度の財政状況について、公的年金の各制度・各実施機関からの報告に基づき、専門的な観点から横断的に分析・評価を行った結果をとりまとめたものです。
(出典:公的年金財政状況報告-令和5(2023)年度)
〇令和5年度公的年金財政状況報告のポイント(一部抜粋)
1.公的年金の収支状況
・公的年金制度全体でみると、運用損益分を除いた収入総額54.4兆円、支出総額54.5兆円であった(運用損益分を除いた単年度収支残は0.1兆円のマイナス)
・時価ベースの運用損益は53.6兆円のプラス。
・時価ベースの年度末積立金は前年度に比べ53.5兆円増加し、304.0兆円。
2.公的年金の財政状況の評価
・令和元(2019)年以降の合計特殊出生率は、平成29(2017)年推計における出生中位の仮定値を下回る水準で推移し、令和5(2023)年は、出生低位の仮定値を下回っていること、また、実質賃金上昇率(対物価)は令和元(2019)年財政検証におけるいずれのケースの前提も下回っていることが確認された。
・これらの将来見通しからの乖離が、一時的なものではなく中長期的に続いた場合には、年金財政に与える影響は大きなものとなる。たとえば、合計特殊出生率が将来推計人口の出生中位の仮定値を下回って推移する傾向が今後も長期にわたって続けば、将来の年金制度の運営は大きな影響を受ける。
・年金財政の観点からは、人口要素、経済要素等いずれも短期的な動向にとらわれることなく、長期的な観点から財政状況の動向を注視すべきである。
詳細は、以下よりご確認ください。
「公的年金財政状況報告-令和5(2023)年度-」をとりまとめ公表(2025/4/1更新)
社会保障審議会年金数理部会は、令和7年3月27日、「公的年金財政状況報告-令和5(2023)年度-」をとりまとめ公表しております。

年金数理部会においては、毎年度、公的年金各制度の財政状況について制度所管省から報告を受けており、本報告は、その内容をもとに、令和5(2023)年度における公的年金の財政状況を専門的な観点から横断的に分析・評価を行った結果をとりまとめたものです。
「公的年金財政状況報告-令和5(2023)年度-(ポイント)」から抜粋してご紹介します。
1 公的年金の収支状況
公的年金制度全体でみると、令和5(2023)年度は、運用損益分を除いた収入総額54.4兆円、支出総額54.5兆円であったことから、運用損益分を除いた単年度収支残は0.1兆円のマイナス。また、時価ベースの運用損益は53.6兆円のプラス。
その結果、時価ベースの年度末積立金は前年度に比べ53.5兆 円増加し、304.0兆円。
2 公的年金の財政状況の評価
・国民年金第1号被保険者数は財政検証の見通しを下回り、厚生年金被保険者数は上回る状況が続いていること、令和5(2023)年度は高い運用収益となった結果、積立金の実績が将来見通しを上回っていること、令和5(2023)年における 65 歳の平均余命は、平成29(2017)年推計における死亡高位の仮定値を下回っていることが確認された。また、令和5(2023)年度は、マクロ経済スライドによる給付水準調整が行われたことにより、年金財政にプラスの効果をもたらしたことに加えて、実質賃金の伸びがプラスになったことにより、平成12(2000)年改正で既裁定年金の物価スラ イドが導入されて以降初めて、賃金の伸びが既裁定年金の伸びを上回ったことが確認された。
・一方で、令和元(2019)年以降の合計特殊出生率は、平成 29(2017)年推計における出生中位の仮定値を下回る水準で推移し、令和5(2023)年は、出生低位の仮定値を下 回っていること、また、実質賃金上昇率(対物価)は令和元(2019)年財政検証におけるいずれのケースの前提も下回っていることが確認された。
・これらの将来見通しからの乖離が、一時的なものではなく中長期的に続いた場合には、年金財政に与える影響は大きなものとなる。たとえば、合計特殊出生率が将来推計人口の出生中位の仮定値を下回って推移する傾向が今後も長期にわたって続けば、将来の年金制度の運営は大きな影響を受ける。
・年金財政の観点からは、人口要素、経済要素等いずれも短期的な動向にとらわれ ることなく、長期的な観点から財政状況の動向を注視すべきである。
詳細は、以下よりご確認ください。
老齢年金請求書にかかる電子申請サービスを利用できる方が拡大されました(2025/3/9更新)
老齢年金請求書にかかる電子申請サービスを利用できる方が拡大されました。
令和6年6月から老齢年金請求書の電子申請サービスが開始されていますが、令和7年3月から配偶者や18歳未満のお子様がいらっしゃる方(同一住所・同一世帯の場合)も新たに電子申請を利用できるようになりました。
電子申請を利用できる方には、受給開始年齢に達する3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」に、電子申請をご案内するリーフレット(PDF)が同封されます。また、マイナポータルを開設している方およびねんきんネット利用者には、マイナポータルおよびねんきんネット経由でお知らせされます。
詳しい手続き等につきましては、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_rorei/denshi_rorei/rourei_seikyu.htm
脱退一時金請求書の様式が変更されました(2025/2/22更新)
国際決済ネットワークであるSWIFT(スイフト/国際銀行間金融通信協会)において、外国送金における事務処理の効率化やマネーロンダリングの規制強化を図るため、外国送金を行うための通信電文フォーマットの見直しが行われました。
これにともない、外国人脱退一時金の外国送金を行う際、「SWIFT(BIC)コード」および受取人住所の「州名(省名)」や「都市名」などの情報が必要になったことから、脱退一時金請求書の様式が見直されました。
◎脱退一時金制度
日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202502/20250203.html
令和7年度における 国民年金保険料の前納額のお知らせについて(2025/2/16更新)
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料額から割引額が控除される「前納制度」を設けております。
厚生労働省は、令和7年度における 国民年金保険料の前納額をお知らせしております。
(1) 6ヶ月前納の場合の保険料額(令和7年4月~令和7年9月分の保険料または令和7年10月~令和8年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:103,870円(毎月納める場合より1,190円の割引額が控除)
・現金納付の場合:104,210円(毎月納める場合より 850円の割引額が控除)
(2)1年前納の場合の保険料額(令和7年4月~令和8年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:205,720円(毎月納める場合より4,400円の割引額が控除)
・現金納付の場合:206,390円(毎月納める場合より3,730円の割引額が控除)
(3)2年前納の場合の保険料額 (令和7年4月~令和9年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:408,150円(毎月納める場合より17, 010円の割引額が控除)
・現金納付の場合:409,490円(毎月納める場合より15, 670円の割引額が控除)
※クレジットカードによる前納の保険料額は現金納付と同じ金額になります。
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年度の年金額改定について(2025/1/25更新)
厚生労働省は、令和7年度の年金額改定についてのお知らせを掲載しております。
令和7年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和6年度から1.9% の引上げとなります。
〇国民年金保険料について
〇在職老齢年金の支給停止調整額
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf
オンラインサービスのサービス拡充について(日本年金機構)(2025/1/22更新)
日本年金機構は、利便性向上を図るため、事業所向け及び個人向けのオ ンラインサービスを提供しています。
令和7年1月から各種オンラインサービスのサービス内容を拡充し、更に便利にご利用いただけるようになりました。本件に関するリーフレットを作成しております。
以下のサービスが拡充されております。
1 事業所向けのオンラインサービスのご利用範囲の拡大
日本年金機構では、社会保険に関する情報や通知書を電子送付する「オンライン事業所年金情報サービス」について、 令和7年1月からは、電子証明書をお持ちの事業主の方及び社会保険労務士の方についてもサービスをご利用いただけるようになりました。
2 個人向けのオンラインサービスのサービス拡充
ねんきんネットやマイナポータルの年金に関するサービスについて、以下の拡充が行われました。
(1)年金受給手続きにおける電子申請の拡大
令和6年6月より、年金の未加入期間がないなど、一定の条件を満たす方を対象に「老齢年金請求書」を電子申請で提出できるサービスを開始していますが、令和7年1月から以下の届書を新たに電子申請の対象に追加しました。
① 老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)
② 年金生活者支援給付金請求書
③ 年金受取機関変更届
(2)ねんきんネットによる相談の開始(試行実施)
電話や年金事務所窓口での相談が難しい、海外にお住まいの方や身体等に障害がある方を対象に、ねんきんネットにログインし、相談事項を入力していただくことで、 後日、日本年金機構から回答を行うサービス(試行実施)が開始されました。
(3)その他のねんきんネットの機能改善
① ねんきんネットから年金事務所窓口における年金相談のネット予約を行うことができる機能の追加
② 保険料の納付実績や将来の年金見込み額等をお知らせする、「ねんきん定期便(電子版)」を更新したことをマイナポータルへお知らせする機能の追加
③ 年金見込み額試算画面の改善
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2025/202501/0107.files/0107.pdf
国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法を追加(2025/1/19更新)
令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法として「2年前納(4月開始)」が追加されました。
〇「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の違い
・「2年前納」
手続き後、初回振替(クレジットカード納付含む。以下同じ。)時に、当月分から翌年度3月分(13カ月から最大で24カ月の2カ年度分)の保険料をまとめて振替(割引あり)
・「2年前納(4月開始)」
手続き後、初回振替時から当年度3月分保険料までは、毎月末日に1カ月分ずつ振替(割引なし)
その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料を振替(割引あり)
「2年前納(4月開始)」を選択し、直近の4月から2年前納の開始を希望する場合は、2月末(必着)までに申出書を日本年金機構に提出してください。なお、2月末までに申出書をご提出いただいた場合でも、口座の確認に時間を要した場合など4月の口座振替(クレジットカード納付)に間に合わない場合があります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202501/0106.html
「社会保障審議会年金部会における 議論の整理」について②(2025/1/6更新)
厚生労働省は、「社会保障審議会年金部会における 議論の整理」を公表しております。
資料の中から、一部抜粋してご紹介します。全部で42パージございますので、2回に分けてご紹介します。(下線は筆者加筆)
Ⅱ 次期年金制度改革等
6 高齢期より前の遺族厚生年金の見直し等
(検討に当たっての問題意識)
・遺族年金については、「社会保障審議会年金部会における議論の整理」(平成 27年1月21日)において「男女がともに就労することが一般化していく(中 略)中で、遺族年金についても、社会の変化に合わせて制度を見直していくこ とが必要」とされており、本部会では、高齢期の前にあたる20代から50代までの遺族を念頭に、制度上の男女差の解消に向けた制度の在り方等について検討を行った。
① 20代から50代の子のない配偶者の遺族厚生年金
(見直しの方向性)
・遺族厚生年金において、女性の就業の進展、共働き世帯の増加等の社会経済状況の変化を踏まえ、男性が主たる生計維持者であることを前提とした考え方を改め、制度上の男女差を解消し、男女それぞれが拠出する保険料を等しく給付に結びつけていく観点から、20代から50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金の給付について時間をかけながら段階的に見直すこととし、事務局から提案があった「②20代から50代の子のある配偶者の遺族厚生年金」の内容も含めた見直し案について概ね意見が一致した。
なお、施行日前に既に受給権が発生している場合や見直しの対象外である60歳以上で死別した場合の遺族厚生年金は、現行制度の仕組みを維持するべ きである。
(具体的な見直し内容)
・20代から50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金を、配偶者の死亡といった生活状況の激変に際し、生活を再建することを目的とする給付と位置づけ、男女とも原則5年間の有期給付として年齢要件に係る男女差を解消する。
ただし、様々な事情により十分な生活再建に至らず、引き続き遺族厚生年金による生活保障の必要性が高い状況にある者への支援の必要性の観点から、所得状況や障害の状態によっては、原則5年間の有期給付が終了した以降も最長65歳到達まで継続して給付(継続給付)を受給できることとする。
継続給付については、その趣旨を勘案し、後述する有期給付加算を含めた額を基本とし、所得の状況に応じて支給額を調整するが、調整に当たっては、収入と支給額の合計額が緩やかに上昇する仕組みとする。
・男女差の解消に伴い、死別時に60歳未満の男性は施行時点から新たに有期給付の受給が可能となる。女性は、30歳未満という現行の有期給付の対象年齢を段階的に引き上げることとし、施行時点では既に男女間の賃金水準の差が一定程度縮小している40歳未満を対象年齢とする。その後は、現に存在する男女の就労環境の違いを考慮するとともに、現行制度を前提に生活設計している者に配慮する観点から、20年程度の時間をかけて60歳未満まで引き上げる。
(有期給付化に伴う配慮措置)
・有期給付の生活再建という観点から、保障を手厚くするため、配偶者の死亡に伴う年金記録分割の導入(死亡分割)、生計維持要件のうち収入要件の撤廃、有期給付加算の創設を行う。
・死亡分割は、離婚時の年金記録分割の仕組み(離婚時分割)と同様に、死亡者の婚姻期間における厚生年金への加入期間の標準報酬月額等を分割することで、残された遺族の将来の老齢厚生年金を増加させる仕組みであり、有期給付の遺族厚生年金を受給後に失権した者を対象とする。
・死亡分割においても、第3号被保険者である期間における分割割合は、離婚時分割に倣って2分の1とする。一方で、双方が厚生年金に加入していた婚姻期間における分割割合は、離婚時分割と異なり、元配偶者の死亡により当事者間で決めることができないという特有の事情を考慮し、2分の1で合意したものと擬制する。
② 20代から50代の子のある配偶者の遺族厚生年金
・18歳未満の子を養育している配偶者については、子が18歳に到達する年度末までの給付内容は現行通りであるが、それ以降も引き続き養育費用が必要な場合や、本格的な就労に向けた準備期間となる場合が想定される。
そのため、現行制度においても、妻が30歳未満に遺族基礎年金を失権した場合にはその後5年間の有期給付の遺族厚生年金を受給できることを踏襲する形で、例えば子が18歳に到達して遺族基礎年金が失権した後も原則5年間の有期給付を受給できることとし、所得状況や障害の状態に応じてはさらにその後の継続給付の受給も可能とする。
・女性のみが対象となっている中高齢寡婦加算については、将来に向かって十分な時間をかけて加算措置を終了する。
なお、見直しに当たっては激変緩和の観点から経過措置を設けることが適当であり、具体的には、施行日前に加算を受給している者は対象とせず、新規に加算が発生する場合のみを対象にし、十分な時間をかけて段階的に逓減させるとともに、受け取り始めた年金額は受け取り終了まで変化させないこととする。
③ 遺族基礎年金(国民年金)
(現行制度と見直しの方向性)
・現行制度において 子に対する遺族基礎年金は、父又は母と生計を同じくするときは、その父又は母が遺族基礎年金の受給権を有していない場合でも、支給停止されている。
たとえば、離婚後に親の一方が亡くなり、その後元配偶者である親に引き取られた場合には子に対する遺族基礎年金は支給停止される。
・現行の遺族厚生年金ではこのような支給停止の規定はなく、遺族基礎年金について子が置かれている状況によって支給が停止される不均衡を解消するため、生計を同じくする父又は母があることによる支給停止規定を見直すことで 概ね意見は一致した。
・寡婦年金の取扱いについては、将来的な廃止を含めて引き続き検討事項とする。併せて、寡婦年金と選択関係にある国民年金の死亡一時金の取扱いについても検討事項とする。
7 年金制度における子に係る加算等
(現行制度と見直しの方向性)
・賦課方式で運営されている年金制度にとって、次世代の育成は制度の根幹を維持するために必要であり、次代の社会を担う子どもの育ちを支援し、子を持つ年金受給者の保障を支援する観点から取組を強化する方向性については概ね意見が一致した。
(具体的な取組)
・児童扶養手当等の近接する制度の状況を考慮し、多子世帯への支援を強化する観点から、公的年金制度における子に係る加算について、第1子・第2子と同額となるまで第3子以降の支給額を増額し、子の人数に関わらず一律の給付とすることについては意見が一致した。
・加算額について、第1子・第2子を含め全体として子に係る加算額を引き上げること、これまで加算対象ではなかった障害厚生年金や遺族厚生年金、老齢基礎年金についても対象を拡大することについては、賛成の意見があった一方で、老齢基礎年金等に子に係る加算を拡大することについては、慎重な意見が複数あった。
その他、子に係る加算の対象となる子について国内居住要件を設けることについては概ね意見が一致したが、子の留学や親の海外赴任についても留意する べきという意見があった。
(配偶者に係る加給年金)
・老齢厚生年金における配偶者に係る加給年金について、社会状況の変化等によりその役割が縮小していることを踏まえ、将来的な廃止も含めて見直す方向性については概ね意見が一致した。今回の改正では、新たに対象となる者の支給額を見直すこととするが、加給年金を前提に生活している者への配慮から、現在の受給者は見直しの対象としないことが適当である。
8 その他の制度改正事項
以下の改正を行うことで概ね意見は一致した。
①障害年金の支給要件のうち、直近1年間に保険料の未納がなければよいとする特例について、障害年金の受給につながるケースが存在していることや今後の取扱いを検討するに当たって丁寧に実態を把握する必要があることを踏まえ、引き続き適用できるよう、時限措置の10年延長を行う。
②国民年金の納付猶予制度について、多くの者が利用していることから同じ年齢を対象として時限措置の5年延長を行う。
③任意加入の特例(高齢任意加入)について、引き続き保険料納付意欲がある者の年金受給の途を開くため、年金受給権確保の観点から、新たに65歳に到達する世代も利用できるよう措置することで本措置の延長を行う。
④離婚時分割の請求期限について、民法上の離婚時の財産分与に係る除斥期間が、離婚後2年間から5年間に伸長されることに伴い、離婚後2年間から5年間に伸長する。
⑤遺族厚生年金の受給権者の老齢年金について、高齢者の就労が進展し、今後繰下げ制度の利用者が増える可能性があることを踏まえて、年金を増額さ せたいという受給者の選択を阻害しない観点から、一定の条件を満たす場合において繰下げ申出を認める。
⑥脱退一時金制度について、将来の年金受給に結び付けやすくするため、再入国の許可を受けて出国した外国人は、当該許可の有効期間内は脱退一時金を請求できないこととする。また、外国人の滞在期間の長期化や入管法等の 改正法により育成就労制度が創設されることを踏まえ、支給上限年数を現行の5年から8年に見直す。
9 今後検討すべき残された課題
① 基礎年金の拠出期間の延長(45年化)
・次期年金制度改革においては、国民に 保険料負担を追加で求める基礎年金の保険料拠出期間(現行40年)の5年延長は行わないこととし、本部会において詳細な制度設計については議論しなかった。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
社会保障審議会年金部会における 議論の整理について①(2025/1/5更新)
厚生労働省は、「社会保障審議会年金部会における 議論の整理」を公表しております。
資料の中から、一部抜粋してご紹介します。全部で42パージございますので、2回に分けてご紹介します。(下線は筆者加筆)
Ⅱ 次期年金制度改革等
1 被用者保険の適用拡大
(短時間労働者への適用拡大)
・「当分の間」の経過措置として設けられた企業規模要件については、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、撤廃する方向で概ね意見が一致した。
・また、月額賃金8.8万円以上とする賃金要件については、就業調整の基準(いわゆる「106万円の壁」)として意識されていることや最低賃金の引上げに伴い週所定労働時間20時間以上とする労働時間要件を満たせば賃金要件を満たす地域や事業所が増加していることを踏まえ、撤廃する方向で概ね意見が一致した。
ただし、最低賃金の動向次第では週20時間の所定労働時間であっても賃金要件を満たさない場合があり得ることから、賃金要件の撤廃によって保険料負担が相対的に過大とならないよう、最低賃金の動向を踏まえつつ、撤廃の時期に配慮すべきである。(中略)最低賃金の減額の特例の対象となる者で、賃金が月額 8.8万円未満の短時間労働者については、希望する場合に、事業主に申し出ることで任意に被用者保険に加入できる仕組みとする。
・週所定労働時間20時間以上とする労働時間要件については、(中略)今回は見直さないこととする。
・学生除外要件については、(中略)今回は見直さないこととする。
(適用事業所の拡大)
・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所における非適用業種については、労働者の勤め先等に中立的な制度を構築する観点等から、解消する方向で概ね意見が一致した。
他方で、常時5人未満の従業員を使用する個人事業所については、(中略)今回は見直さないこととする。
(複数事業所の勤務者やフリーランス等)
・複数の事業所で勤務する者の労働時間等を合算し、被用者保険を適用することについては、社会保障におけるDXの進展を視野に入れながら、実務における実行可能性等を見極めつつ、慎重に検討する必要があるとの意見があり、引き続き検討していく。
・複数の事業所で勤務する者の現行の適用事務について、事業所における事務負担の軽減の観点から見直しの方向性について検討したが、(中略)、医療保険者や日本年金機構、事業者団体等と議論しつつ、複数の事業所で勤務する者の現行の適用事務の見直しを引き続き検討していく。
・他方で、労働基準法上の労働者に該当しない働き方をしているフリーランス等への適用の在り方については、(中略)、諸外国の動向等を注視しつつ、中長期的な課題として引き続き検討していく。
(事業所への配慮等)
・特に、施行時期については、個人事業所への適用拡大の影響が大きいと考えられることから、企業規模要件の撤廃を優先して施行すべきである。
2 いわゆる「年収の壁」と第3号被保険者制度
① いわゆる「106万円の壁」への制度的対応
(就業調整に対応した保険料負担割合を変更できる特例)
・被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生・手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対して、健康保険組合の特例を参考に、被用者保険において、事業主と従業員との合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を時限的に設けることについて、議論を行った。
・本特例の導入については賛成意見が多かったものの、制度の細部までは意見が一致せず、一方で前述のような慎重意見や反対意見が多くあり、部会として意見はまとまらなかった。政府において、本部会での意見を踏まえて、本特例の妥当性や、仮に導入するとした場合の中小企業への負担軽減策を含めた具体的な制度案について、検討を深める必要がある。
② 第3号被保険者制度
(今後の取組の方向性)
・就労している第3号被保険者が第2号被保険者として厚生年金に加入する途を開くことが重要であるとの認識は本部会で共有されており、第3号被保険者制度に係る当面の取組の方向性としては、引き続き適用拡大を進めることにより、第3号被保険者制度の縮小を進めていくことが基本的な方向性となる。
・その上で、その先に残る第3号被保険者の中には様々な属性の者が混在している状況にあり、第3号被保険者制度の将来的な見直しや在り方に言及する意見は多くあった一方で、次期改正における制度の在り方の見直しや将来的な見直しの方向性については、意見がまとまらなかった。
・政府に対して、適用拡大を進めることにより、第3号被保険者制度の縮小・ 見直しに向けたステップを着実に進めるとともに、第3号被保険者の実態も精緻に分析しながら、引き続き検討することを求める。
3 在職老齢年金制度の見直し
(見直しの方向性)
本部会の議論では、
・保険料を拠出した者に対し、それに見合う給付を行うという公的年金の原則との整合性
・高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業を抑制しない、働き方に中立的な仕組みとする観点 から、現行の在職老齢年金制度を見直すことで概ね意見は一致した。
具体的な見直し案について、本部会では、賃金と老齢厚生年金の合計額による支給停止の基準額(現行は50万円)を引き上げる案と、廃止案について議論したが、特定の案に意見はまとまらなかった。
4 標準報酬月額上限の見直し
(見直しの方向性)
現行の標準報酬上限額の改定のルールを見直して新たな等級を追加することについては概ね意見は一致した。なお、上限を引き上げることの負担感は、被保険者本人にも事業主にとっても相当大きいものであることに留意が必要との意見があった。
5 基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了
(本部会における議論)
・過去30年の状況を投影した経済前提を中心に、全国民共通の基礎年金が将来にわたって一定の給付水準を確保することの重要性については、委員の意見が概ね一致した。この観点から、過去30年投影ケースのように、今後の経済が好調に推移しない場合に発動されうる備えとしてはマクロ経済スライドの早期終了の措置を講じることについて賛成の意見の方が多かった。
一方で、慎重な意見もかなりあり、保険料・拠出金・積立金の関係が分かりづらいことや報酬比例部分(2階)の調整期間の延長により足下の年金の給付水準が下がる場合があること、基礎年金水準上昇に伴う国庫負担の増加に対応した財源確保の見通しが曖昧であることなどから国民の理解が得られるのかというものや、厚生年金の積立金を基礎年金(1階)の給付水準の向上に活用することは、実際に厚生年金保険料を負担している被保険者や事業主の理解が得られるのかというものもあり、部会として意見はまとまらなかった。
次回につづく。
詳細は、以下よりご確認ください。
社会保障審議会企業年金・個人年金部会 における議論の整理 (案)について(2025/1/4更新)
厚生労働省は、第39回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会の資料を公開しております。
資料として、社会保障審議会企業年金・個人年金部会 における議論の整理 (案)が掲載されております。資料より一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
Ⅱ 拠出・運用・給付の在り方
1 iDeCo加入可能年齢の上限の引上げ
現行のiDeCoの加入者は、国民年金被保険者であって、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者であることとされている。このため、iDeCo 加入可能年齢の上限を70歳に引き上げるためには、国民年金被保険者以外の者についてiDeCoに加入するための要件を検討する必要がある。その際、iDeCo を含む私的年金は公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした上乗せの制度と位置づけられていることを踏まえて、公的年金の改正の議論も考慮しつつ、具体的な要件について定める必要がある。
現在の要件である国民年金被保険者に加え、公的年金への保険料を納めつつ、上乗せとしての私的年金に加入してきた者が、引き続き老後の資産形成を継続できるよう、60歳から70歳までのiDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする者(具体的には①iDeCoの加入者・運用指図者であった者及び②企業型DC等の私的年金の資産を iDeCo に移換する者)であって、老齢基礎年金や iDeCo の老齢給付金を受給していない者にiDeCoの加入・継続拠出を認めることとすべきである。
2 iDeCo受給開始可能年齢の上限の引上げ
受給開始可能年齢の上限の引上げについては、iDeCoが老後の所得確保のための手段の一つであるとの性質も踏まえるとともに、現在でも高齢期における手続が困難であるといった意見や、更に引き上げた場合の実務上の課題を勘案する必要がある。また、前述のとおり令和4年5月に受給開始年齢の上限が75歳に引き上げられたばかりであり、施行後の70歳以降に受給を開始する者の状況も明らかではない。
このため、iDeCoの受給開始可能年齢の上限は引き続き75歳とし、令和9年4月以降の70歳以降で受給を開始する者の状況等を見極めた上で、受給開始可能年齢をさらに引き上げるのかどうかについて丁寧に議論していくべきである。
3 拠出限度額
(1) 個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額
iDeCo の拠出限度額については、国民年金基金と共通の拠出枠となる第1号被保険者は制度創設以降、企業型DCがある第2号被保険者は2017年以降、企業年金がない第2号被保険者は2010年以降、その拠出限度額が見直されていない。
iDeCoの第2号被保険者の拠出限度額について、企業年金がない場合や、事業主掛金が少ない場合であっても、企業年金と合わせた共通の拠出限度額まで拠出できるよう、見直しを行う。
また、iDeCoの拠出限度額について、後述する企業型DCの拠出限度額と合わせ、経済・社会情勢の変化を踏まえた見直しを行うべきである。
(2)企業型DCの拠出限度額
企業型 DCの拠出限度額は、給付時に退職前給与の6割に相当する水準を公的年金と私的年金とでカバーすることを勘案して設定されている。具体的には、目標となる当該給付水準を満たすために必要な保険料率を、民間事業所の大部分をカバーできる賃金水準に乗じたものを拠出限度額としており、2014年(平成26年)に現在の5.5万円となった。
このため、企業型DCの拠出限度額について、賃金の上昇等の経済・社会情勢の変化を踏まえた見直しを行うべきである。
企業型DC のマッチング拠出における加入者掛金の限度額については、事業主拠出が原則であるという企業年金の性質を踏まえ、DBと同様に事業主掛金額を超えない範囲内で認めることとされてきた。
事業主拠出が原則であるとの企業年金の性質を前提としつつも、マッチング拠出をめぐる現状や第2号被保険者の拠出限度額の見直しの方向性も踏まえ、総合的に従業員の老後の所得保障を手厚くするという趣旨からは、企業型 DC のマッチング拠出について、事業主掛金額を超えられないとする制限を見直す必要がある。
Ⅳ DB・DC制度の環境整備
6 いわゆる選択制DB・選択制DC
いわゆる選択制DBにおいて、DCと同様、事業主が従業員に社会保険・雇用保険等の給付額への影響等を説明するよう、DBの法令解釈通知に追記すべきである。その上で、障害年金や遺族年金を含む社会保険制度における給付に影響を及ぼすことについて、労使協議や導入時・加入時に、従業員に対して正確な説明が行われるよう、取組を進める。
7 自動移換
事業主が取るべき対応として、企業型DCの加入者資格を喪失する前から資格喪失時にかけて、資格喪失時に取るべき対応に係る説明を実施することや、企業型DCの全加入者に対する資格喪失時の個人別管理資産の移換の手続等に関する継続的な説明を実施することとすべきである。
運営管理機関や国民年金基金連合会に対しては、自動移換となった者への周知方法等の改善を引き続き促すべきである。また、国民年金基金連合会に対して、移換手続をしやすくするための取組や、自動移換の現状や制度改正によるシステム改修経費等を踏まえた自動移換の適切な手数料の設定を促すべきである。
8 DCの中途引き出し(脱退一時金)
DCの脱退一時金については、公的年金の脱退一時金の見直しの状況や実務も踏まえ、通算拠出期間について5年から8年へ引き上げる等、見直すべきである。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
遺族年金制度の見直しについて(2024/12/13更新)
厚生労働省は、第23回社会保障審議会年金部会の資料を公開しております。
今回は、以下の議題が取り上げられております。
(1)被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について②
(2)基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了 (マクロ経済スライドの調整期間の一致)について②
(3)遺族年金制度について②
この中から、本日は、
(3)遺族年金制度について、資料より一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
※文章にするとわかりづらいので、厚労省の資料にわかりやすい図が多数掲載されているため、資料より引用してご紹介します。
◆遺族年金制度見直しのポイント
ポイント① 男女差の解消
現行制度では、子のない男性に遺族厚生年金が支給されないケースがありました。
こうした男女差の解消のため、以下のように見直しが検討されております。
(出典:第23回社会保障審議会年金部会の資料3)
ポイント② 改正のイメージ
制度見直し前後の変化のイメージ(子のないケース)は以下の通りです。
また、改正前と改正後の給付のイメージは以下の通りです。
(出典:第23回社会保障審議会年金部会の資料3)
以下のような見直しが検討されております。(A,B,C,Dは、上の図に記載あり)
▶新たに子のない男性にも遺族厚生年金を支給(A)
▶年金額を増額(有期給付加算+死亡分割)(B)
・現行制度の離婚分割を参考に、有期給付の遺族厚生年金(継続給付含む)の受給権が失権した者を対象として、死亡者との婚姻期間中に係る厚年期間の標準報酬等を分割する「配偶者の死亡に伴う年金記録分割」(仮称)を創設する。
・5年間の有期給付となる遺族厚生年金を対象として、現行制度の遺族厚生年金よりも金額を充実させるため、死亡した被保険者の老齢厚生年金の4分の1に相当する額の「有期給付加算」(仮称)を創設する。これにより、有期給付の受給者を支援する。
▶配慮が必要な方は5年目以降も継続して受給可能(C)
継続給付の対象
①障害年金受給権者であって障害の状態にある者
②前年所得に基づく支給額調整
▶収入にかかわらず受給可能(D)
・配偶者であって有期給付の遺族厚生年金の受給権者となる者を対象として、現行制度における生計維持要件のうち収入要件を廃止する
〇現行制度の給付内容が維持される者
・18歳未満の子のある世帯としてみた場合における子を養育する間の遺族給付の内容は、現行制度の給付内容を維持する。
・60歳以降の高齢期に配偶者を亡くした者に対する遺族厚生年金は、現行制度の給付内容を維持する。
・改正法の施行日前に受給権が発生している遺族厚生年金については、現行制度の給付内容を維持する。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
年金制度における子に係る加算等の見直しについて(2024/12/7更新)
厚生労働省は、第22回社会保障審議会年金部会の資料を公開しております。
今回、「年金制度における子に係る加算等」、「国民年金保険料の納付猶予制度」について議題とされております。
今回は、「年金制度における子に係る加算等について」、資料の中から、一部抜粋してご紹介いたします。(下線は筆者加筆)
◆年金制度における子に係る加算等について
まず、年金制度における加算の現状について、以下の図をご確認ください。
(出典:第22回社会保障審議会年金部会 資料1)
上記の図を参照しながら、以下の見直し案を見ていただくとわかりやすいと思います。
〇年金制度における子に係る加算の見直し
(見直しの考え方及び方向性)
視点 ① 多子世帯への支援の強化(第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化)
・児童扶養手当において多子世帯への支援を強化する等、近接する制度の状況を考慮し、公的年金制度における子に係る加算についても、第1子・第2子と同額となるまで、第3子以降の支給額を増額してはどうか。
具体的には次の施策を検討してはどうか。
▶老齢厚生年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金について、第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化
視点 ② 子に係る加算のさらなる拡充
・子の出生時における親の年齢が上昇傾向にある中で、子育て期間中に定年退職等を迎え、主たる収入が年金となる親が増えていくことが想定されることから、年金制度における子に係る加算を拡充してはどうか。
具体的には次の施策を検討してはどうか。
▶子に係る加算額(234,800円(令和6年度価格))の引上げ(※)
▶老齢基礎年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金について、新たに子に係る加算の対象に追加
その他、子の「国内居住要件」の設定、老齢厚生年金の子に係る加給年金の要件緩和(厚生年金加入期間要件を10年に短縮)、厚生年金を優先する併給調整を行うこととしてはどうか。
(※)引上げ額については、民間企業や公務員の子に対する扶養手当などを参考に検討してはどうか。
上記の内容を反映させた全体像が以下の通りです。
(出典:第22回社会保障審議会年金部会 資料1)
〇老齢基礎年金における子に係る加算の検討
【支給要件の考え方】
・老齢基礎年金の受給権が発生した時点で、遺族基礎年金や障害基礎年金と同様の以下の要件を満たし、かつ、その状態が維持されている者に子に係る加算を支給することとしてはどうか。 ▶子の生計を維持
▶子が18歳未満(18歳になる年度末まで。子が障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳未満。)
【加算額の考え方】
・子に係る加算は、子の数に比例して一律に定額を加算する仕組みである。遺族基礎年金や障害基礎年金については、本体給付額も受給資格を満たす者に定額を給付する制度であるが、老齢基礎年金においては保険料の免除や納付猶予等がある中で受給権者の保険料納付状況は様々であり、本体給付の受給額も様々である。
そのため、老齢基礎年金の受給権者間で不公平感が生じないようにする仕組みを検討してはどうか。
・遺族基礎年金において、受給権の取得には長期要件として死亡した者に25年間の受給資格期間を求めている。一 方で、老齢基礎年金は受給資格期間10年間で受給権が発生するため、定額の給付である子に係る加算について、遺族基礎年金の受給権者とのバランスを失することの無いような仕組みを検討してはどうか。
具体的には、加算額の満額支給の要件として、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計月数で25年間(300月) を求めることとし、300月に満たない受給権者はその月数に応じて調整することとしてはどうか。
〇子に係る加算についての国内居住要件の検討
(対象とする子の範囲についての検討)
・児童手当や児童扶養手当では親・子の双方に原則、国内居住要件を設けている。
・類似の目的を有する制度と整合的となることが望ましいが、子に係る加算の対象となる子についても国内居住要件を設けること(※)として はどうか。
(※)加算の対象である「子」に国内居住要件を設け、受給権者である「親」には現行どおり国内居住要件を課さないことを想定。
・社会保険である年金制度において、加算の対象となる子の範囲に国内居住要件を設けることについては、今回の拡充後の子に係る加算の性格を踏まえ、以下のような視点から整理してはどうか。
▶本体部分の年金給付は保険料の拠出と保険給付が対価的な関係にある。一方で、子に係る加算については子の数に比例する定額給付であり、子の数に関わらず負担する保険料が不変であることを踏まえると、原則として、加算部分の給付は保険料拠出と対価的な関係にはないといえる。 このような性格を持つ今回の子に係る加算の拡充は、次世代育成支援という政策的な目的で行うものであり、その趣旨を踏まえれば、支給対象に一定の制約を設けることは政策的な配慮の範囲内と整理できるのではないか。
▶これまで年金制度において、福祉年金等の保険料負担と結びついていない給付については国内居住要件を設けて運用されている。
〇配偶者加給年金(老齢厚生年金)の主な制度改正とその考え方について
(現状と方向性)
・夫婦がともに65歳に到達し、基礎年金を受給するまでの間(一方が65歳以上、その配偶者が65歳未満である間)は、受給権者の老齢基礎年金と配偶者加給年金額を加算した老齢厚生年金により世帯の給付水準を維持するという考え方で配偶者加給年金が支給されている。
・高齢期における就業が進展する中で、65歳前の配偶者が就労して報酬を得ているとしても、受給権者の老齢厚生年金に加算されている加給年金が支給停止されることはなく、加給年金は単に生計維持関係(配偶者との同居と、配偶者の収入が850万円未満であることが条件)にある65歳未満の年下の配偶者がいれば加算されることになる。
・女性の就業率の向上に伴う共働き世帯の増加など社会状況の変化等を踏まえ、扶養する年下の配偶者がいる場合にのみ支給される配偶者に係る加算の役割は縮小していくと考えられることから、現在受給している者への支給額は維持した上で、将来 新たに受給権を得る者に限って支給額について見直すことを検討してはどうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
在職老齢年金制度の見直しの方向性について(2024/11/26更新)
厚生労働省は、第21回社会保障審議会年金部会の資料を公開しております。
資料の中から、「在職老齢年金制度について」について、一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
在職老齢年金制度は、厚生年金の適用事業所で就労し、一定以上の賃金を得ている60歳以上の厚生年金受給者を対象に、原則として被保険者として保険料負担を求めるとともに、年金支給を停止する仕組みです。(70歳以降は厚生年金被保険者とならないため、保険料負担はなし。)
(出典:第21回社会保障審議会年金部会 資料2 在職老齢年金制度について)
〇現行制度の見直しの意義
・現在のところ65歳以上の在職老齢年金制度による就業抑制効果について実証研究に基づく定量的な確認はされていないが、世論調査に基づくと、60代後半の3割強が「厚生年金を受け取る年齢になったときの働き方」の問に対し、「年金額が減らないように、就業時間を調整しながら会社などで働く」と回答しており、一定程度の高齢者は在職老齢年金制度の存在を意識しながら働いている様子が伺える。
・高齢化や人手不足を背景に一部の業界から、「人材確保や技能継承等の観点から、高齢者活躍の重要性がより一層高まっているが、在職老齢年金制度を意識した就業調整が存在しており、今後、高齢者の賃金も上昇していく傾向にある。高齢者就業が十分に進まないと、サービスや製品の供給に支障が出かねない」といった旨の声も聞かれ、少子高齢化が進行し、こうした状況が今後様々な業界へと波及することもあり得る。
・在職老齢年金制度が高齢者の就業意欲を削ぎ、さらなる労働参加を妨げている例も存在していることを踏まえ、高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業を抑制しない、働き方に中立的な仕組みとする観点から、在職老齢年金制度の見直しを検討する。
〇在職老齢年金制度の見直しの方向性
・在職老齢年金制度が高齢者の就業意欲を削ぎ、さらなる労働参加を妨げている例も存在していることを踏まえ、高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業を抑制しない、働き方に中立的な仕組みとする観点から、在職老齢年金制度の見直しを検討することとしてはどうか。
・在職老齢年金制度を撤廃した場合は将来世代の給付水準が低下するため、現行制度を維持すべきといった意見もある。このため、在職老齢年金制度を撤廃する案に加え、基準額を引上げる案を検討することとしてはどうか。
(出典:第21回社会保障審議会年金部会 資料2 在職老齢年金制度について)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
脱退一時金に関する見直しの方向性ついて(2024/11/21更新)
厚生労働省は、第20回社会保障審議会年金部会の資料を公開しております。
資料より、脱退一時金に関する見直しの方向性ついてご紹介します。(下線は筆者加筆)
脱退一時金制度に関する見直しの方向性
【現行制度】
・外国人の場合は、滞在期間が短く、保険料納付が老齢給付に結び付きにくいという特有の事情を踏まえ、脱退一時金制度を設けている。また、脱退一時金を受給するとそれまでの被保険者期間がなくなる。
・脱退一時金については、在留資格の見直しや外国人の滞在期間の長期化を踏まえ、令和2年改正で支給上限額を3年から5年に引き上げた。
【脱退一時金に係る状況の変化等】
・平成29年8月、老齢年金を受け取るために必要な受給資格期間が25年から10年に改正された。
・令和2年改正時と比べて、5~10年滞在した外国人の割合が約6%から約18%に増加しているなど、老後を日本で暮らす可能性がある外国人も増加していると考えられる。
・本年成立した入管法等の一部を改正する法律により、今後、育成就労制度が創設され、育成就労制度(3年)を経て特定技能1号(5年)に移行し、計8年我が国に滞在する者が増加すると考えられる。
・現行制度においては、再入国許可付き出国をした場合でも脱退一時金の受給が可能となっており、滞在途中の一時的な帰国の際に脱退一時金を受給するとそれまでの年金加入期間がなくなってしまうこととなる。
【検討の方向性】
・原則として単純出国した場合のみ脱退一時金を支給することとし、再入国許可付きで出国した者には当該許可の有効期間内は脱退一時金は支給しない(再入国しないまま許可期限を経過した場合には受給が可能と なる。)こととすることについてどう考えるか。
なお、その場合は、施行後に十分に年金加入期間を確保できず、年金と脱退一時金のいずれの支給にもつながらない場合等も考慮し、必要な経過措置を設けることとしてはどうか。
・在留資格の見直しや、在留外国人の滞在期間も踏まえて、現行の支給上限を5年から8年に引き上げることについてどう考えるか。
・こうした見直しを行うこととした場合は、施行に際し、在留外国人に年金や脱退一時金の仕組みや趣旨といった必要な情報がしっかりと伝わるよう、運用上の工夫を図ることとしてはどうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等の省略について(2024/11/3更新)
日本年金機構では令和6年11月1日(金曜)から、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始しました。
これにともない、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となります。
対象となる範囲は、請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合です。
日本年金機構において戸籍関係情報の情報連携の対象となる届書や添付が省略できる書類は、「情報連携を行う届書等一覧(PDF)」または各届書における案内をご確認ください。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html
日本国外の金融機関で年金を受け取っている方への年金支払いに関する手続きのお願い(日本年金機構)(2024/10/27更新)
日本年金機構は、日本国外の金融機関で年金を受け取っている方への年金支払いに関する手続きのお願いをホームページに掲載しております。
国際決済ネットワークであるSWIFT(国際銀行間金融通信協会)において、外国送金におけるマネーロンダリングの規制強化や外国送金事務の効率化を図ることを目的として、外国送金を行う際は、送金先の金融機関のSWIFT(BIC)コードやお客様の住所の都市名・州名が必要となりました。
年金の外国送金についても、今後、SWIFT(BIC)コードなどが必要となりますが、日本年金機構ではこれらの情報を管理していないことから、日本国外の金融機関で年金を受け取られている方へ、「外国送金者にかかる住所・受取金融機関情報の回答書」が順次、送付されます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1023.html
令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定について(2024/10/7更新)
日本年金機構は、令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせしております。
●送付予定日
次の送付予定日に、日本年金機構から対象者あてに控除証明書が送付されます。
(※)「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った場合、郵送は行われません。
その他、電子データの控除証明について、控除証明書の送付時期に関するQ&Aなども掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1004.html
第18回社会保障審議会年金部会の資料について(2024/9/29更新)
厚生労働省は、9月20日に開催された第18回社会保障審議会年金部会の資料を公開しております。
今回、以下に関する資料が掲載されております。
・働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方について
・国民年金保険料の納付猶予制度について
・国民年金における任意加入の特例(高齢任意加入)について
・公的年金シミュレーターについて
上記に関して、資料より一部抜粋してご紹介します。
○国民年金保険料の納付猶予制度について
◆納付猶予制度に関する検討の方向性
(1)納付猶予制度については、被保険者の対象年齢の要件は現行通り(被保険者が50歳未満であること。)とした上で、時限措置を延長することを検討してはどうか。
(2)納付猶予制度の延長に際しては、制度の基本的な考え方は維持しつつ、所得要件については、本人及び配偶者の前年の所得が一定額以下であっても、保険料納付の原則に立ち返って世帯主(親など)に一定以上の所得がある場合は納付猶予の対象外とし、保険料納付を求めることを検討してはどうか。
○国民年金における任意加入の特例(高齢任意加入)について
◆見直しの方向性
・年金制度は、保険事故が発生するまでの間に保険料を拠出することとされており、老齢基礎年金の支給要件である65歳到達後に保険料を拠出できる任意加入の特例として位置づけられている。
・任意加入の特例は、昭和40(1965)年4月1日(昭和39年度)までに生まれた者を対象とした時限措置であり、令和11(2029)年度には昭和40年4月1日生まれの者が65歳に到達する。
・こうした中で、任意加入の特例は、老齢基礎年金受給に必要な資格期間を満たさない者を年金受給権の取得につなげる重要な役割を果たしており、令和4年度時点でも任意加入の特例を利用している者の数は約1,500人存在する。
・これまでの改正経緯等も踏まえ、引き続き保険料納付意欲がある者の年金受給の途を開くため、年金受給権確保の観点から、昭和50 (1975)年4月1日(昭和49年度)までに生まれた者まで対象とする方向で検討する。
○公的年金シミュレーターについて
◆次期公的年金シミュレーターの開発方針(案)
・次期公的年金シミュレーターは、現行の考え方を継承しつつ、
➢年金の仕組みや制度改正の内容を国民に分かりやすく周知すること
➢働き方などの変化に伴う年金額の変化を「見える化」し、国民一人一人の生活設計を支援すること を目的として運用することとし、そのために必要な機能を装備する。
・公的年金シミュレーターの利用をさらに促進するため、手軽に利用できる、円滑に操作できる、画面が見やすいといった現行の特徴を維持する。個人情報の記録や保存を行わず、IDパスワードを用いないことも現行どおりとする。
◆次期公的年金シミュレーターの機能(案)
・老齢年金については、現行の機能を維持する。さらに改善や追加を行うべき機能がないか、検討する。 ・現行の老齢年金に加えて、障害年金等の試算機能、iDeCoの試算機能を追加する。
・新たな試算機能の追加にあたっては、障害年金等、iDeCoの基本的な仕組みや特徴を分かりやすく国民に周知するとともに、生活設計に役立つように年金額を「見える化」することを目的として、できる限り簡素で使いやすい設計にする。
詳細は、以下よりご確認ください。
国民年金保険料のスマートフォンアプリで支払いに対応する決済アプリの追加について(2024/9/28更新)
2024年10月1日(火曜)より、国民年金保険料のスマートフォンアプリでのお支払いに対応する決済アプリに「AEON Pay」が追加されます。
(出典:日本年金機構ホームページ)
スマホ決済の利用には納付書と対応する決済アプリが必要です。「領収(納付受託)済通知書」(納付書)のバーコードを、決済アプリで読み取ることによって、電子決済できます。
現在、対象の決済アプリは以下のとおりです。(五十音順)
・auPAY
・d払い
・PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)
・PayPay
・LINE Pay(2023年11月1日から対象)
・楽天ペイ(2023年4月17日から対象)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/smartphone.html
日・ポーランド社会保障協定交渉で実質合意(2024/9/22更新)
日・ポーランド両国政府は、東京において、本年9月9日から13日まで日・ポーランド社会保障協定の締結に向けた第2回政府間交渉を実施し、同協定について今般実質合意に至りました。
日・ポーランド社会保障協定の締結により、日・ポーランド両国からそれぞれ相手国に派遣される企業駐在員等について、日・ポーランド双方の社会保障制度への加入が義務付けられる等の課題が解決され、両国間の人的交流及び経済交流がさらに
促進されることが期待されます。
詳細は、以下よりご確認ください。
海外で年金を受け取る場合の届書様式を変更(日本年金機構)(2024/8/19更新)
日本年金機構は海外で年金を受け取る場合の届書様式を変更しました。
以下の様式が掲載されております。
![]() ・外国居住年金受給権者
住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法
・外国居住年金受給権者
住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法
![]() ・租税条約に関する届出書(様式9)
・租税条約に関する届出書(様式9)
![]() ・特典条項に関する付表(様式17-米)
・特典条項に関する付表(様式17-米)
その他、同ページには、関連情報として、
・年金を受けている方が海外に転出するとき
・海外にお住まいの年金を受けている方が引っ越しをしたとき
・海外にお住まいの年金を受けている方が海外の金融機関の口座で受け取りを希望するとき
などの関連情報の参照先も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/kaigai.html
国民年金保険料のねんきんネットから納付について(2024/8/11更新)
令和6年8月5日(月曜)から、納付書がお手元になくてもねんきんネットから国民年金保険料を納付できるサービスが再開されました。
ねんきんネットに表示される納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を利用して、インターネットバンキングでPay-easy(ペイジー)納付ができる仕組みです。お手元に納付書がなくてもその場で納付できます。
●納付可能な保険料
「納付書によらない納付」で納付できる保険料は前月分以前の保険料です。
(当月分以降の保険料は納付できません。)
ただし、以下の場合は、前月分以前の未納期間の保険料であっても、「納付書によらない納付」では納付できません。
・複数の月をまとめて納付することはできません。(1カ月分ずつ納付できます。)
・免除または納付猶予、学生納付特例等が承認されている期間の保険料を追納することはできません。
納付書によらない納付を利用するためには、ねんきんネットの登録が必要です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202408/0805.html
「ねんきんネット」持ち主不明記録検索機能のスマートフォン専用画面を新設(2024/6/20更新)
日本年金機構は、「ねんきんネット」持ち主不明記録検索機能のスマートフォン専用画面の新設についての案内を掲載しております。
「ねんきんネット」では、国のコンピューターで管理されている年金記録のうち、現在持ち主がわからなくなっているもの(持ち主不明記録)などを検索できる「持ち主不明記録検索」機能があります。
令和6年6月17日(月曜)からスマートフォンで利用する方向けの検索画面が新たに設けられました。
すでに亡くなっている方の年金記録をご家族等が検索することも可能です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/introduction/unknownrecord.html
年金の制度や手続きに関する各種動画を閲覧できるページを新設(日本年金機構)(2024/6/12更新)
日本年金機構は、年金の制度や手続きに関する各種動画を閲覧できるページを新設しました。
現在、以下の動画が掲載されております。
1.国民年金に関する動画(自営業者の方や学生の方向け)
・20歳になったら国民年金(20歳になった方に向けた制度説明動画)
・国民年金に関する電子申請
・確定申告・年末調整に必要な通知書の電子送付
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書の記載方法
・簡易な所得見込額の申立書の記載方法
2.厚生年金保険に関する動画(事業主の方や会社員の方向け)
・健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
・算定基礎届事務説明
・電子申請のご利用案内
・オンライン事業所年金情報サービス
・健康保険・厚生年金保険 子育て支援のための制度
・厚生年金保険料等の猶予に関する動画
3.年金の請求手続きに関する動画
・老齢年金請求書の記載方法について
・老齢年金請求書の電子申請手順
・年金請求書(遺族基礎年金)の記載方法について
・年金請求書(遺族厚生年金)の記載方法について
・障害基礎年金請求書の記入方法について
・障害厚生年金請求書の記入方法について
・未支給年金・未支払給付金請求書の記載方法について
4.年金を受け取っている方の手続きに関する動画
・扶養親族等申告書の提出方法/所得の計算方法
・確定申告・年末調整に必要な通知書の電子送付
5.年金について学べる動画
・知っておきたい年金のはなし(手話・字幕版/多言語版)
・公的年金はみんなの強い味方
・退職後の年金手続きガイド
・障害年金ガイド(手話・字幕版)
・「わたしと年金」エッセイ 受賞作品朗読動画
・国民年金ってホントに必要なの!講座
・QuizKnockによる年金クイズ動画
動画は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/doga/index.html
楽しく年金制度を学べる中高生向け年金教育教材を公開(厚労省)(2024/6/1更新)
厚生労働省は、ワークシートと特設サイトから成る中高生向け年金教育教材を新たに公開しました。
この教材は、年金制度について分かりやすく、楽しく学べるよう、「QuizKnock」とコラボレーションをして制作されたものです。中学校、高等学校の学習指導要領を参考に3時間分の授業を用意し、授業を通じて将来のライフプランと年金制度について考えながら探究学習を進められるように工夫されています。
以下の内容が掲載されております。
●QuizKnockと知る年金授業
・1時間目 公的年金ってどんな制度?
・2時間目 ライフプランと年金制度
・3時間目 年金制度を考えてみよう
●授業資料のダウンロード
●サクッと学べる!!年金制度12のキーワード
年金授業については、動画を交えて年金制度についてクイズ形式で解説されており、わかりやすく説明されております。学生向けのものですが、一般の方でも、視聴されると年金制度への理解が深まると思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
老齢年金請求書にかかる電子申請サービスが開始されます(2024/5/30更新)
利便性の向上等を図るため、令和6年6月3日(月曜)から、年金の未加入期間がないなど一定の条件を満たす方を対象に、「老齢年金請求書」を電子申請により提出することができるようになります。
電子申請が可能な方には、日本年金機構から送付する「年金請求書(事前送付用)」に電子申請をご案内するリーフレット(PDF)が同封されます。
個人の方の電子申請(老齢年金請求書)について、特集ページが開設されており、
以下の内容が掲載されております。
1.老齢年金請求書の電子申請の説明動画
2.老齢年金請求書の電子申請利用対象者
3.電子申請を利用するために必要な手続き
4.電子申請の手続き画面への入り方
5.電子申請の流れ
6.老齢年金請求書に関するお問い合わせ先
7.老齢年金請求書を紙で提出したい場合
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202405/0522.html
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税について(日本年金機構)(2024/5/14更新)
令和6年3月28日に税制改正法が成立し、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
日本年金機構は、本件に関する案内を掲載しております。
(1)控除される金額
所得税および個人住民税の定額減税が行われます。減税される金額は、次の金額の合計です。なお、合計額が所得税額または個人住民税額を超える場合は、それぞれの税額が減税額の限度となります。
なお、減税の対象は国内居住者に限ります。
※1 令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が48万円以下の者に限る。
※2 令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)で合計所得金額の見積額が48万円以下の者に限る。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2024/teigakugenzei.html
年金の制度や仕組みに関するパンフレットを更新(2024/4/5更新)
日本年金機構は、年金の制度や仕組みに関するパンフレットを掲載しております。
2024年4月1日付で以下のパンフレットが更新されました。
・知っておきたい年金のはなし
・太郎と花子の人生行路(ライフステージと年金)
山あり谷ありの人生を送る一組の夫婦をモデルに、ライフステージと年金との関係を紹介しております。
・国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり
・退職後の年金手続きガイド
お勤め先を退職する方向けに、年金手続き等を説明したパンフレットです。
・20歳になったら国民年金
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html
「わかりやすい日本語」による記事を新設(日本年金機構)(2024/3/27更新)
日本年金機構は、「わかりやすい日本語」による記事を新設しました。
記事では、以下の内容が掲載されております。
〇公的年金制度(こうてきねんきんせいど)とは
〇基礎年金番号(きそねんきんばんごう)と基礎年金番号通知書(きそねんきんばんごうつうちしょ)
〇国民年金(こくみんねんきん)
・国民年金(こくみんねんきん)にかならず入る人(はいるひと)
・国民年金(こくみんねんきん)の保険料(ほけんりょう)
・もらえるお金(おかね)(国民年金(こくみんねんきん))
〇健康保険(けんこうほけん)と厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)
・健康保険(けんこうほけん)と厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に入る人(はいるひと)
・健康保険(けんこうほけん)と厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)の保険料(ほけんりょう)
・もらえるお金(おかね)(厚生年金保険(こうせいねんきんほけん))
〇脱退一時金(だったいいちじきん)/日本からはなれるときにもらえるお金
外国人労働者の方にもわかりやすいように、漢字には振り仮名が振ってあります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202403/032602.html
国民年金保険料のねんきんネット納付について(2024/1/8更新)
国民年金保険料は、令和6年1月9日(火曜)から納付書がお手元になくてもねんきんネットから納付できるようになります。
(出典:日本年金機構ホームページ)
ねんきんネットに表示される納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を利用して、インターネットバンキングでPay-easy(ペイジー)納付ができる仕組みです。お手元に納付書がなくてもその場で納付できます。
◆納付可能な保険料
納付書によらない納付で納付できる国民年金保険料は前月分以前の国民年金保険料と追納の申込みが承認された期間の国民年金保険料(追納保険料)です。当月分以降の保険料は納付できません。
◆納付書によらない納付の利用方法
・ねんきんネットへのログイン方法
「マイナンバーカードを利用する方法」と「ユーザID・パスワードを利用する方法」のどちらかでねんきんネットにログインできます。
・マイナンバーカードを利用してねんきんネットにログインする方法
「マイナポータルからログイン」を選択すると、マイナポータルのトップページが表示されます。マイナポータルにログイン後、トップページの「もっとつながる」を選択し、ねんきんネットにログインします。
・ユーザID・パスワードを利用してねんきんネットにログインする方法
ねんきんネットのユーザIDとパスワードを入力後「ログイン」ボタンをクリックし、ねんきんネットにログインします。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/nofusholess.html
国民年金における育児期間の保険料免除について(2023/12/31更新)
厚生労働省は、令和5年12月26日に開催された「第11回社会保障審議会年金部会」の資料を公開しております。
資料として、以下の2点が掲載されております。
資料1 国民年金における育児期間の保険料免除について
資料2 標準報酬月額の上限について
自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料免除措置を創設する。
※当該期間に係る被保険者期間の各月を保険料納付済期間に算入する。
(出典:第11回社会保障審議会年金部会資料)
◆免除に係る要件等
➢ 対象者や要件等
・育児休業制度や厚生年金保険における育児休業等期間における保険料免除制度(夫婦ともに育児休業を取得した場合はともに免除)も参考に、共働き・共育てを推進するための経済支援として、両親ともに育児期間の国民年金保険料免除を認めることとし、子を養育する国民年金第1号被保険者を父母(養父母を含む)ともに措置の対象とする。
・育児休業を取得することができる被用者とは異なり、自営業・フリーランス・無業者等の国民年金第1号被保険者については、育児期間における就業の有無や所得の状況はさまざまであることから、その多様な実態を踏まえ、育児期間における第1号被保険者全体に対する経済的な給付に相当する支援措置を講じることとし、一般的に保険料免除を行う際に勘案する所得要件や休業要件は設けない。
➢ 対象となる免除期間の考え方
・厚生年金保険の育児休業等期間の保険料免除制度では、育児・介護休業法に定める育児休業等をしている期間を免除の対象としているところ、育児休業制度・育児休業給付の対象期間が、原則として子が1歳に達するまでとしていることを踏まえ、経済的支援として行う今般の国民年金第1号被保険者に対する育児期間の保険料免除についても、原則として子を養育することになった日から子が1歳になるまでを育児期間免除の対象期間とし、産前産後免除が適用される実母の場合は産後免除期間に引き続く9ヶ月を育児期間免除の対象期間とする。
・育児期間免除の対象期間における基礎年金額については満額を保障する。
➢ 対象となる子の範囲
・厚生年金保険における被保険者の育児休業等期間中の保険料免除に係る子と同様の範囲とし、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童についても対象として含む。
2026年度中施行予定です。
資料2 標準報酬月額の上限について
〇標準報酬月額の上限の在り方について
制度の現状
・平成16年改正において、各年度末時点において、全被保険者の平均標準報酬月額の2倍に相当する額が標準報酬月額の上限を上回り、その状態が継続すると認められる場合には、政令で、上限の上に等級を追加できることとし、このルールを法定化した。このルールに基づき、これまで、令和2年9月に現在の上限となる等級(65万円)を追加した。
・上限の上に等級を追加した場合、新たな上限等級に該当する者の報酬比例部分が増加するとともに、保険料収入が増加し、また、積立金の運用益も増加することとなるため、厚生年金受給者全体の将来の給付水準も上昇する(所得再分配機能の強化につながる。)。
・厚生年金保険(第1号厚生年金被保険者のみ)では、
上限等級(65万円)に該当する者の割合は6.3%となっており、健康保険と比較すると、多くの者が上限等級に該当している(健康保険では1%未満)。また、上限等級に該当する者の割合は女性よりも男性の方が高く、かつ、男性については上限等級に最頻値が見られる。
上限等級(65万円)に該当する者の年間標準賞与額の分布をみると、約4割は0円となっている。
・ 厚生年金保険の上限等級の額について、健康保険と比べると、平成16年改正以降、大きく差が開いている。
ご議論いただきたい点
・厚生年金被保険者の分布や、上限等級に該当する者の賞与の実態、健康保険の上限等級との比較を踏まえると、現行の厚生年金保険制度は、負担能力のある被保険者に対して、実際の負担能力に応じた保険料負担を求めることができていないのではないか。負担能力に応じて負担を求める観点や、所得再分配機能を強化する観点から、現行のルールを見直して、上限の上に等級を追加することについて、どのように考えるか。
・仮にそのような見直しを行った場合、新たな上限等級に該当する者とその事業主の保険料負担が増加すること、また、歴史的には給付額の差があまり大きくならないように上限が設けられてきたことを考慮すると、どのようなルールで上限を設定することが適当と考えられるか。
・厚生年金の財政としては、保険料収入が増加し、積立金の運用益も増加することから、その増加分の使途についてどのように考えるか。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20231226.html
「年金請求書(遺族基礎年金)の記載方法について」(動画)のご紹介(2023/12/21更新)
日本年金機構は、「年金請求書(遺族基礎年金)の記載方法について」(動画)を掲載しました。(50分32秒:YouTube厚生労働省チャンネル)
本動画では、遺族基礎年金を請求される方々へ、基本的な制度や請求書の記載方法を説明しております。
動画は以下の内容で構成されております。
・年金制度の概要
・添付書類
・請求書(本紙)1枚目の記載方法
・請求書(本紙)2枚目の記載方法
・請求書(本紙)3枚目の記載方法
・請求書(本紙)4枚目の記載方法
・請求書(本紙)5枚目の記載方法
・請求書(別紙)1ページの記載方法
・請求書(別紙)2ページの記載方法
・提出先
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/izoku/20180305.html
動画「未支給年金・未支払給付金請求書の記載方法について」を公開(日本年金機構)(2023/10/13更新)
日本年金機構は、動画「未支給年金・未支払給付金請求書の記載方法について」を掲載しました。
YouTube厚生労働省チャンネルで、書き方のポイントや注意点を交えながら、請求書の記載方法をご紹介した動画です。動画の再生時間は、29分27秒です。
動画では以下の内容が説明されております。
・未支給年金とは
・未支給年金の請求について
・未支給年金を請求できる方
・未支給年金を請求できる範囲と優先順位
・添付書類
・記載方法
・提出先
・提出後の流れ
・お問合せ先
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20140731-02.html
動画「障害厚生年金請求書の記入方法について」を公開(日本年金機構)(2023/10/12更新)
日本年金機構は、動画「障害厚生年金請求書の記入方法について」をホームページに掲載しました。
YouTube厚生労働省チャンネルで、書き方のポイントや注意点を交えながら、請求書の書き方をご紹介した動画を掲載しています。
動画は、全体版(43分20秒)と分割版の2種類がございます。
分割版は以下の内容で構成されております。
【分割版】障害厚生年金請求書の記入方法について
1.受給要件(2:49)
2.年金請求書1ページ目の書き方(氏名・住所、年金受取機関、配偶者・子についてなど)(11:11)
3.年金請求書3ページ目の書き方(配偶者の受給状況、他の年金の受給状況、年金加入履歴など)(6:34)
4.年金請求書5ページ目の書き方(障害給付の請求事由、傷病について、生計維持申立など)(11:41)
5.年金請求書7ページ目の書き方(請求者や配偶者の過去の年金加入状況など)(4:30)
6.年金請求書8ページ目の書き方(委任状について)(2:05)
7.添付書類(2:40)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shougaikousei.html
扶養親族等申告書がスマートフォン等で提出できるようになりました(日本年金機構)(2023/9/12更新)
マイナポータルからねんきんネットを利用されている方を対象に、令和6年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「申告書」という。)を、スマートフォンやパソコンで電子申請できるようになりました。
日本年金機構の「マイナポータルを利用した電子申請(扶養親族等申告書)」の特集ページでは、扶養親等申告書の電子申請の説明動画も掲載されております。
動画は、【継続】前年の扶養親族等申告書を提出した方向けのものと【新規】前年の扶養親族等申告書を提出していない方向けのものと2種類掲載されております。
以下の内容が掲載されております。
・オンライン提出の事前準備
・申告書の作成画面の入り方
・申告書の作成
・提出する申告書の確認
・電子署名の付与
・提出完了
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_rorei/denshi_fuyo/shinsei_fuyo.html
「ねんきんネット」に関するパンフレットを公開(日本年金機構)(2023/6/21更新)
日本年金機構は、「ねんきんネット」に関するパンフレットを公開しております。
「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォンから ご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。
マイナポータルを使って以下のことができます
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の電子データの受け取り
・国民年金保険料学生納付特例等の電子申請
ほかにも
・ ご自身の年金記録の確認
・ 将来の年金見込額の試算
・ 「ねんきん定期便」や各種通知書の確認 など
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/n_net.files/mottobenri.pdf
公的年金制度をわかりやすく学べるアニメーション動画を掲載(日本年金機構)(2023/5/24更新)
日本年金機構は、公的年金制度をわかりやすく学べるアニメーション動画を掲載しました。
全3話のアニメーション動画で、20歳前の方をはじめとした若い方々に知っていただきたい内容となっています。
以下の内容で構成されております。
第1話 老後の暮らしに安心を
5分11秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
第2話 若い皆さんのもしもの時に安心を
4分54秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
第3話 初めての国民年金
6分09秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/koutekinenkin.html
国民年金法施行規則の一部を改正する省令が公布されました(2023/3/11更新)
厚生労働省より、国民年金法第110条の規定に基づき、国民年金法施行規則の 一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第18号。以下「改正省令」という。)が令和5年3月6日付けで公布及び施行されました。(年管発0306第1号)
失業又は事業の休廃止を理由とする国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予の申請については、国民年金法施行規則第77条第2項第4号ロ等の規定に基づき、離職票など失業等を確認することができる書類の添付を申請の都度求められております。
これについて申請者の負担軽減を図る観点から、過去に同一の離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、当該離職票等の添付を不要とするよう所要の改正が行われました。
〇改正省令の概要
失業等を理由とする免除等の申請については、過去に当該失業等に係る離職票等を添付し免除等を申請(令和元年10月30日以降に行ったものに限る。)を行っていた場合は、 当該離職票等の添付を不要とすること。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230308T0010.pdf
国民年金保険料のスマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済について(2023/2/12更新)
日本年金機構は、国民年金保険料のスマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済についての案内を掲載しております。
国民年金保険料は、令和5年2月20日(月曜)から新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになります。
スマホ決済は、対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールした上、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。
令和5年2月20日(月曜)のサービス開始時点における対象決済アプリは以下のとおりです。(五十音順)
・auPAY
・d払い
・PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)
・PayPay
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/smartphone.html