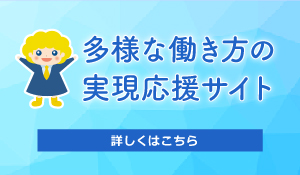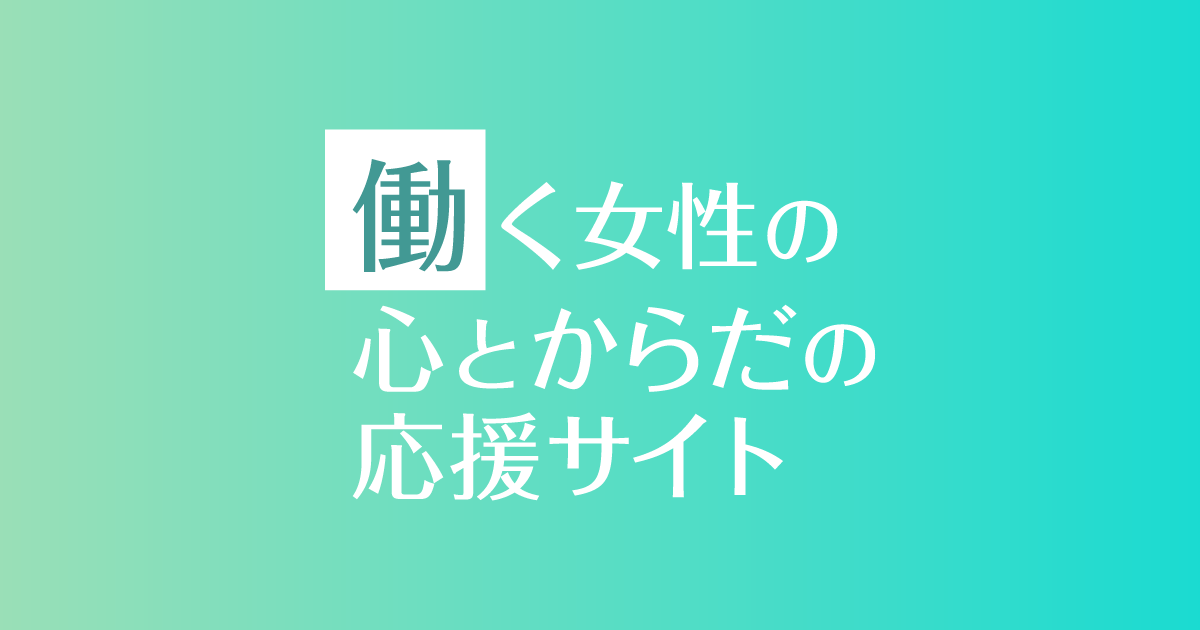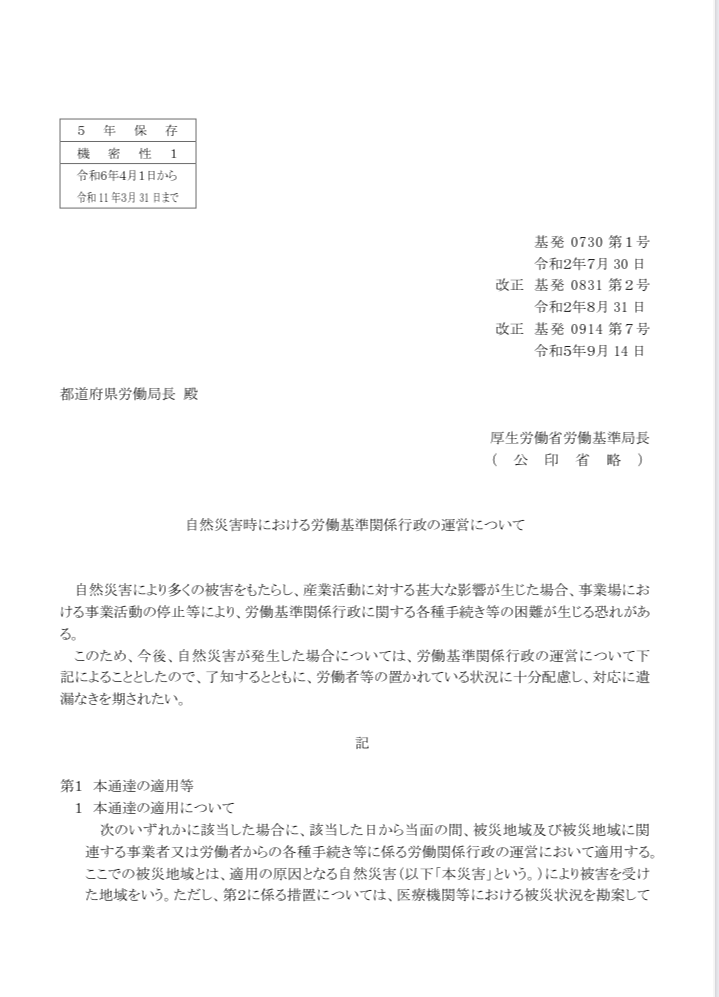労働基準法関係法制研究会(第12回)の資料を公開(2024/9/9更新)
厚生労働省は、労働基準法関係法制研究会(第12回)の資料を公開しております。
資料では、労働基準法上の「労働者」、「事業」及び労使コミュニケーションについて、問題の所在、前回(第8回)の議論および今後の議論・検討の進め方について整理されています。
本日は、労働基準法上の「労働者」について、資料より一部抜粋してご紹介します。
「労働基準法上の「労働者」」について
(問題の所在)
◆労働基準法第9条の労働者の定義について
労働基準法第9条に定める「労働者」の定義自体について、どのように考えるか。
◆昭和60年労働基準法研究会報告等について
① 昭和60年判断基準をどのように扱うべきか、
② プラットフォームワーカーなど個別の職種に関するより具体化した判断基準を作成することが可能かどうかについて、裁判例などを通じて 、国際動向も踏まえながら、検討する必要があるのではないか。そのうえで、契約関係や役務の提供の実態を踏まえ、労働基準法の「労働者」に当たらないプラットフォームワーカーであっても、労働基準関係法令などにおける特別の取扱いの必要性についてどう考えるか。
(今後の議論・検討の進め方)
労働基準法の「労働者」の判断基準(昭和60年労働基準法研究会報告)等について 今後の議論・検討をどのように進めていくべきか。
(前回の議論)
・昭和60年の研究会報告自体を所与の前提として議論をするというよりは、もう一度きちんと専門的な検討をして、労働者概念自体をどう考えるかということを議論していくべき。裁判例分析をしつつ、それに対して学説がどのような反応をしているのか、そこに内在する理論的な問題点も見ていく必要がある。諸外国の実態や法令、裁判例も見つつ、今後出てくる日本の実態を踏まえて、複眼的に分析していくことが必要。
・プラットフォームワーカーについてはEUの動きもあり、来年のILO総会の議題にもなっている。プラットフォームワーカーも含めて労働者性をどう考えるかについて、拙速に議論するのではなく、専門的分析を踏まえて検討をするべき。
・フリーランス法ができ、フリーランス一般について、労災保険の特別加入が可能になった。諸外国では、プラットフォーマーに一定程度保険料を拠出させるというような議論もなされている。必要な対応については、早急に議論するということが必要。
・プラットフォームワーカーやフリーランスなど労働者に当たらない場合にも、一定の社会的保護を及ぼすということが重要だということが各国で議論されている。労働者ではない人に対して、健康確保や所得、報酬の保障等の社会的保護を及ぼす場合、そのことが労働者概念にどう影響するか、しないのか、これについても議論されている。労働者概念の中身をどのように実態の変化に合わせて変えていくかということと同時に、併せて法制度の在り方としてどういう仕組みにするかということを、両方考えないといけない。
家事使用人について
(問題の所在)
家事使用人については、労働基準法制定当初からの状況変化や、家事使用人の働き方の変化を踏まえ、労働基準法を適用する方向で具体的施策を検討すべきではないか。
検討に当たっては、私家庭に労働基準法上の使用者としての義務や災害補償責任をどこまで負わせることができるか、また、労働基準法の労働者の定義を引用している関係法令の適用をどうするか、検討が必要ではないか。
(前回の議論)
・家事使用人の位置付けが時代を経て変わってきたということを踏まえて、基本的には労働基準法を適用するとなった際に、使用者責任や災害補償についても、一定の責任を負うべき。
・これまで家事使用人でない労働者を私家庭が使用していた場合に私家庭が負う労働基準法上の責任を、家事使用人を使用する私家庭も 同じように負ってくださいねという議論。今まで特別扱いしていたものを通常の扱いにするという文脈での議論。
・労働基準法を私家庭に適用することにより、労働基準法による国家的監督や規制が私家庭に及び、使用者としての責任を負わせることに懸念と疑問を感じる。
・解雇の問題については労働契約法の問題として受けるなど、問題ごとにどう受けるのがベストなのかという話かと思う。労働基準法を適用するのか、別の法制度を用意するのかと、その両方を見ながら議論というのはあり得るかとは思う。
詳細は、以下よりご確認ください。
ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)に関するQ&Aを公表(2024/9/2更新)
厚生労働省は、ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)に関するQ&Aを公表しました。
令和5年の通常国会において成立した「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」において、ゲノム情報による不当な差別等への適切な対応の確保に関する条項が盛り込まれたこと等をふまえ、労働分野における不当な差別を防止するための対応として、Q&Aをとりまとめました。
Q&Aの内容は、以下の内容について掲載されております。
問1:採用選考時に応募者の遺伝情報の提出を求めても問題ないのでしょうか。
問2:採用後、ゲノム情報を取得して提出するよう(又はゲノム情報を取得したと会社で話したところ、ゲノム情報を提出するよう)、会社から求められました。求めに応じる必要はあるのでしょうか。
問3:採用後、会社からゲノム情報の提出を求められ提出したところ、解雇されました。ゲノム情報を基に解雇することは問題ではないのでしょうか。
問4:採用後、会社からゲノム情報の提出を求められ提出したところ、異動を命じられました。ゲノム情報を基に配置転換を命じることは問題ではないのでしょうか。
問5:採用後、会社からゲノム情報の提出を求められ提出したところ、昇格・昇給が止まりました。ゲノム情報を基に昇格・昇給に関する不利益な取扱いをすることは問題ではないのでしょうか。
問6:配置転換や解雇などの不利益取扱いを受けた場合には、どこに相談すればいいのでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
賃金のデジタル払い 労使協定例、リーフレットのご紹介(2024/8/21更新)
厚生労働省は、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について、以下の資料等を新たに公開しております。
・賃金の支払方法に関する労使協定の様式例
・リーフレット「【労働者向け】賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き」
・リーフレット(多言語翻訳版)「Leaflets "Necessary procedures for receiving your wage by `digital payment’"(Multilingual Translation)」
・リーフレット「【使用者向け】賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き」
・資金移動業者向けQ&A(令和6年8月9日更新)
雇用主向けのリーフレットでは、賃金のデジタル払いの導入にあたっての手続きの流れやポイントなどが記載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
自己診断機能をリニューアル(働き方・休み方改善ポータルサイト)(2024/8/15更新)
働き方・休み方改善ポータルサイトでは、自己診断機能をリニューアルしました。
働き方・休み方改革の取組を進めるうえでは、まずは自社の実態を確認することが不可欠です。本ツールを活用することにより、自社で優先的に取り組むべき課題を確認することが可能となります。
なお、指標には企業向けと社員向けの2種類があります。目的に応じてご活用ください。
◆企業向け
企業向け指標は、主に企業の人事労務担当者が自社における働き方・休み方の現状・課題を把握し、自社で取り組むべき施策を検討するために活用いただくことを想定しています。
指標には5つの観点が設定されており、「労働時間の長さ」「休暇の取得状況」「メリハリのある働き方・休み方」「柔軟な働き方」「時間制約のある社員の活躍」について、実態データ等に基づいて、チェックを行います。
◆社員向け
社員向け指標は、企業が働き方改革を進める時に、管理職や一般社員の働き方の実態など、現場の課題を把握して今後の施策・取組を検討する際に活用いただくことを想定しています。
企業向け指標と異なる点は、自社の社員にチェックリスト項目に回答してもらうところにあります(企業向けは主に人事労務担当者が自社の状況に基づいて回答します)。その過程で、社員にも「働き方・休み方改革についてこんな取り組み方があるが、自社ではやっていない。これならうちでもやれそうだ。」と気付いてもらうという目的もあります。
詳細は、以下よりご確認ください。
配偶者手当と賃金制度の見直しセミナーの動画を公開(厚労省)(2024/7/14更新)
厚生労働省は、配偶者手当と賃金制度の見直しセミナーの動画を3本公開しております。
民間企業における配偶者手当の見直し(年収の壁)や、職務給の導入・メリットについて解説されたものです。
以下の動画が掲載されております。
1. 配偶者手当の見直し~熾烈な人材獲得競争に向けて①~(23:09)
1.1 背景
1.2 配偶者手当の見直しの手順
1.3 年収の壁
1.4 年収の壁・支援強化パッケージ
1.5 多様な人材が活躍できる組織で、人手不足時代を乗り越える
2. 個々の企業の実態に応じた職務給の導入メリット~熾烈な人材獲得競争に向けて②~(25:48)
2.1 人材獲得競争の中で、何をすべきか
2.2 背景(年功序列制→職能給→職務給)
2.3 職務給(ジョブ型人事)の導入メリット
2.4 これからの日本
3. 職務給の導入手順(21:15)
3.1 全体観
3.2 職務分析
3.3 関係者と話してみよう
コラム
動画は、以下よりご確認ください。
労働基準法における「労働者」について、これまでの議論を踏まえた考え方(案)について(2024/7/10更新)
厚生労働省は、令和6年6月26日に記載された「労働基準関係法制研究会 第8回資料」を公開しております。
この回では、労働基準関係法制についてのヒアリングが行われ、全国社会保険労務士会連合会が提出資料も掲載されております。
資料では、労働基準法に関する様々な論点について、社労士としての視点からの意見が述べらております。
この中から、労働基準法の「労働者」に関する部分について、資料から抜粋して、ご紹介します。
3.労働基準法の「労働者」について
・労働者性の判断は多様な判断基準を総合的に評価する必要があることから、実務的には非常に判断が難しく、予見可能性が乏しい。
・近年、柔軟な働き方が認められる労働者や自ら積極的にフリーランスでの契約を望む者が増加する一方、業種によっては偽装フリーランスが指摘されるケースも増加しており、労働者性の線引きは非常に曖昧なものとなっている。
・複数の仕事を並行して行うキャリアを指向する労働者が増加していることから、個人事業者に対する保護は重要な問題である。対策としては、労災保険特別加入制度の活用などが考えられるであろう。
・既存の特定加入団体等機能に加えて、加入を希望するフリーランス自身が行政機関で加入手続できる仕組みを構築することがより働き方に中立な制度となり得るのではないか。
また、厚生労働省の資料では、労働基準法における「労働者」について、これまでの議論を踏まえた考え方(案)として以下のような内容が記載されております。
1 労働基準法第9条の労働者の定義について
(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)
労働基準法上の「労働者」の定義は、法制定時から変わるものではなく、今日の課題は、もっぱら個別の働く人が「労働者」に該当するかどうかの当てはめとなっている。これは国際的にも同様で、欧米においても「労働者」の基本的な定義を維持しつつ、個別のプラットフォームワーカー等が「労働者」の定義に当てはまるかどうかの判断を明確化しようとしている。
こうしたことも踏まえ、労働基準法第9条に定める「労働者」の定義自体について、どのように考えるか。
(筆者注)
※プラットフォームワーカーとは、デジタルプラットフォームを介して、発注者に対して労務の提供や労働の成果物の提供を行う働き手のことをいいます。
2 労働基準法の「労働者」の判断基準(昭和60年労働基準法研究会報告)等について
昭和60年の研究会による判断基準は、職種や雇用形態にかかわらず、労働者であると判断するために必要な要件を、抽象的に一般化して示されたものである。
また、これまでも個別の職種等に関連して、判断基準への当てはめが難しい事情が生じた場合には、当てはめについての具体的考え方を通達の形で示してきている。(例:建設業手間請け労働者に係る判断基準)
他方、欧米でのプラットフォームワーカーの労働者性の検討においては、「経済的従属性」を考慮しているが、昭和60年の判断基準には含まれていない。「経済的従属性」をどのように扱うかは、労働基準法が刑罰法規であることから、罪刑法定主義の観点で適当かどうかも踏まえ、丁寧に検討する必要がある。
また、プラットフォームワーカーについては、プラットフォームを介するという契約関係の特徴があり、役務の提供の実態を踏まえた検討が求められる。
これらのことを踏まえ、
①昭和60年判断基準に盛りこむことが適当な要素があるか、
②プラットフォームワーカーなど個別の職種に関するより具体化した判断基準を作成することが可能かどうかについて、裁判例などを通じて、国際動向も踏まえながら、検討する必要があるのではないか。そのうえで、契約関係や役務の提供の実態を踏まえ、労働基準法の「労働者」に当たらないプラットフォームワーカーであっても、労働基準関係法令などにおける特別の取扱いの必要性についてどう考えるか。
(筆者注)
経済的従属性とは以下のようなものを言います。
・使⽤者との関係で、交渉⼒が不均衡・⾮対称であり、経済的劣 位にある関係。
・特定の契約の相⼿⽅に対し、収⼊の全部ないし多くを依存して いる関係。
3 家事使用人について
家事使用人については、労働基準法制定当初からの状況変化や、家事使用人の働き方の変化を踏まえ、労働基準法を適用する方向で具体的施策を検討すべきではないか。
検討に当たっては、私家庭に労働基準法上の使用者義務や災害補償責任をどこまで負わせることができるか、また、労働基準 法の労働者の定義を引用している関係法令の適用をどうするか、検討が必要ではないか。
詳細は、以下よりご確認ください。
多様な働き方の実現応援サイトメールマガジンのご紹介(2024/6/25更新)
厚生労働省の「多様な働き方の実現応援サイト」では、パート・アルバイト・契約社員等の待遇の改善と、職務・勤務地・時間を限定した多様な正社員についての情報を掲載しています。
また、登録された企業の人事担当者様向けに、各種セミナーや委託事業の案内など役立つ情報をお届けするメールマガジンも配信しています。
今回、多様な働き方の実現応援サイトメールマガジン令和6年6月号(配信日:令和6年6月3日)がホームページに掲載されております。
6月号は、「年収の壁」対応のキャリアアップ助成金の解説動画の紹介や不妊治療と仕事の両立に係るマニュアル等の作成についての記事などが掲載されております。
ご興味のある方は、メールマガジンの登録をされ、購読されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
「多様な正社員」制度導入支援セミナーの資料・動画を公開(多様な働き方の実現応援サイト)(2024/5/28更新)
厚生労働省の多様な働き方の実現応援サイトでは、令和6年2月9日開催された 「多様な正社員」制度導入支援セミナーの資料・動画を掲載しております。
多様な人材活用のヒントとなるよう、「多様な働き方」に関するトレンドや、勤務地や職務内容、勤務時間などを限定した「多様な正社員」制度のポイント、実際に「多様な働き方」を実践されている先進事例などを紹介しています。
以下の内容で構成されております。
・基調講演(33:49)
「多様な正社員」制度の導入に向けて ―タイプ別人事制度―
1.多様な正社員制度の導入状況
2.多様な正社員制度の課題と取り組み
3. 職務基軸の人事制度:「人材マネジメントの方針」
4.まとめ
・事例紹介
企業事例のご紹介①(13:25)
企業事例のご紹介②(33:41)
・パネルディスカッション(42:41)
詳細は、以下よりご確認ください。
「我が社の働き方改革(企業の取り組み事例動画)」(働き方改革特設サイト)のご紹介(2024/5/13更新)
働き方改革 特設サイトでは、お役立ちコンテンツの動画として「我が社の働き方改革(企業の取り組み事例動画)」公開しております。
働き方改革に取り組む企業に、取り組みのきっかけや導入による効果などを聞いたもので、5月13日現在10社の事例が紹介されております。
以下の動画が掲載されております。
・小規模企業での職務分析・職務評価
・小売店での労務管理
・システムを活用し業務の効率化
・人材不足解消に向けた職場環境の改善
・情報共有システムで業務の効率化
・ダイバーシティで魅力的な商品を
・心と体のベストコンディションを目指して
・健康経営で変わる労働環境
・IT化で実現する働き方の選択肢
・同一労働同一賃金に取り組み
6~8分程度の動画でコンパクトにまとまっています。
ご興味のある方は視聴されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
「企業の配偶者手当の在り方の検討」についてのWEBサイトを更新(2024/4/28更新)
厚生労働省は、「企業の配偶者手当の在り方の検討」についてのWEBサイトを更新しました。
今回、「支給状況が減少傾向にある」ことがわかるグラフの追加等の更新が行われました。
これに伴い、以下のリーフレットも令和6年4月改定版に更新されております。
・「配偶者手当」の在り方の検討に向けて(リーフレット令和6年4月改訂版)
民間企業における「配偶者手当」の支給状況、就業調整の実態とその影響について触れた上で、「配偶者手当」の見直しを実施・検討した企業の例を紹介し、「配偶者手当」の円滑な見直しに向けた留意点を明示し、配偶者手当見直し検討のフローチャートの紹介がされており、簡潔にまとめられてた資料です。
・「配偶者手当」の在り方の検討に向けて(実務資料編令和6年4月改訂版)
先程の資料をもっと掘り下げた形で、実際に、配偶者手当の見直しに向けて実務を進める上での具体的な進め方等についての説明がされております。
Ⅰ.配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項等
Ⅱ.見直しを行う場合の留意点および企業事例等
労働契約法の条文やそれに関連する判例等も紹介されております。
配偶者手当について、見直しを検討されている企業の方は、参考になる資料だと思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
職種限定合意がある者の配転命令に関する最高裁判決(令和6年4月26日 第二小法廷判決)について(2024/4/27更新)
昨日、職種限定合意があった技術職の方の配転命令に関する最高裁判決が出ました。本日は、この判決についてご紹介します。
〇事案の概要
上告人(仮にXさんとします)は、被上告人(Y社とします)との間の労働契約に基づき、Y社が指定管理者として管理を行う施設において、福祉用具の改造・製作、技術の開発を担当する技術職として平成13年3月から勤務してきた。XとY社との間には、Y社がXを福祉用具の改造・製作、技術の開発を担当する技術職として就労させるとの職種限定合意があった。
Y社は、Xに対し、その同意を得ることなく、平成31年4月1日付けで総務課の施設管理担当への配置転換命令(以下「本件配転命令」という。)をした。
本件は、Xが、本件配転命令がXとY社との間の職種限定合意に反するなどと主張して、Y社に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求等をした事案である。
〇原審の判決
大阪高裁は、本件配転命令をもって権利の濫用ということはできず、本件配転命令が違法ということはできないと判断した。
〇最高裁の判断(下線は一部筆者加筆)
原審の上記判断は是認することができない。(損害賠償に係る部分は破棄、本件配転命令について不法行為を構成すると認めるに足りる事情の有無や、被上告人が上告人の配置転換に関し上告人に対して負う雇用契約上の債務の内容及びその不履行の有無等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする)
(理由)
労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨
の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該
合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。上記事実関係等によれ
ば、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技
術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に
対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそ
もそも有していなかったものというほかない。
そうすると、被上告人が上告人に対してその同意を得ることなくした本件配転命
令につき、被上告人が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として、そ
の濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法
令の違反がある。
〇まとめ
日本の裁判所は、使用者による解雇を厳格に制限する代わりに、配転を含む労働力の活用については、使用者の裁量を広く認めています。ただし、①職場や職種を最初から限定して採用されている場合は、本人の同意なく一方的に配転を命じることはできず、また、②配転命令が権利濫用となる場合は、無効となる場合があります。
本判決は、職種限定合意がある場合の原則通り、個別的同意なしに職種限定合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと判断しました。
今回の判決により、職種限定合意がある場合、その職種がなくなってしまうような場合は、配置転換について本人の同意が得られないと、配置転換以外に解雇を回避する他の手段がなければ、退職勧奨をして、それにも応じてもらえないなら、最終的には解雇するしかなくなってしますね。
個人的には、職種限定合意があったとしても、解雇を回避するための配置転換は、理由が妥当であって、権利の濫用等に当たらないのであれば合意がなくても認めてもよいと思いますが・・・。
判決分は以下よりご確認ください。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/092928_hanrei.pdf
「働き方改革取組事例集2023」、「「働き方改革推進支援センター」支援事例2023」のご紹介(2024/4/12更新)
厚生労働省の働き方改革 特設サイトでは、お役立ちコンテンツ 関連資料ダウンロード&リンクに「働き方改革取組事例集2023」、「「働き方改革推進支援センター」支援事例2023」 を追加しています。
〇「働き方改革取組事例集2023」
時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金、年次有給休暇の時季指定について簡単な解説がされており、その後に、12社の取組事例が紹介されております。
取組事例では、代表者の想い、取組事例の紹介、従業員の声、専門家のコメント、CASE STUDYが掲載されております。
〇「「働き方改革推進支援センター」支援事例2023」
「働き方改革推進支援センター」 は、中小企業・小規模事業者の働き方改革の取り組みを支援することを目的として、全国47都道府県に設置されています。
センターでは、労務管理の専門家が無料で、時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金、その他働き方改革を広く支援する取り組みに関する個別相談やコンサルティングを実施しています。
以下の事例が紹介されております。
・労働時間・休暇のサポート事例:5社
・同一労働同一賃金のサポート事例:6社
・効率化・改善のサポート事例:3社
・労務管理・就業規則の作成や見直しのサポート事例:7社
・助成金活用のサポート事例:2社
詳細は、以下よりご確認ください。

「パートタイム・有期雇用労働法 解説動画」をリニューアル(多様な働き方の実現応援サイト)(2024/3/3更新)
厚生労働省の多様な働き方の実現応援サイトでは、「パートタイム・有期雇用労働法 解説動画」をリニューアルしました。
以下の動画が掲載されております。
◆全編
パートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について
パートタイム・有期雇用労働法の内容を網羅的に把握できる動画です。(47分31秒)
◆チャプター別
・パートタイム・有期雇用労働法の目的とその内容について
「パートタイム・有期雇用労働法」の目的とその内容についてお伝えします。(2分54秒)
・不合理な待遇差をなくすための規定について
「不合理な待遇差」とは何を指すのか確認してみましょう。(8分49秒)
・不合理な待遇差をなくすための規定について~同一労働同一賃金ガイドライン~
「不合理な待遇差」について、基本給、賞与、手当、福利厚生などの各項目ごとの具体例を紹介しています。(11分04秒)
・参考となる判例
どの待遇が不合理か否かについて判断された実際の裁判例を紹介します。(6分48秒)
・労働者に対する待遇に関する説明義務について
具体的にどのような説明が必要なのか確認してみましょう。(5分41秒)
・パートタイム・有期雇用労働法に対応するための取組手順について
正社員とパート・アルバイト・契約社員等との間にある待遇差について見直しの方法を紹介しております。(7分57秒)
・裁判外紛争解決手続『行政ADR』等について
職場で事業主と労働者の間にトラブルが生じた場合に利用できる無料の解決制度を紹介します。(1分18秒)
・パートタイム・有期雇用労働法に対応するための事業主の皆さまへの支援について
事業主への制度導入支援窓口である「働き方改革推進支援センター」を紹介します。(3分00秒)
詳細は、以下よりご確認ください。
1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等について本社一括届出が可能となりました(2024/2/22更新)
1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等については、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、令和6年2月23日から、一定の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届等と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労 働基準監督署に届け出ることが可能となりました。
新たに本社一括届出の対象となった手続は下記6手続です。
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告
本件に関するリーフレットも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001211058.pdf
「家事使用人の雇用ガイドライン」のご紹介(2024/2/17更新)
厚生労働省は、「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定し、令和6年2月8日より公表しております。
個人宅に出向き、ご家庭と直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法が適用除外とされています。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査では、業務内容や就業時間などが不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生する、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないなどの問題が一部にあることが分かりました。
こうした実態を踏まえ、厚生労働省の委託事業において、有識者参画のもと議論を行い、本ガイドラインの策定が行われました。
ガイドラインには、以下の内容が掲載されております。
1 基本的な考え方
①ガイドラインの目的
② ガイドラインの対象者
③家事使用人に適用される労働関係等法令
2 家事使用人を雇用する際の留意事項
①労働契約の条件を明確にしましょう
②労働契約の条件を適正にしましょう
③就業環境を整えましょう
④労働契約の更新・終了の際には適切に対応しましょう
⑤保険の加入やケガなどの発生状況について確認しましょう
3 家政婦(夫)紹介所の留意事項
①募集段階(契約前段階)
②契約段階
③その他
また、家事使用人(家政婦・家政夫)についての特集ページでは、ガイドラインのほかに、「労働契約書のひな型」も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
社会人として働き始めてからの労働法、「働くこと」と「労働法」、『はたらく』へのトビラのご紹介(2024/1/7更新)
労働条件に関する総合サイト「確かめよう労働条件」では、社会人として働き始めてからの労働法、「働くこと」と「労働法」、『はたらく』へのトビラ、を更新しております。
〇社会人として働き始めてからの労働法
社会人対象の労働教育(セミナー)を企画しようとする方にお役立ていただけるよう、実際に社会に出てから直面する可能性のある場面を想定して、以下の8つの学習テーマが設定されています。
①給与明細から労働条件について考える
②労働契約の締結と労働条件について考える
③様々な働き方
④仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
⑤労働時間
⑥ハラスメント
⑦会社を辞める時、辞めさせられる時のルール
⑧困った時の相談先
〇「働くこと」と「労働法」
~大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き~
労使間トラブルが多く発生している状況に鑑み、学生の皆さんが在学中の様々な機会に労働法や制度に関する知識を習得し、未然に労使間トラブルを回避できるよう、教職員の方々が学生を指導する際の手引きとして作成されています。
モデル授業案として、以下の内容が掲載されております。
⓪「働くこと」を考えよう
①アルバイトを始める前の注意点
②働き始めておかしいな、と気付いたら
③インターンシップを行うにあたって
④就職活動の際の留意点
⑤契約と労働条件
⑥働きすぎと心身の健康
⑦多様な働き方
⑧働き続けやすさとは
〇『はたらく』へのトビラ
教育現場での労働法教育を担う教員の方向けに、以下の「ワークルール20のモデル授業案」が掲載されております。
・イケテル働き方って何?
・契約を結ぶってどういうこと?
・契約の中身で注意することは?
・働くときの契約に必要なこととは?
・労働組合って何?
・困った時は、誰にどう相談しますか?
・働く環境を適切に選ぶには?
・安心を支える制度とは?
・働く上での幸せ・不幸せって何?
・働くトラブルを回避するには?
・約束しなくて大丈夫?
・救う法律は何?
・それってパワハラじゃない?
・こんなこと聞かれたらどうする?
・誰もが一緒に働ける社会とは?
・「働きやすい」ってどういうこと?
・男女の「働く」ってどこまで平等ですか?
・なんでこういう法律があるの?
・最低賃金って何?
・生命を大切にする働き方は?
詳細は、以下よりご確認ください。
「働く女性の心とからだの応援サイト」のご紹介(2023/11/7更新)
女性が働き続けるためには、職場全体で、女性特有の健康課題を認識し、サポート体制を整えることが必要です。「働く女性の心とからだの応援サイト」では、そのために必要な情報を掲載しています。
以下のような活用方法が紹介されております。
・女性の健康支援の取組方を知りたい→ 取り組みのポイント
・個別の健康課題について支援情報を知りたい→ 健康課題別 職場のサポート
・他社の取組事例を知りたい→ 企業取組事例
・仕事と健康に関する様々な課題と解決策を知りたい→ 専門家コラム、Q&A
この度、「不妊治療と仕事との両立支援担当者等向け研修会」の開催について(厚生労働省)の案内が掲載されました。
企業において、「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくり」のための具体的なノウハウなどを内容とした、オンラインの研修会です。
配信期間:2023年9月25日(月)~ 2024年3月15日(金)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.funin-ryoritsu.jp/
「動画で学ぼう!労働条件」を更新(2023/10/28更新)
労働条件に関する総合サイト「確かめよう労働条件」では、「動画で学ぼう!労働条件」を更新しました。
このセミナーでは、近い将来に社会人として働く、あるいは在学中にアルバイトとして働く、学生・生徒の皆さんに、労働関係法令の基礎知識をわかりやすく教え、安心して働けるよう、次のような知識を身につけていただくことを目的として開催されています。
① 労働条件に問題がありそうな就職先を避け適正な労働条件の会社を選べる眼を養う。
② 労働条件に関するトラブルに巻き込まれないようにする。
③ 遭遇した労働トラブルを解決できる道筋を知る。
今年度掲載された動画は以下の通りです。
① 労働契約締結の際の労働条件の明示(3:57)
労働契約を締結する際に明示される労働条件の内容等について、分かりやすく解説しています。
② 賃金明細と残業代(3:40)
賃金明細書の記載内容と労働基準法で定められた、働く時間と残業代について、分かりやすく解説しています。
③ 年次有給休暇(年休)(4:00)
労働基準法で定められた「年次有給休暇」の仕組みについて、分かりやすく解説しています。
④ 賃金(3:49)
労働基準法で定められた「賃金」について、分かりやすく解説しています。
ご興味のある方は視聴されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
「パンフレット 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」のご紹介②(2023/10/20更新)
厚生労働省は、令和6年4月から改正される労働条件明示のルールに関するリーフレット等が新たに公開されております。
本日は、昨日に引き続き「パンフレット 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」です。
パンフレットは、全体で24ページで、以下の内容で構成されております。
〇巻頭
・はじめに(改正事項とその対象者)
・用語の解説など
〇第1章 就業場所・業務の変更の範囲
〇第2章 更新上限に関する事項
〇第3章 無期転換に関する事項
〇第4章 その他の留意事項
各項目について、注意すべきポイントについて解説されており、労働条件通知書の記載例も掲載されております。
パンフレットの中から、私の独断で重要だと思われる記載について紹介させていただきます。(下線は筆者加筆)
今回は、「第3章 無期転換に関する事項」、「第4章 その他の留意事項」をご紹介します。
〇第3章 無期転換に関する事項
1.有期契約労働者に対する無期転換申込機会の書面明示
・「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要になります。
・初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、上記の明示が必要になります。
2.(1)無期転換後の労働条件の書面明示
・「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものです。
・明示方法は、事項ごとに明示するほか、有期労働契約の労働条件と無期転換後の労働条件との変更の有無、変更がある場合はその内容を明示する方法でも差し支えありません。
・2024年(令和6年)4月以降は、無期転換後の労働条件について、①無期転換申込権が生じる契約更新時と、②無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明示する必要があります。
2.( 2 )均衡を考慮した事項の説明に努めること
・「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、対象となる労働者に無期転換後の労働条件に関する定めをするに当たって、労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じ、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)との均衡を考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について説明するよう努めることになります。
・この説明は文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本ですが、説明の方法は特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合は当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えありません。また、説明会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によっても差し支えありません。
・労働契約法第3条第2項が規定する「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」との考え方は、すべての労働契約に適用され、無期転換者の労働契約も含まれます。均衡を考慮した事項について、労働者の理解を深めるため、労働者に十分な説明をするよう努めてください。
・無期転換した短時間勤務労働者(いわゆる無期雇用のパートタイム労働者)については、引き続きパート・有期労働法の対象になることにも留意するようにしましょう。
・短時間正社員については、処遇が正社員としての実態を伴っていない場合には、パート・有期労働法の適用があり、均衡・均等待遇が求められます。
◆対象となる労働者への説明例
具体的な説明例(正社員用と、無期転換後用の賃金テーブルの双方を提示しつつ)
Aさんは無期転換後も以前と変わらず、レジや接客が主な業務で、店舗の運営に責任は負いません。一方、正社員の人は、レジや接客、発注に加え、店舗運営に責任があり、クレーム処理などの業務も行います。こうした【業務の内容と責任の程度】の違いを考慮し、Aさんの給与水準を定めています。
◆無期転換に関する明示のタイミングと記載例
記載例
・無期転換申込機会:「本契約期間中に無期労働契約締結の申込みをした時は、本契
約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。」
・無期転換後の労働条件:「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」又は
「無期転換後は、労働時間を○○、賃金を○○に変更する。」
〇第4章 その他の留意事項
1.就業規則について
・常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること等によって、働く方に周知しなければなりません。
具体的には、就業規則を備え付けている場所等を労働条件通知書や社内メールなどで働く方に示すことなどにより、就業規則を必要なときに容易に確認できるようにする必要があります。
・無期転換申込みに関する事項を就業規則に定める場合は、当該事業所において雇用する有期雇用労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めることとされています
3.無期転換ルールにおける通算契約期間のリセット(クーリング)
・契約更新上限を設けた上でクーリング期間を設定し、クーリング期間経過後に再雇用することを約束して雇止めを行うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図る」という労働契約法第18条の趣旨に照らし、望ましいものではありません。
資料は、以下よりご確認ください。
いかがだったでしょうか?本パンフレットは、労働条件通知書の記載例を見比べながら確認すると理解しやすいと思います。
来年4月までまだ時間がありますが、有期雇用者が多いサービス業や小売業の方は、早めの対応が必要かと思います。
情報がアップデートされましたら、こちらのブログでご紹介させていただきます。
「パンフレット 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」のご紹介①(2023/10/19更新)
厚生労働省は、令和6年4月から改正される労働条件明示のルールに関するリーフレット等が新たに公開されております。
本日は、「パンフレット 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」です。
パンフレットは、全体で24ページで、以下の内容で構成されております。
〇巻頭
・はじめに(改正事項とその対象者)
・用語の解説など
〇第1章 就業場所・業務の変更の範囲
〇第2章 更新上限に関する事項
〇第3章 無期転換に関する事項
〇第4章 その他の留意事項
各項目について、注意すべきポイントについて解説されており、労働条件通知書の記載例も掲載されております。
パンフレットの中から、私の独断で重要だと思われる記載について紹介させていただきます。(下線は筆者加筆)
今回は、「第1章 就業場所・業務の変更の範囲」、「第2章 更新上限に関する事項」をご紹介します。
〇第1章 就業場所・業務の変更の範囲
1 .就業場所・業務の変更の範囲の書面明示
・変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年(令和6年)4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者。
・「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。
配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。
・「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。
労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務、いわゆるテレワークを雇入れ直後から行うことが通常想定されている場合は、「雇入れ直後」の就業場所として、また、その労働契約期間中にテレワークを行うことが通常想定される場合は、「変更の範囲」として明示してください。
◆労働条件通知書の記載例
①就業場所・業務に限定がない場合
就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含める必要があります。
(就業場所)
(雇入れ直後)〇〇営業所 (変更の範囲)会社の定める営業所
(雇入れ直後)本店及び労働者の自宅 (変更の範囲)本店及び全ての支店、営業所、労働者の自宅での勤務
(従事すべき業務)
(雇入れ直後)原料の調達に関する業務 (変更の範囲)会社の定める業務
(雇入れ直後)店舗における会計業務 (変更の範囲)全ての業務への配置転換あり
②就業場所・業務の一部に限定がある場合
就業場所や業務の変更範囲が一定の範囲に限定されている場合は、その範囲を明確にしましょう。
(就業場所)
(雇入れ直後)豊橋 (変更の範囲)愛知県内
(従事すべき業務)
(雇入れ直後)商品企画 (変更の範囲)本社における商品又は営業の企画業務、
営業所における営業所長としての業務( ただし、出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務)
③完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)
雇い入れ直後の就業場所・業務から変更がない場合は、その旨を変更の範囲で明確にしましょう。
(就業場所)
(雇入れ直後)旭川センター (変更の範囲)旭川センター
(従事すべき業務)
(雇入れ直後)理美容業務 (変更の範囲)理美容業務
〇第2章 更新上限に関する事項
1 .更新上限の書面明示と更新上限を新設・短縮する場合の説明
・有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要になります。
・以下の場合について、あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要になります。
ⅰ 更新上限を新たに設けようとする場合
ⅱ 更新上限を短縮しようとする場合
・更新上限の新設・短縮の理由をあらかじめ説明する際は、文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本ですが、説明の方法は特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合は当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えありません。また、説明会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によっても差し支えありません。
◆Q&A
Q:最初に有期労働契約を結んだ時から更新上限を設定していますが、その場合
も労働者には説明をした方がよいのでしょうか?
A:最初の契約締結より後に更新上限を新設・短縮する場合に、事前説明が必要
となります。
資料は、以下よりご確認ください。
令和6年4月から改正される労働条件明示のルールに関するリーフレット等のご紹介(労働条件通知書)(2023/10/18更新)
厚生労働省は、令和6年4月から改正される労働条件明示のルールに関するリーフレット等が新たに公開されております。
今回新たに公開された資料は以下の資料となります。
〇各種リーフレット
・リーフレット 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
・パンフレット 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?
〇Q&A
・令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A
〇通達
・労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について
〇参考
・モデル労働条件通知書
以上の資料について、何回かに分けてご紹介させていただきます。
本日は、「モデル労働条件通知書」です。
2023年8月に一度、労働条件通知書のイメージが公開されておりました。
今回、一部追加、修正され公表されております。
以下の部分が変更されております。(下線が変更部分)
〇契約期間
・【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合】
本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをすることにより 、本契約期間の末日の翌日( 年 月 日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無( 無 ・ 有(別紙のとおり)
⇒文言の修正です
〇退職に関する事項
3 創業支援等措置( 有( 歳まで業務委託・社会貢献事業) , 無 )
⇒追記されました
〇その他
・中小企業退職金共済制度
(加入している , 加入していない) (※中小企業の場合)
・企業年金制度( 有(制度名 ) , 無 )
⇒追記されました
・※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。
労働契約法第18条の規定により、有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始するもの)の契約期間が通算5年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、無期転換申込権の発生については、特例的に本通知書の「契約期間」の「有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合」欄に明示したとおりとなります。
⇒文言の修正です
〇欄外
※ 本通知書の交付は、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)第6条に基づく文書の交付を兼ねるものであること。
⇒追記されました
資料は、以下よりご確認ください。
令和6年4月から改正される労働条件明示のルールに関するリーフレット等のご紹介(労働条件明示等に関するQ&A)(2023/10/17更新)
厚生労働省は、令和6年4月から改正される労働条件明示のルールに関するリーフレット等が新たに公開されております。
今回新たに公開された資料は以下の資料となります。
〇各種リーフレット
・リーフレット 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
・パンフレット 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?
〇Q&A
・令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A
〇通達
・労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について
〇参考
・モデル労働条件通知書
以上の資料について、何回かに分けてご紹介させていただきます。
本日は、「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A」の中から、一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
Q:今回の改正を受けて、既に雇用されている労働者に対して、改めて新たな明示ルールに対応した労働条件明示が必要か。
A:既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はない。 新たな明示ルールは、今般の省令・告示改正の施行日である令和6年4月1日以降に締結される労働契約について適用される。
Q:令和6年4月1日を契約の開始日とする契約の締結を3月以前に行う場合、新たな明示ルールに基づく労働条件明示が必要か。
A:労基法第15条の労働条件明示は、労働契約の締結に際し行うものであることから、契約の始期が令和6年4月1日以降であっても、令和6年3月以前に契約の締結を行う場合には、改正前のルールが適用され、新たな明示ルールに基づく明示は不要である。
Q:就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲の明示について、「変更の範囲」とは、当該労働契約の期間中における変更の範囲を指すと解してよいか。
A:就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲とは、当該労働契約の期間中における変更の範囲を意味する。このため、契約が更新された場合にその更新後の契約期間中に命じる可能性がある就業の場所及び業務については、改正労基則において明示が求められるものではない。
Q:有期労働契約の更新回数の上限とは、契約の当初から数えた回数を書くのか、残りの契約更新回数を書くのか。また、通算契約期間の上限についてはどうか。
A:労働者と使用者の認識が一致するような明示となっていれば差し支えない。なお、労働者・使用者間での混乱を避ける観点からは、契約の当初から数えた更新回数又は通算契約期間の上限を明示し、その上で、現在が何回目の契約更新であるか等を併せて示すことが考えられる。
Q:更新上限がない場合にも上限がない旨の明示を必ずしなければならないか。
A:改正労基則では、有期労働契約の更新上限を定めている場合にその内容を明示することが求められており、更新上限がない場合にその旨を明示することは要しない。
Q:無期転換申込権を行使しない旨を表明している有期契約労働者に対しても、無期転換申込み機会の明示を行う必要があるか。
A:明示を行う必要がある。
資料は、以下よりご確認ください。
「自然災害時における労働基準関係行政の運営について」の通達を改正(2023/10/1更新)
厚生労働省は、「自然災害時における労働基準関係行政の運営について」の通達を改正しました。(令和5年9月14日 基発 0914 第7号)
自然災害により多くの被害をもたらし、産業活動に対する甚大な影響が生じた場合、事業場における事業活動の停止等により、労働基準関係行政に関する各種手続き等の困難が生じる恐れがあ るため、このような場合についての、労働基準関係行政の運営について定められたものです。
一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
第3 労災保険給付の請求に係る事務処理について
1 労災保険給付請求書に係る事業主証明及び診療担当者の証明
本災害により、被災労働者の所属事業場等が一時休業した等の理由から、労災保険給付請求書(以下「請求書」という。)の事業主証明を受けることが困難な場合には、事業主証明がなくとも請求書を受理すること。
また、被災労働者が療養を受けていた医療機関が一時休業した等の理由から、診療担当者の証明が受けられない場合においては、診療担当者の証明がなくとも請求書を受理すること。
なお、この場合、請求書の事業主証明欄の記載事項及び診療担当者の証明欄の記載事項を請求人に記載させ、証明を受けられない事情を付記させること。
第4 労災保険給付の支払に係る事務処理について
本災害により、労災給付の振込先に指定された金融機関や郵便局の通帳・キャッシュカード・ 届出印を紛失した場合でも、各金融機関等において非常時の取り扱いがなされることがあるため、詳細については、金融機関や郵便局の窓口へ相談するよう受給者へ案内すること。
また、労災年金証書を紛失した場合は、労災年金の支給決定を受けた労働基準監督署に「年金証書再交付申請書」を提出することにより再発行を受けることができることについて、受給者へ 案内すること。
第5 労働保険料等の取扱いについて
1 猶予制度の周知等について
事業主等からの申請に基づき、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官は、労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の納付猶予措置等を行うことができる。
被災に伴い労働保険料等に係る相談があった場合は、これらの制度を踏まえ丁寧に対応するほか、これらの制度ついて労働局において被災事業主等へ周知を行うこと。
第6 未払賃金の立替払事業の運営について
2 対象となる範囲
(1) 対象事業主
本災害に伴い、災害救助法第2条の規定に基づき、その適用 の対象とされた地域に本社機能を有する事業場が所在している中小企業事業主であって、本災害による建物の倒壊等の直接的な被害により事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないもの。
(2) 対象労働者
上記(1)の事業主の適用被災地域に所在する事業場において 使用されていた労働者であって、本災害により退職を余儀なくされ、賃金が未払となっているもの。
3 適用被災地域における労働者等の実情を踏まえた対応
(1) 申請に必要な書類の簡略化等
立替払事業に係る申請に際して添付しなければならない書類を対象事業場が被災したことにより入手できない場合等にあっては、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第9条第3項ただし書及び第14条第2項ただし書の規定を踏まえ、地方公共団体が発行する罹災証明書等の申請者側において入手可能な各種資料を最大限活用する等により、申請に当たっての労働者等の負担をできるだけ軽減すること。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230922K0010.pdf
モデル就業規則(令和5年7月版)を公表(2023/7/12更新)
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
また、就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
厚生労働省は、「モデル就業規則」を公表しています。
この度、「モデル就業規則(令和5年7月版)」が公表されました。
令和5年7月の主な改訂事項は、「退職金の支給(54条)」です。
以下のように変更されました。
〇改定前
(退職金の支給)
第54条 勤続 年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続 年未満の者には退職金を支給しない。
〇改定後
(退職金の支給)
第54条 労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。
詳細は、以下よりご確認ください。
職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について(2023/5/26更新)
厚生労働省は、令和5年5月24日に開催された、第357回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会の資料を公開しております。
職業安定法施行規則の一部を改正する省令案についてご紹介します。
〇改正の概要
(1)明示すべき労働条件等の追加について
【職業安定法施行規則第4条の2第3項関係】
労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等において、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(当該更新回数の上限等を含む。)並びに就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を追加する。
(2)有料職業紹介事業における手数料表等の事項についての掲示方法について
【職業安定法施行規則第 24 条の5第4項関係】
有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程を事業所内に掲示する義務があるところ、事業所内の掲示に限らず、インターネット等その他の適切な方法によって情報の提供を行うことができることとする。
〇施行期日等
公 布 日:令和5年6月下旬(予定)
施行期日:令和6年4月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
「職業安定法に基づく労働条件明示等について」(対応案)(2023/4/23更新)
厚生労働省は、令和5年4月21日に開催された「第356回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料を公開しております。
今回、「職業安定法に基づく労働条件明示等について」の資料が掲載されております。
・労働基準法施行規則の改正により、令和6年4月1日から労働契約締結の際の労働条件明示事項が追加
・雇用・労働総合政策パッケージの中で、労働市場の強化・見える化を推進。
以上の背景から、見直しが検討されております。
〇対応案
職業紹介、労働者の募集等において、求職者等に対して明示しなければならない事項について以下を追加
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業の場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
ワークルール動画「Work Rule Rap」(連合)のご紹介(2023/4/22更新)
連合は、ワークルール動画「Work Rule Rap」を公開しました。
「Co.慶応」さんが、重要なワークルールをラップで説明していく動画となっています。
動画の内容は以下の通りです。
1. 働くって?
2. 働くために必要なルール
3. 安心して働くために
4. 働くみんなの労働組合
5. 困ったときの相談窓口
動画の途中にワークルールクイズが出題されます。
例えば、「アルバイトでも法律で守ってもらえるの?」、「学生だから時給700円でいいの?」などです。
視聴時間は、5:28です。
視聴してみましたが、テンポよく進んでいくのであっという間に見終わります。これから、アルバイトを始める学生に向けた内容ですが、新入社員の方が見ても役立つと思います。
動画は、以下よりご確認ください。
2024年4月変更の労働条件明示のルールに関するリーフレットを公開(2023/4/4更新)
2024年4月から労働条件明示のルールが変更されます。
これに関するリーフレットを厚生労働省が作成し公表しております。
変更の主な内容は以下の通りです。
〇労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項の追加
1.就業場所・業務の変更の範囲
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。
2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者に あらかじめ説明することが必要になります。
3.無期転換申込機会
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
4.無期転換後の労働条件
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
また、「無期転換ルール及び労働契約関係の明確化」の特集ページには、リーフレット以外にも、通達、省令・告示も掲載されており、今後、Q&Aも掲載される予定のようです。
参考資料として、モデル労働条件通知書の改正イメージも掲載されております。
労働条件通知書や雇用契約書を労働条件通知書としても使用している場合は、内容の改定が必要となりますので、人事労務担当の方は必ずご確認ください。
「お役立ちリンク集(より働き方改革を進めるためのお役立ちリンク集)」のご紹介(2023/3/12更新)
厚生労働省が運営する「働き方改革 特設サイト」では、お役立ちコンテンツ に「お役立ちリンク集(より働き方改革を進めるためのお役立ちリンク集)」ページを新たに開設しました。
〇相談窓口一覧
よろず支援拠点、産業保健総合支援センター、トラック運転者の長時間労働改善特別相談センターなどの各相談窓口と相談できること等が掲載されております。
〇相談窓口一覧・参考資料
以下の項目について、相談窓口、関連サイト、リーフレット等資料、セミナー・説明動画などについて掲載されております。
・育児・介護休業法について
・男性の育児休業取得促進の取組支援
・仕事と育児・介護との両立支援
・不妊治療と仕事との両立への取組支援
・職場におけるハラスメントの防止措置の取組支援
・良質なテレワークの定着促進
・多様な正社員制度の導入支援
・副業・兼業など多様な働き方の実現に向けた支援
・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定、認定制度
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定、情報公表、認定制度
・厚生労働省の助成金、中小企業庁の施策や補助金の案内
相談窓口一覧・参考資料については、調べたい内容が決まっている方は、それに関連するWEBサイトのリンクが掲載されているので便利だと思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
「事業者・労務管理担当の方のQ&A」を追加(スタートアップ労働条件)(2023/1/4更新)
事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト「スタートアップ労働条件」では、「事業者・労務管理担当の方のQ&A」を公表しております。
今回、Q&Aが追加されました。(一部抜粋してご紹介します。)
〇雇用契約
・面接のとき、残業時間は実際どのくらいですかとよく聞かれます。どの程度答えればよいでしょうか?
〇労働時間・休日・休憩
・時間外労働の上限規制が適用除外とされている「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」(労基法34⑪)の具体的な範囲を教えてください。
・フレックスタイム制の清算期間が3か月まで延長されましたが、時間外労働の上限規制のうち、時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間未満(労基法36⑥2)、複数月平均80時間以内(労基法36⑥3)の要件は、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制に対してはどのように適用されますか?
・働き方改革関連法で、勤務時間インターバル制度が導入されるなど、労働時間設定法も改正されたと聞きました。具体的な改正内容を教えてください。
・働き方改革関連法で、長時間労働者に対する面接指導の対象となる労働者の要件が変わるなど、労働安全衛生法も改正されたと聞きました。具体的な改正内容を教えてください。
〇年次有給休暇
・年次有給休暇を取得した日の賃金について、いくら支払わなければならないという決まりはあるのでしょうか?
・年次有給休暇はいつまで請求を認めなければならないのでしょうか?また、翌年に繰り越された年次有給休暇と当年の年次有給休暇のどちらを先に付与することになるのでしょうか?
・当社では、派遣労働者と在籍出向者を受け入れていますが、年次有給休暇はそれぞれどのように与えることになるのでしょうか?
・当社では、満60歳となった日をもって定年となりますが、ひきつづき満65歳となる日まで、1年間の有期労働契約を更新することにより再雇用しています。また、再雇用に際し、週所定労働日数を5日または4日のどちらかを選択することができます。このような場合に、年次有給休暇はどのように与えるのでしょうか?
その他、「賃金」、「解雇・雇止め」、「パート・有期・派遣」、「就業規則・書類の保存」、「その他」などのQ&Aも新たに追加されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
「確かめよう労働条件」 労働条件に関する疑問に答えるQ&Aを追加(2023/1/2更新)
労働条件に関する総合サイト「確かめよう労働条件」では、労働条件に関する疑問に答えるQ&Aを公開しております。
今回、Q&Aが追加されました。
〇労働時間・休日・休憩
・時間外労働の上限規制が適用除外とされている「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」(労基法36⑪)の具体的な範囲を教えてください。
・フレックスタイム制の清算期間が3か月まで延長されましたが、月45時間・年360時間という時間外労働の限度時間(労基法36④)は、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制に対してはどのように適用されますか。
〇年次有給休暇
・使用者に年休5日付与義務が課せられましたが、どのような点に留意すれば良いのでしょうか?
・使用者が年休取得管理簿を作成・保管することが義務づけられましたが、どのような点に留意すれば良いでしょうか。
・2020年4月1日から、労働基準法115条に定める労基法上の消滅時効が5年(当面3年)に改正されましたが、年次有給休暇権は、いつまで権利行使が可能でしょうか。
〇賃金
・賃金請求権の消滅時効が変わったと聞きました。どのようになったのでしょうか?
・賃金は差し押さえられることができるということですが、差し押さえられると、どうなるのでしょうか?
〇解雇、退職等
・定年(60歳)後の継続雇用で1年契約で更新されていたのですが、2回目の更新で理由もなく更新しないと言われてしまいました。このような扱いが許されるのでしょうか。
〇その他
・働き方改革関連法で、労働安全衛生法も改正されたと聞きました。具体的な改正内容を教えてください。
・働き方改革関連法で、労働時間設定法も改正されたと聞きました。具体的な改正内容を教えてください。
・使用者には、労働者に対して36協定や法令等の周知義務があると聞きました。今まであまり使用者から協定や法令等の説明を聞いたことはありません。使用者は、36協定のほかどのような法令等を周知しなければならないのですか?
詳細は、以下よりご確認ください。
賃金のデジタル払い よくあるご質問への回答(労働者、使用者向け)のご紹介(2022/12/5更新)
先日、賃金のデジタル払いについての特集ページのご紹介をさせていただきました。
本日は、その中から、現在掲載されているQ&Aをいくつかご紹介します。(全部で7つ掲載されておりますが、今回その中から3つのQ&Aを抜粋してご紹介致します。)
〇賃金のデジタル払いは必ず実施しなければならないのでしょうか。引き続き、銀行口座等で受け取ることができなくなるのでしょうか。
⇒賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。
労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。また、使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。
賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。
〇賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きを教えてください。
⇒事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。
その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になります。
〇賃金のデジタル払いを選択するために留意すべき事項をわかりやすく教えてください。
⇒労働者は、資金移動業者口座は「預金」をするためではなく、支払や送金に用いるためであることを理解の上、支払等に使う見込みの額を受け取るようにしてください。その他の留意事項は、同意書の裏面に記載されています。
使用者は、労働者に対して賃金のデジタル払いを賃金受取方法として提示する際は、銀行口座か証券総合口座を選択肢としてあわせて提示しなければいけません。また、労働者に対して、同意書の裏面に記載された留意事項を説明してください。
今後、リーフレットを作成し、このページに掲載することを予定しています。掲載後、賃金支払・受取方法の選択・説明の際などにご活用ください。
その他のQ&Aは以下よりご確認ください。
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)」についての特集ページを開設(2022/12/2更新)
厚生労働省は、「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)」についての特集ページを開設しました。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとなりました。(令和5年4月1日施行)
特集ページでは、「法令、通達等」、「よくあるご質問への回答(労働者、使用者向け)」について記載されております。
周知用資料は、現在作成中で、出来次第、掲載される予定です。また、資金移動業者を指定した際には、速やかに、指定された資金移動業者に関する情報の一覧が掲載される予定です。
通達については、現在以下の2つの通達が掲載されております。
・「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(局長通達1)(令和4年11月28日基発1128第3号)
・「賃金の口座振込み等について」(局長通達2)(令和4年11月28日基発1128第4号)
詳細は、以下よりご確認ください。
「適切な労務管理のポイント」パンフレットのご紹介(2022/11/18更新)
昨今の経済情勢や経営環境の変化の中で、経営状況が悪化したために、やむなく労働条件の変更や雇用調整を行わざるを得ないとする企業もみられます。そのような場合であっても、守るべきルールがあります。
厚生労働省は、労働条件の変更や雇用調整をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる主要な裁判例を取りまとめたパンフレット「適切な労務管理のポイント」を公開しております。
以下のような内容で構成されております。
1. 賃金の支払等
(1)賃金の確実な支払い
(2)退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置
(3)休業手当の支払
2. 労働条件の変更
(1)合意による変更
(2)就業規則による変更
(3)配置転換・出向
3. 解雇・雇止め
(1)解雇の禁止
(2)解雇の効力
(3)解雇の手続
(4)解雇事由
(5)整理解雇
(6)退職勧奨
(7)勤務成績を理由とする解雇
(8)有期労働契約の雇止め
(9)採用内定取消し等
(10)退職時の証明
4. 民事上のトラブルの解決を図るための制度
全体で12ページの資料で、要点がかなり簡潔にまとめられておりますが、掲載されている裁判例は、参考になると思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000920658.pdf