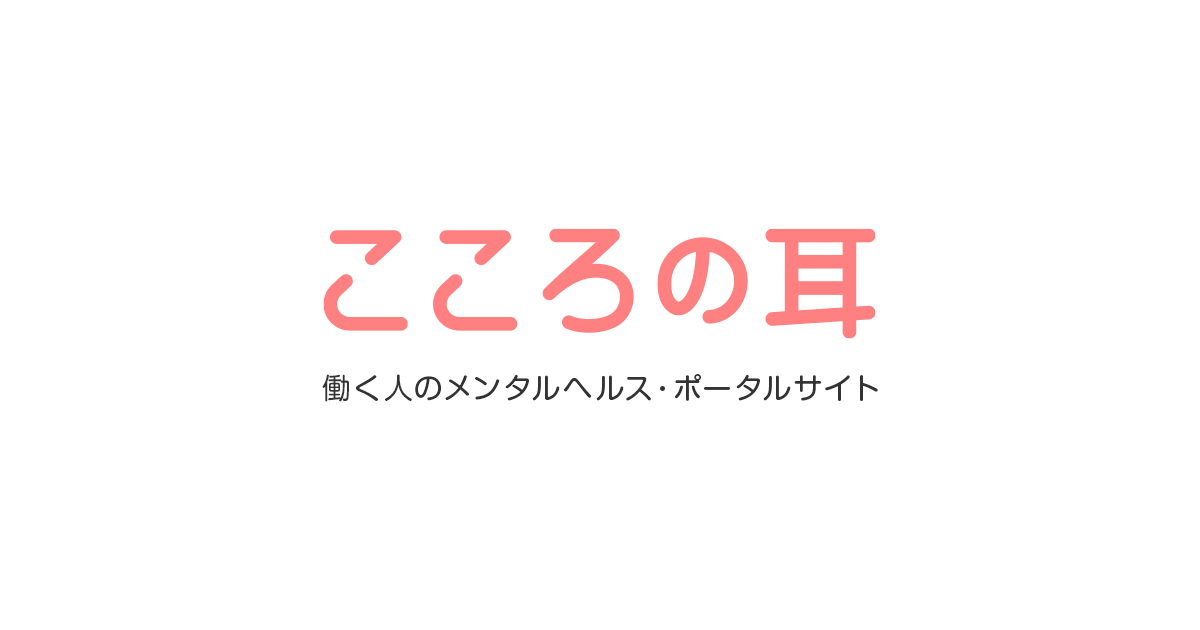
職場のメンタルヘルスケア 季節のコラム」(こころの耳)のご紹介(2025/5/13更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、毎月「職場のメンタルヘルスケア 季節のコラム」を掲載しております。
5月は、「「五月病」とのつきあい方」です。
5月病とは、主に5月の連休明けに心身のバランスを崩し、疲労感やストレスを感じる状態を指します。
コラムでは、五月病への対応策として、ストレス対処法が紹介されております。
その他、「こころの耳」関連サイトとして、5分研修シリーズ「新入社員に見られやすいメンタルヘルス不調の症状やその要因」、5分研修シリーズ「異動後のメンタルヘルスケア」なども紹介されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
「きいてよ!コッコロー」、「ストレス対処法としての生活習慣-食う・寝る・遊ぶの充電法」を公開(2025/4/20更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、3月下旬に以下の2つのコーナーを追加しました。
・「コッコローのご紹介」に「きいてよ!コッコロー」を新たに追加
・「ストレス対処法としての生活習慣-食う・寝る・遊ぶの充電法」を新たに公開
・「きいてよ!コッコロー」
誰かに聞いてほしいことを、コッコローにお話しできるチャットコンテンツです。
今のあなたの気持ちをよかったら話してみてください。
コッコローが一生懸命リアクションをスタンプで返してくれます。
・「ストレス対処法としての生活習慣-食う・寝る・遊ぶの充電法」
食う・寝る・遊ぶの3つの充電機能を上手に使って、ストレスに対処し、毎日を健康に過ごすためのポイントについて紹介しています。
詳細は、以下よりご確認ください。
こころの耳Q&Aに新たなQ&Aを追加(2025/2/9更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、職場のメンタルヘルスに関するよくあるご相談について、「こころの耳」委員会等の職場のメンタルヘルスに関する専門家からのアドバイスを掲載しています。
今回、フリーランス、新入社員の方を対象にした新たなQ&A10問が追加されました。
一例として以下のような質問が掲載されております。
・フリーランスで仕事をしていますが、取引先の担当者から怒鳴られたり、繰り返し報酬の減額を迫られたりしています。仕事の大半がこの取引先からなので、休んだらその間に取引を打ち切られてしまうのではないか、辞めたら経済的に苦しくなってしまうのではないかと心配で、気持ちが休まりません。どうしたらいいでしょうか。
・フリーランスで働いていますが、体調を崩したため、取引先の担当者に契約解除を切り出したところ、担当者がとりあってくれず、今辞めると損害賠償を請求すると言われました。担当者が怖いのでその後言い出せておりませんが、毎日不安で仕事が手につかなくなってきました。契約解除するにはどうしたらいいでしょうか。
・今の仕事はつらいことばかりなので辞めたいのですが、親はつらいことがあっても辞めるなという考えなので納得してくれそうにありません。どうしたらいいでしょうか。
・まだ入社して3か月しか経っていないのですが、辞めたいと思うのは甘えなのでしょうか。
その他、以下のような検索機能でQ&Aの検索も可能です。
詳細は、以下よりご確認ください。
15分でわかるはじめての交流分析①~④(こころの耳)のご紹介(2025/1/2更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイ「こころの耳」では、「15分でわかるはじめての交流分析 ①ストローク編」と、「15分でわかるはじめての交流分析 ②人生の立場編」の内容を新たに更新しました。
また、「15分でわかるはじめての交流分析 ③5つの特性編」と、「15分でわかるはじめての交流分析 ④エゴグラム編」を新たに公開しました。
それぞれの概要は以下の通りです。学習時間の目安は15分です。
①ストローク編
職場などにおいては、自分と他人との交流パターン(人間関係)に着目することで、人間関係の改善や自律的な生き方・自己実現に役立ちます。今回は、他者との関わり(ストローク)を中心に学んでいきましょう。
②人生の立場編
自分と他人との交流パターン(人間関係)に着目することは、職場などにおける人間関係の改善や自律的な生き方・自己実現に役立ちます。今回は、「4つの人生の立場」を中心に学んでいきましょう。
③5つの特性編
「自分らしさ」をつくる心の働きについて理解すると、人間関係の改善や自律的な生き方・自己実現に役立ちます。今回は、「5つの特性」を中心に学んでいきましょう。
④エゴグラム編
自分の5つの特性について分析するために「エゴグラム」が役立ちます。先に「エゴグラムセルフチェック」を実施していただき、結果を手元に置いた上でお読みいただくことを推奨します。
詳細は、以下よりご確認ください。
「こころの耳 5分研修シリーズ」に「病院を受診するか悩んでいる方へ」他1つの動画を公開(2024/12/30更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「ここの耳」では、「こころの耳 5分研修シリーズ」を公開しております。
3~5分程度の短い動画を通じて、セルフケアやラインによるケア、ストレスチェックなどについて、手軽に学べるミニ動画シリーズです。
医師や保健師、社会保険労務士、カウンセラーなどの専門家が、わかりやすく解説しています。
この度、「こころの耳 5分研修シリーズ」に「病院を受診するか悩んでいる方へ」と、「メンタルヘルス不調で会社を休むことに悩んだとき」が新たに掲載されております。
それぞれの動画の概要は以下の通りです。
〇「病院を受診するか悩んでいる方へ」
精神科や心療内科の受診について、自分は甘えているだけなのではないか、自分より大変な人がたくさんいるのに自分なんかが受診していいのだろうか、などと不安に感じてためらっている方もいるかもしれません。受診するかどうかの考え方や、初診時の流れ、よくある質問と答えなどを紹介しています。
〇「メンタルヘルス不調で会社を休むことに悩んだとき」
メンタルヘルス不調で仕事を休むことを勧められても、会社に迷惑をかけるのではないか、弱い人間だと思われてしまうのではないか、などと感じて、躊躇することもあるかと思います。一人で気負わず、回復を最優先にする考え方について紹介しています。
その他にも、たくさん動画が掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
「職場のメンタルヘルスシンポジウム」令和6年度分の動画を掲載(こころの耳)(2024/12/17更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、厚生労働省委託事業「職場のメンタルヘルスシンポジウム」の動画を掲載しています。
「職場のメンタルヘルスシンポジウム」は、その年ごとにテーマが設定され、基調講演、企業担当者による取組事例の紹介、パネルディスカッションなどが行われています。
この度、令和6年度「中小企業におけるメンタルヘルス対策~元気な会社がやっている取組に学ぶ~」が掲載されました。厚生労働省YouTubeを通じて閲覧できます。
動画は、以下の内容が掲載されております。
・あいさつ[3分26秒]
・基調講演「人材定着のために重要なこと」[30分21秒]
・中小企業におけるメンタルヘルス対策の取組事例
3社分掲載されております。[19分38秒][19分27秒][17分00秒]
動画は各パートごとに分割されておりますので、ご興味もあるもののみ視聴することも可能です。自社のメンタルヘルス対策の参考にされてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
こころの耳 5分研修シリーズ」に新たに2つの動画を掲載③(2024/12/5更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「ここの耳」では、「こころの耳 5分研修シリーズ」を公開しております。
3~5分程度の短い動画を通じて、セルフケアやラインによるケア、ストレスチェックなどについて、手軽に学べるミニ動画シリーズです。
医師や保健師、社会保険労務士、カウンセラーなどの専門家が、わかりやすく解説しています。
この度、「こころの耳 5分研修シリーズ」に「新入社員へのラインによるケア」と、「ご家族がメンタルヘルス不調の方へ2(ご自身のケア)」が新たに追加されました。
それぞれの動画の概要は以下の通りです。
〇「新入社員へのラインによるケア」
新入社員は、学生生活からの大きな変化に直面し、緊張や不安を感じやすいものです。緊張が大きいと、疲れやすくなり、体調を崩すこともあります。新入社員に対するラインによるケアのポイントと考え方について紹介しています。
〇「ご家族がメンタルヘルス不調の方へ2(ご自身のケア)」
メンタルヘルス不調のご家族を支えながら、一緒にいるのがしんどく感じる、家族のサポートから少し離れたい、などと感じることもあるのではないでしょうか。自分を大切にすることが、ご家族の支援につながります。ご自身のケアのポイントや、サポーターを持つ方法について紹介しています。
その他にも、たくさん動画が掲載されております。
ご興味のある方は、視聴されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
「こころの耳 5分研修シリーズ」に新たに2つの動画を掲載②(2024/11/24更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「ここの耳」では、「こころの耳 5分研修シリーズ」を公開しております。
3~5分程度の短い動画を通じて、セルフケアやラインによるケア、ストレスチェックなどについて、手軽に学べるミニ動画シリーズです。
医師や保健師、社会保険労務士、カウンセラーなどの専門家が、わかりやすく解説しています。
この度、「こころの耳 5分研修シリーズ」に「上司との関係に悩んでいる方へ」と、「メンタルヘルス不調の従業員の家族と連携する際の留意点」が新たに追加されました。
〇「上司との関係に悩んでいる方へ」
上司とうまくいかず悩んでいる方は少なくないと思います。上司との関係が良好であれば、職場での快適さが増し、お互いに助け合う雰囲気が醸成され、モチベーションが高まることも期待できます。上司とうまく付き合うための考え方やポイントについて紹介しています。
〇「メンタルヘルス不調の従業員の家族と連携する際の留意点」
従業員がメンタルヘルス不調などにより長期に休んで療養する場合は、安全に療養生活を送ることができるよう、家族の理解や支援を得ることが望ましいと考えられます。しかし、実際には、家族への情報提供がスムーズにいかないケースも少なくありません。家族と連携しようとする場合の留意点について紹介しています。
その他にも、たくさん動画が掲載されております。
ご興味のある方は、視聴されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
「こころの耳 5分研修シリーズ」で新たに2つの動画を公開①(2024/11/15更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「ここの耳」では、「こころの耳 5分研修シリーズ」を公開しております。
3~5分程度の短い動画を通じて、セルフケアやラインによるケア、ストレスチェックなどについて、手軽に学べるミニ動画シリーズです。
医師や保健師、社会保険労務士、カウンセラーなどの専門家が、わかりやすく解説しています。
この度、「こころの耳 5分研修シリーズ」に「怒りの感情との付き合い方」と、「ご家族がメンタルヘルス不調の方へ1(相手への接し方)」が新たに追加されました。
〇「怒りの感情との付き合い方」
怒りは迫りくる脅威と戦うために必要な感情であり、危険を回避するための防衛本能です。しかし、時に他者との関係性を悪化させてしまうこともあります。怒りをうまくコントロールして上手に付き合っていくことが大切です。怒りの感情をコントロールするためのおすすめの方法を紹介しています。
〇「ご家族がメンタルヘルス不調の方へ1(相手への接し方)」
メンタルヘルス不調のご家族を支えながら、先行きが見えない不安に襲われたり、どのように接したら良いか不安に感じたりすることもあるかと思います。接し方のポイントを知り、あなた自身が気持ちのゆとりを持てることは、ご家族のサポートを続けていくために大切です。メンタルヘルス不調のご家族への接し方のポイントについてお伝えしています。
その他にも、たくさん動画が掲載されております。
ご興味のある方は、視聴されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
職場メンタルヘルスケア 季節のコラム」のご紹介(2024/10/13更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、毎月、「職場メンタルヘルスケア 季節のコラム」を掲載しております。
10月は「健康の秋 ~心身の健康を考える~」です。
コラムでは、職場におけるストレスレベルや疲労蓄積度を測定できるツール「5分でできる職場のストレスセルフチェック」、「働く人の疲労蓄積度セルフチェック(働く人用)」や働きやすい職場づくりについて解説する動画コンテンツ「動画で学ぶ『職場環境等の改善』」などが紹介されております。
そのほか、職場のメンタルヘルスの専門家や各界の有識者が書かれたコラムも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
令和6年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム(こころの耳)のご紹介(2024/9/25更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、11月29日(金)にオンラインで開催される『令和6年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム「中小企業におけるメンタルヘルス対策~元気な会社がやっている取組に学ぶ~」』の案内を掲載しております。(参加無料)
プログラムは、以下の内容となっております。
・挨拶(13:30~13:35)
・基調講演 (13:35~14:05)
「人材定着のために重要なこと」
・中小企業におけるメンタルヘルス対策の取組事例 (14:05~15:25)
・講演者、事例発表者によるパネルディスカッション (15:35~16:30)
Zoomでの参加は、先着500名(事前予約必要)で、YouTube参加は予約不要とのことです。
ご興味のある方は参加されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
コラム「社会保険労務士に聞いてみよう-メンタルヘルスQ&A-」のご紹介(2023/4/8更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、コラム「社会保険労務士に聞いてみよう-メンタルヘルスQ&A-」という記事が掲載されております。
多くの企業で抱えていると思われるメンタルヘルス関連の事案に対し、社会保険労務士がQ&A方式回答しております。
どの記事も3~5分程度で読むことができます。現在、以下の12個のコラムが掲載されております。
・第1回 休職中の社員が職場復帰を申し出てきたら
・第2回 従業員50人未満の小さな企業でのメンタルヘルス対策
・第3回 社員がメンタルヘルス不調で休業することになったら
・第4回 休業中の社員への連絡と確認
・第5回 診断書等の個人情報の取扱いに関する注意点は?
・第6回 復職前の試し出勤時の労災補償や傷病手当金等の注意点は?
・第7回 こころの病で再休職した場合、傷病手当金を再度支給できる仕組みはあるの?
・第8回 退職後、傷病手当金の仕組みはどうなっているの?
・第9回 病気で退職する社員の退職後の社会保険は?
・第10回 メンタルヘルス不調で休職中の社員が退職する場合雇用保険はもらえるの?
・第11回 休職手続き前に会社側が有給休暇取得を促すことはできるの?
・第12回 メンタルヘルス不調における治療と仕事の両立支援の注意点は?
質問、ポイント、回答という形式で要点が簡潔にまとめられており、人事労務担当の方が、上記テーマについての社内での取組を検討する際、その第一歩として、全体像を理解するのに役立つと思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
「こころの耳 5分研修シリーズ」に新たな動画を掲載(2023/12/15更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、「こころの耳 5分研修シリーズ」を掲載しております。
本コンテンツは、3~5分程度の短い動画を通じて、セルフケアやラインによるケア、ストレスチェックなどについて、手軽に学べるミニ動画シリーズです。
医師や保健師、社会保険労務士、カウンセラーなどの専門家が、わかりやすく解説しています。
今回、「相談することが苦手な方へ」と、「うつ病などの治療をしながら働く方へ」、「休業時に使える主な支援制度」が新たに追加されました。
◆「相談することが苦手な方へ」
人に相談すると相手に心配をかけてしまう、どうせ解決しないなどと考えて一人で抱え込んでいませんか。相談することが苦手な人は少なくありません。相談することの効果や、相談する勇気の持ち方についてお伝えしています。
◆「うつ病などの治療をしながら働く方へ」
うつ病などの精神疾患を抱えながら仕事をされる方の中には、体調などの事情から、治療と仕事の両立に悩まれる方も多いのではないかと思います。頑張りすぎず仕事をするためのポイントについて紹介しています。
◆「休業時に使える主な支援制度」
休業期間を安心して過ごせることは心の健康の回復のために重要です。メンタルヘルス不調などで休業に入る際に使える主な支援制度について、傷病手当金や自立支援医療制度、企業等が独自に行っている支援などを紹介しています。
動画は、以下よりご確認ください。
「働く人の疲労蓄積度セルフチェック(働く人用)」のご紹介(2023/12/12更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、「働く人の疲労蓄積度セルフチェック(働く人用)」と「働く人の疲労蓄積度セルフチェック(家族支援用)」を、厚生労働省「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」(2023年改正版)の内容に合わせてリニューアルしました。
◆「働く人の疲労蓄積度セルフチェック(働く人用)」
2つのSTEPによる簡単な質問から、あなたの職場における疲労蓄積度を測定します。
本チェックでは、健康障害防止の視点から、これまでの医学研究の結果などに基づいて、疲労蓄積度が判定できます。
質問は全部で27問です。(所要時間約5分間)
STEP1:最近1か月間の「自覚症状」⇒14問
STEP2:最近1か月間の「勤務の状況」⇒13問
STEP1とSTEP2の回答結果に基づき、それぞれ4段階のレベルで判定され、疲労蓄積度は0~7点で判定されます。また、判定結果について簡単なコメントが記載されます。
◆「働く人の疲労蓄積度セルフチェック(家族支援用)」
2つのSTEPによる簡単な質問から、ご家族で働いている方の職場における疲労蓄積度を測定します。
質問は全部で22問です。(所要時間約5分間)
STEP1:最近1か月の「疲労・ストレス症状」⇒13問
STEP2:最近1か月の「働き方と休養」⇒9問
STEP1とSTEP2の回答結果に基づき、それぞれ「高い」「低い」の2段階のレベルで判定され、疲労蓄積度は0~2点で判定されます。また、判定結果について簡単なコメントが記載されます。
ご自身の疲労蓄積度を一度測定されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正(2023/9/6更新)
厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。

この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。
【認定基準改正のポイント】
〇業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
〇精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
〇医学意見の収集方法を効率化
・専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
詳細は、以下よりご確認ください。
「性別違和について相談を受けた方へ」(こころの耳 5分研修シリーズ)のご紹介(2023/7/15更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、様々なテーマについて短時間で学べる「こころの耳 5分研修シリーズ」を公開しております。
3~5分程度の短い動画を通じて、セルフケアやラインによるケア、ストレスチェックなどについて、手軽に学べるミニ動画シリーズです。
医師や保健師、社会保険労務士、カウンセラーなどの専門家が、わかりやすく解説しています。
同僚によるケアの項目に、「3. 性別違和について相談を受けた方へ」が掲載されております。
日本人におけるLGBTの割合は10%近くと言われます。性的違和を感じている方から相談を受けることは珍しいことではないかもしれません。
性的違和に関する相談を受けた時のポイントについて紹介しています。
動画は以下よりご確認ください。
つらい気持ちになったときに見てみていただきたいコンテンツ、動画について(こころの耳)(2023/7/14更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、ストレスを感じることが多い、人間関係がうまくいかない、理解してくれる人が周囲にいない、将来が不安で仕方がないなど、つらい気持ちを抱えている方への、動画やコンテンツを公開しております。
動画は約3分半です。
また、「つらい気持ちになったときに見てみていただきたいコンテンツ」では、以下のコンテンツが紹介されております。
・こころの病 克服体験記 (サイト内)
心の病を克服した人からの体験記です。
・全国医療機関検索
心の病は、早期発見·早期治療が大事です。1人で悩まないで専門医に相談しましょう。
・失業·生活困窮などでお困りの方の救済制度(セーフティネット)
失業や生活困窮でお困りの方に生活や雇用に関する社会保障の一部を紹介しています。
・まもろうよこころ
相談窓口、ゲートキーパー、自殺対策の取り組みなどの情報がわかりやすくまとめられています。
・生きづらさを感じている方々へ
相談窓口や、Buzzfeed配信番組「もくもくニュース #なんか生きづらいかも」などを紹介しています。
その他、相談窓口なども紹介されております。
以下よりご確認ください。
「中小企業の事業主の方へ~メンタルヘルスケアに役立つコンテンツ~」を公開(こころの耳)(2023/6/27更新)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、「中小企業の事業主の方へ~メンタルヘルスケアに役立つコンテンツ~」を公開しました。
中小企業は従業員数が少ないため、一人ひとりが持っている力を十分に発揮できることが会社にとっても重要となります。一方で、メンタルヘルスケアに十分な時間を割く余裕がないという事業主の方も少なくないと思います。
本ページでは、中小企業の事業主の皆様にも手軽に活用いただける、従業員のメンタルヘルスケアに役立つコンテンツや情報などが紹介されています。
具体的には、以下の事項が掲載されております。
〇第14次労働災害防止計画における中小事業者のメンタルヘルス対策
〇中小企業で活用できるコンテンツ
・はじめて「こころの耳」をご覧になる方へ
必要な情報を見つけていただくポイントについて案内されています。
・従業員のセルフケアに役立つコンテンツ
従業員が自分自身のメンタルヘルスのセルフケアをするために役立つコンテンツが紹介されています。
(1)うさぎ商事の休憩室~みんなで知りたいメンタルヘルス~
(2)eラーニングで学ぶ「15分でわかるセルフケア」
(3)こころの耳 5分研修シリーズ「生活習慣と睡眠からはじめるセルフケア」
(4)パンフレット「Selfcare こころの健康 気づきのヒント集」
・事業場が行うメンタルヘルス対策やラインによるケアに役立つコンテンツ
(1)メンタルヘルス推進室へようこそ~事業場内メンタルヘルス推進担当者の奮闘記~
(2)eラーニングで学ぶ「15分でわかるラインによるケア」
(3)こころの耳 5分研修シリーズ「日頃からの部下への声かけ」
(4)パンフレット「Relax 職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」
(5)パンフレット「中小企業事業者の為に産業医ができること」
(6)ストレスチェック制度について
(7)小さな会社のためのこころの健康づくりお役立ちツール
〇相談窓口
・労働者の方向けの相談窓口
(1)働く人の「こころの耳相談」
(2)相談窓口案内
・メンタルヘルス対策の取組みに関する相談窓口
(1)産業保健総合支援センター(さんぽセンター)
(2)地域産業保健センター(地さんぽ)
〇中小企業におけるメンタルヘルス対策の取組事例
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」の最新版を公開(2023/4/27更新)
厚生労働省は、労働安全衛生法第66条の10において規定しているストレスチェック制度について、各事業場において円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検等を行う「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を、厚生労働省が委託運営するサイトにて公開しています。

今般、本プログラムの最新版(ver.3.6)がダウンロードサイトにて公開されました。
主な実施手順は、以下の通りです。
①初期設定
・プログラムの設置・設定
②受験
③受験後
・高ストレス者判定
受検者一覧と高ストレス者該当者を表示・印 刷・PDF保存、Excel、CSV保存できます。
・個人結果出力
受検者毎のストレスチェック結果を表示・印 刷・PDF保存できます。
・職場結果出力
職場ごとの集団分析結果を表示・印刷・PDF保 存できます。
・面接指導管理
高ストレス者の一覧が表示され、面接指導対象 か等を記録できます。
・報告用データ
労働基準監督署へ報告する情報を表示できます
詳細は、以下よりご確認ください。
Google マップは現在の Cookie 設定では表示されません。「コンテンツを見る」を選択し、Google マップの Cookie 設定に同意すると閲覧できます。詳細は Google マップの[プライバシーポリシー]をご確認ください。Cookie の利用は、[Cookie 設定]からいつでも変更できます。



















